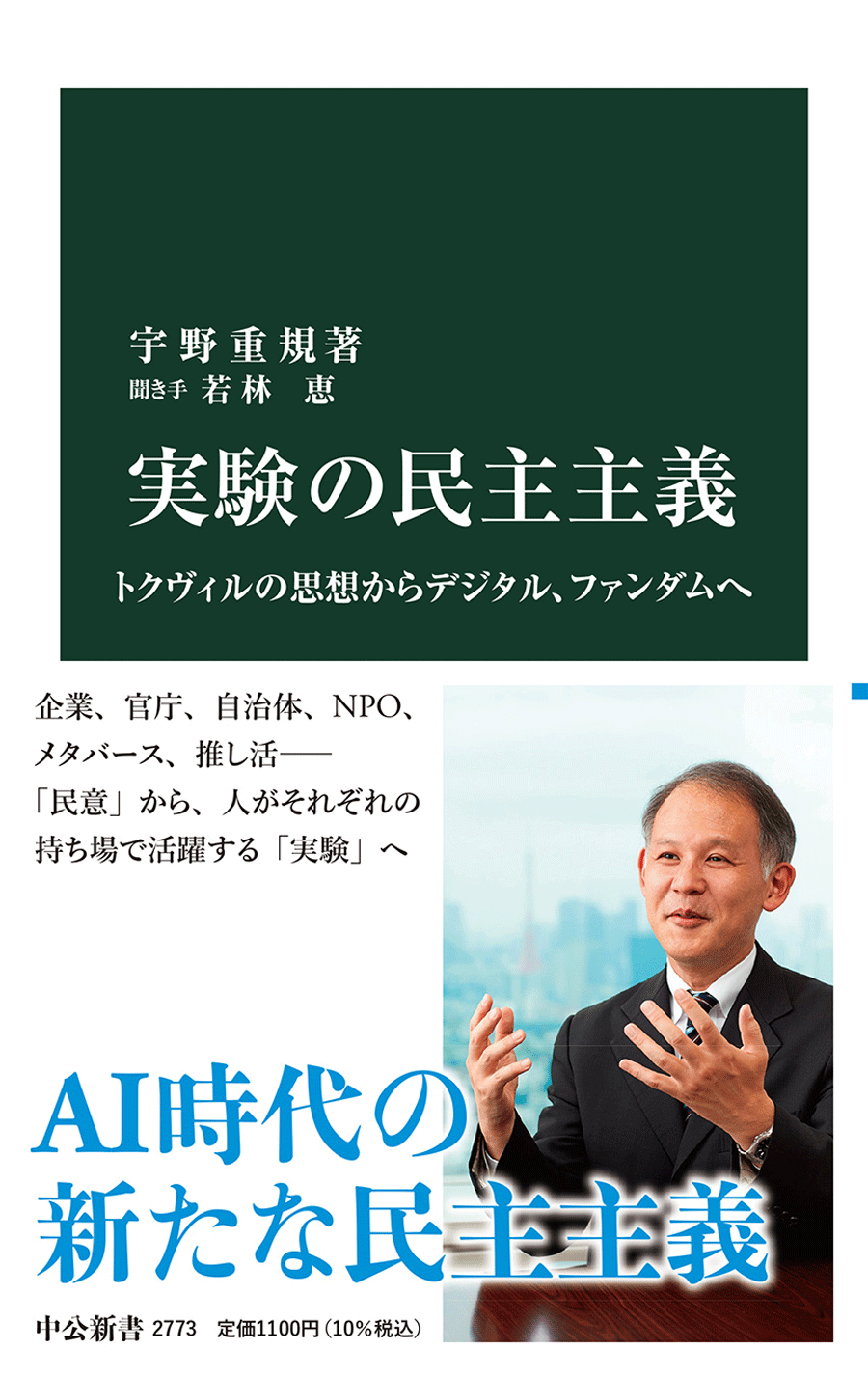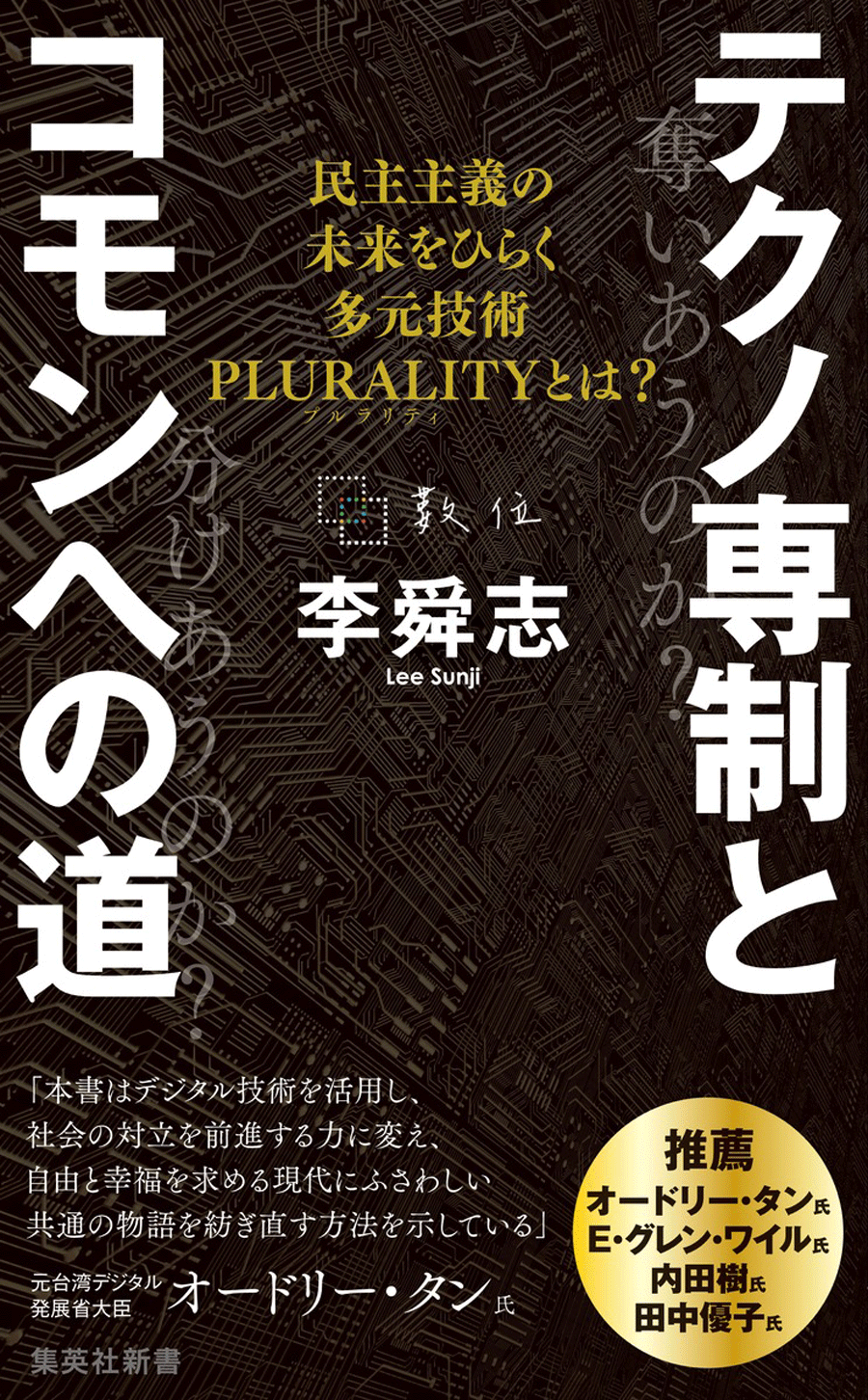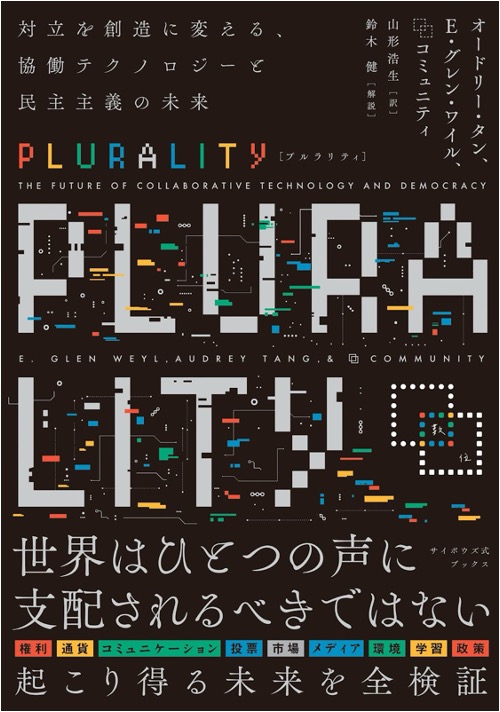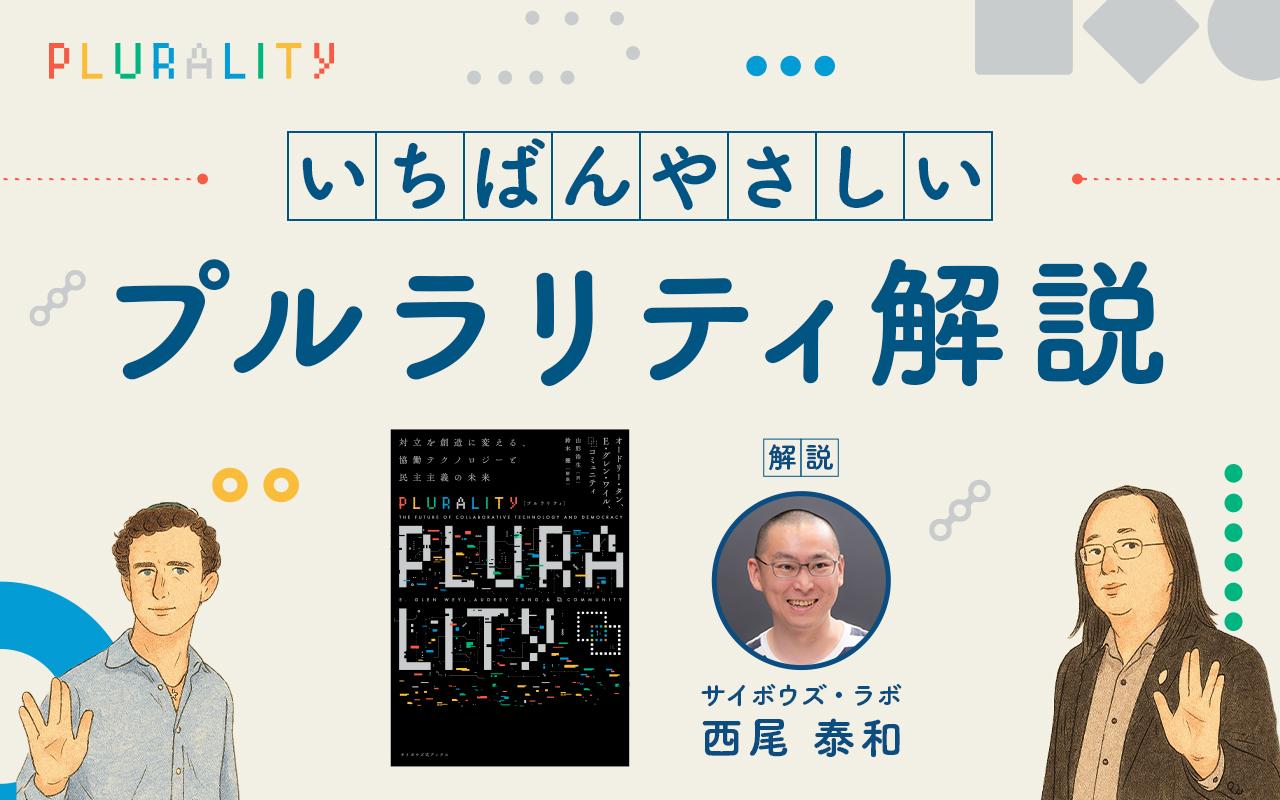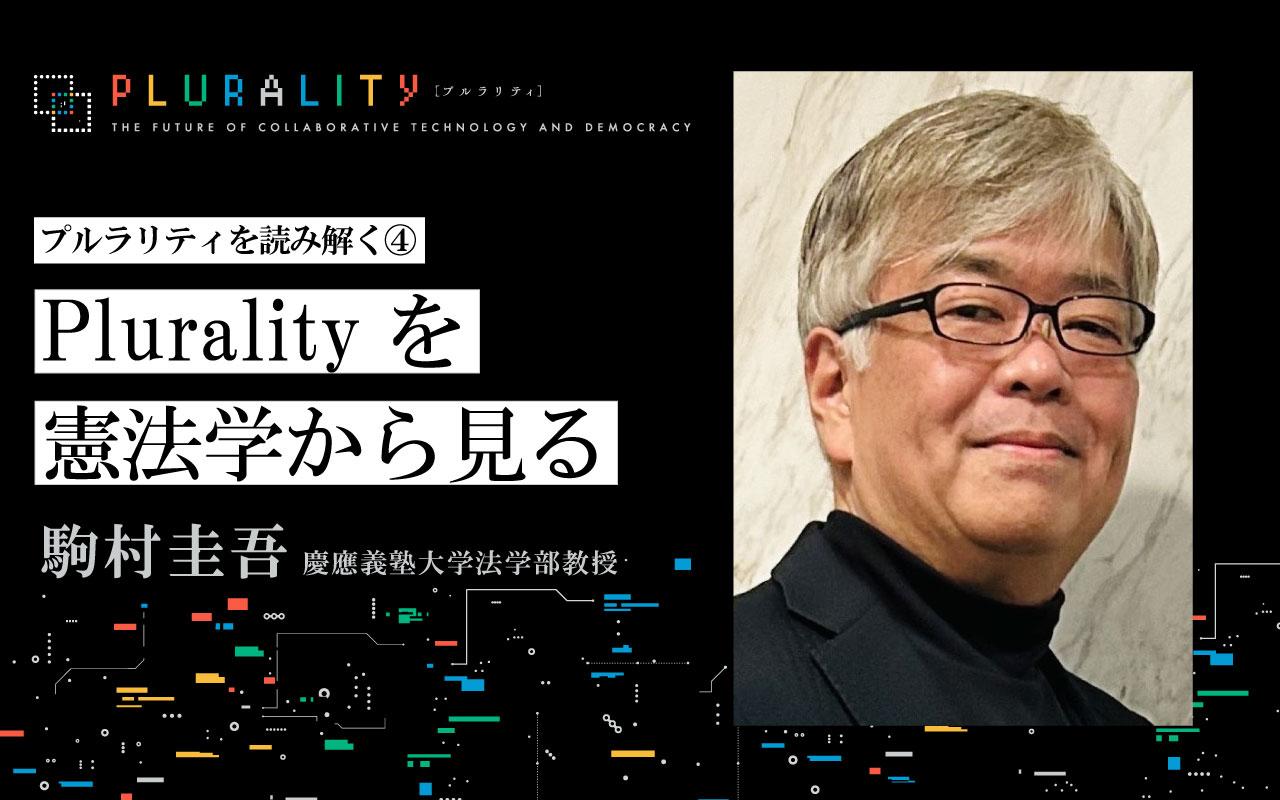「わかりあえない」から進むテクノロジー
政治的思考とテクノロジー トクヴィル・デューイ・アーレントの導き──宇野重規
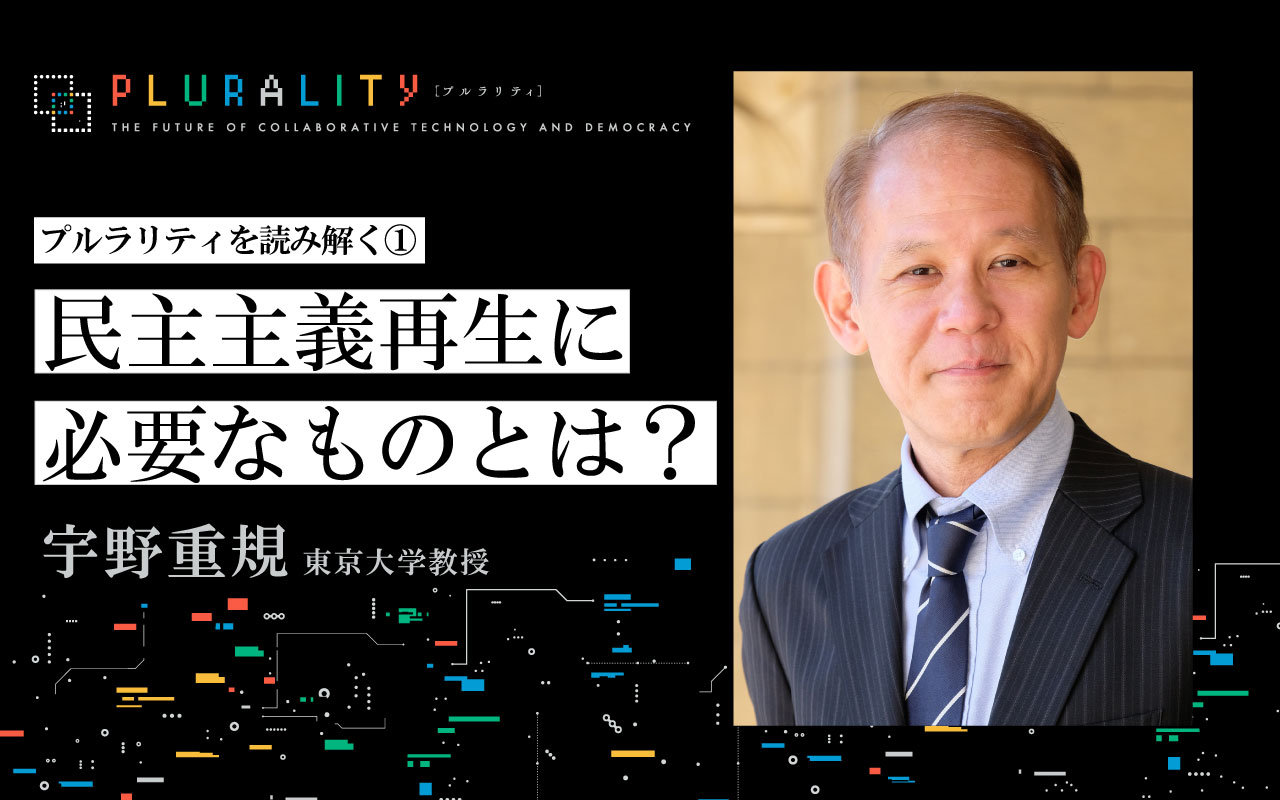
2025年5月2日に、サイボウズ式ブックスより『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』が刊行されました。
また、2025年6月17日には、集英社新書より『テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?』が刊行されています。
Plurality(プルラリティ)は「多元性」を意味し、台湾のデジタル民主主義を牽引する初代デジタル大臣オードリー・タンとマイクロソフト首席研究員にして気鋭の経済学者E・グレン・ワイルが提唱する新たな社会ビジョンです。
AIや大規模プラットフォームは世界をつなぐ一方で、フェイクニュースの蔓延や中央集権的な監視などによって民主主義を脅かし、社会的分断を深めています。
本書の中で著者たちは単一の視点ではなく多様な考え方を認め、テクノロジーと民主主義の共生を目指すことで、社会的・文化的な違いを超えた相互理解と尊重を育む新たな道を示しています。
この記事では「プルラリティを読み解く」と題して、各界の識者にそれぞれの視点からプルラリティをどう見るかについて寄稿いただきました。
第1回は東京大学教授で『実験の民主主義』(中公新書)などの著作がある宇野重規さんです。
「象徴」と「鬼才」による快著
オードリー・タンとグレン・ワイルによる『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義』は、政治思想史を研究する筆者にとって、まさに快著である。二人の天才が、ぐっと自分の近くにまで来てくれたというのが、本を読んでの最初の感想である。
もちろん二人の仕事には、これまでも強い関心を抱いてきた。オードリー・タンは、市民による政治参加とテクノロジーを結びつけた、まさにシビック・テック理念の象徴であるし、グレン・ワイルは公正な市場と民主主義を結びつけ、私的所有に大胆に切り込んだ鬼才である。濃淡こそあれ、親しみと敬意を感じてきた二人の著者が手を組んで書いた真の共著、しかも二人をつなぐのは『なめらかな社会とその敵』の著者である鈴木健とあれば、本を開いたときにときめきのようなものを感じたとしても、軽薄とそしられることはないだろう。
しかしながら、驚いたことに、本を読み進めていてまず出会ったのは、筆者が長年研究してきた思想家アレクシ・ド・トクヴィルである。地方自治などの活動を通じて、市民が日常的に協力し合い、地域の課題を自ら解決していくことが民主主義の礎となると説いた一九世紀フランスの思想家が、本書では当然のように登場する。「深く多様で、非市場的で分散化した社会市民的なつながりがないと、民主主義は機能しないのだ」(同書39頁)。筆者自身、トクヴィルが民主主義社会の鍵であるとしたアソシエーション、すなわち個人の自発的意思に基づく社会的結合を現代的に生かすものとして、ファンダムの原理に着目している。デジタル民主主義を支えるためにも、リアルな人間関係の活性化が不可欠であろう。
実験を許すのが民主主義社会である
次に着目したのは、筆者がやはり研究してきたアメリカの思想家ジョン・デューイへの言及である。民主主義とは、人々が多様な社会的実験をすることを許す社会にほかならない。答えのない時代だからこそ、多様な個人のイニシアティブによる実験が必要であり、それを許すのが民主主義社会である。このように説くプラグマティズムの理論家デューイは、現代においてまさに注目すべき思想家であると筆者は考えている。本書ではさらに、デューイのもとで学んだ中華民国の哲学者である胡適を通じて、その理論が台湾の教育政策に深く影響を及ぼしたことが強調されている。その意味でデューイがまさに、アメリカと東アジアの国々をつなぐ大切な思想家であることも、本書の大切なメッセージである。民主主義をめぐる太平洋を超えた対話が期待される(トランプ時代だからこそ、なおさら)。
そして何より、『PLURALITY』というタイトルにもなっている「多数性(複数性)」の概念を鮮やかに示したのは、ハンナ・アーレントである。筆者は『全体主義の起源』や『人間の条件』などアーレントの著作を、大学院の演習などで繰り返し読んできた。人間の生の根本的な条件を、平等な他者とともに存在する複数性に見出したアーレントは、筆者の思考をつねに刺激し、突き動かしてきた思想家の一人である。人が複数存在するからこそ公共性が生まれ、そこに言葉の力を介して政治の営みが始まる。社会的差異は対立を生み出すが、もしテクノロジーを介して適切に協力関係を築くことができれば、それは社会にとってマイナスではなく、むしろ進歩を生み出す原動力となる。アーレントの思想を魅力的な現代的概念として甦らせた二人の知的営為は、「コラボレーション」という言葉と共に、私たちの未来を切り開くだけのパワーがあると思う。複数の主体の間の緊張に満ちた関係に着目する「多数性(複数性)」を今こそ強調したい。
民主主義の再生のカギはテクノロジーの支援
筆者は「Plurality」の前提になっている危機意識を深く共有する。人工知能は中央集権化されたトップダウンの統制を強化し、ブロックチェーンは人々を孤立させ、過激な見方に走らせるかもしれない。さらに、専制主義勢力はSNSなどを利用して、民主主義国家内部の分断や紛争を煽り立てている。その意味で、現代世界において優位に立つのは、テクノクラシーとテクノ・リバタリアンの影響ばかりなのかもしれない。
しかし私たちは無力ではないはずだ。テクノクラシーとテクノ・リバタリアンに対抗して、今こそデジタル民主主義のポテンシャルを活性化すべきなのではなかろうか。民主主義を再生させるために、私たちは今こそ力を合わせなければならないが、本書はそのための勇気を与えてくれる。
多数性(複数性)を否定しようとする権威主義に対して、私たちは戦っていかねばならない。そのためにはテクノロジーに支えられた政治的思考が不可欠である。本書をそのための宝箱として活用する読者が一人でも増えることに期待している。
宇野重規(うの・しげき)
1967年生まれ。東京大学社会科学研究所教授。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。専門は、政治思想史、政治哲学。著書に『政治哲学へ』(東京大学出版会)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社学術文庫)、『〈私〉時代のデモクラシー』(岩波新書)、『民主主義のつくり方』(筑摩選書)、『保守主義とは何か』(中公新書)、『民主主義とは何か』(講談社現代新書)、『日本の保守とリベラル』(中公選書)『実験の民主主義』(中公選書、若林恵との共著)などがある。
「わかりあえない」から進むテクノロジー
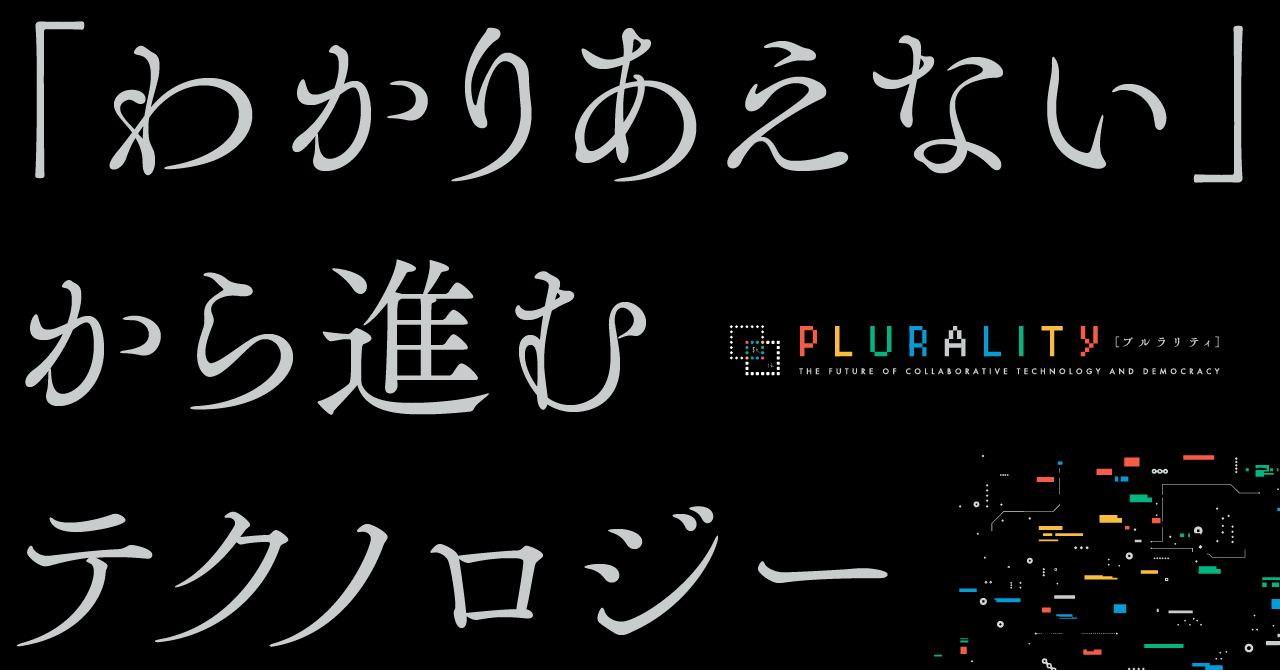
テクノロジーは「人をつなぐもの」であるはずが、進化の過程で人々の対立を生むようになってしまった。どうすれば私たちは、いまの状況から前に進むことができるのか? 多様な意見にあふれる社会で、わかりあえなさを抱えたまま生きていく。「敵」と「味方」を超越し、対立を創造に変える。そんなテクノロジーとコミュニケーションの話をしたい。
SNSシェア
編集

高部 哲男
コーポレートブランディング部サイボウズ式ブックス所属。編集プロダクション、写真事務所、出版社などを経て、2020年サイボウズ入社。「はたらくを、あたらしく」を合言葉に、多様な働き方、生き方、組織のあり方などをテーマにした書籍制作に日々奮闘中。複業として社外での書籍編集にも関わる。