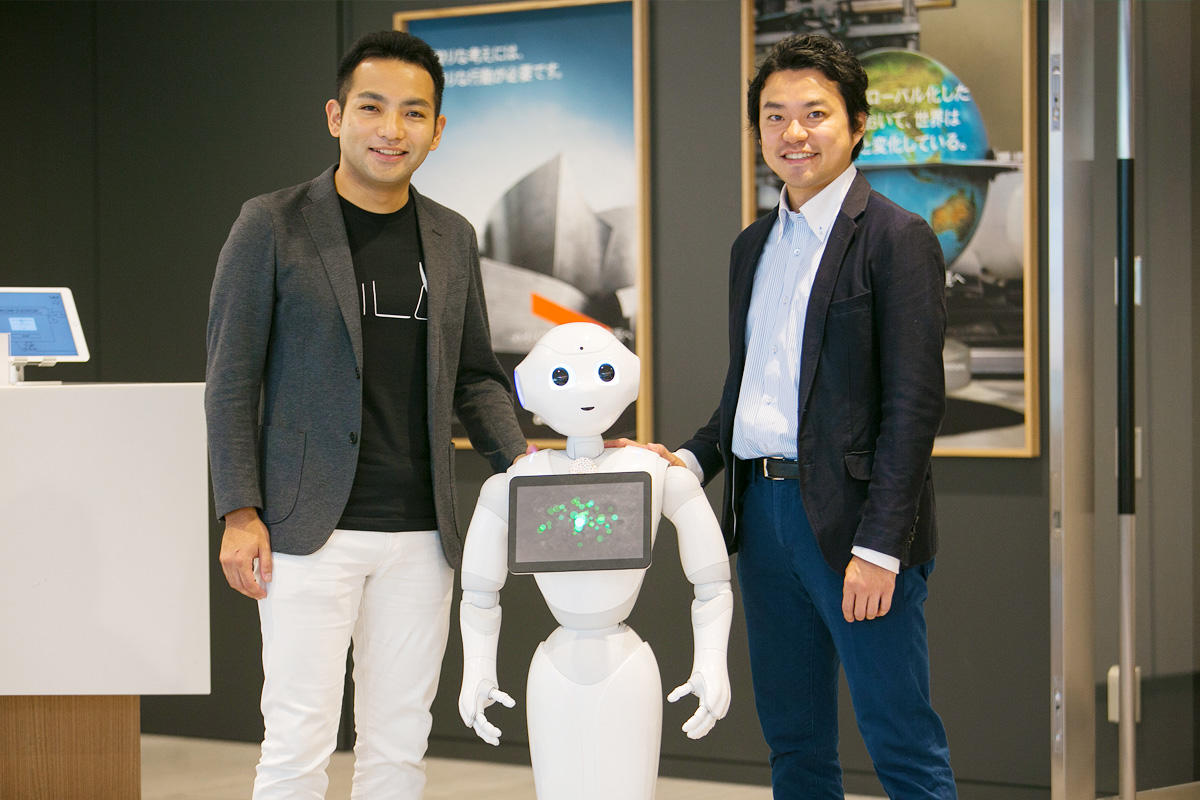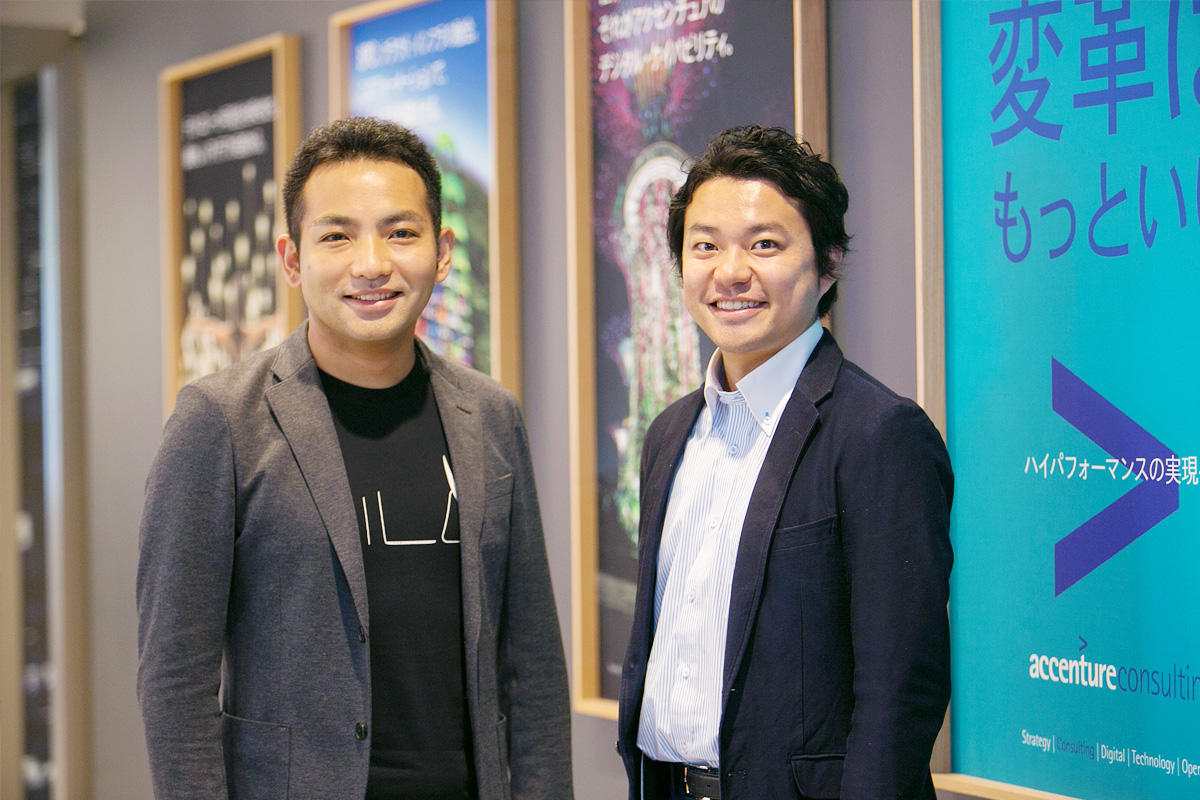あのチームのコラボ術
初期の段階では想像もしていなかったことが起こることがシゴト- 一冊入魂の流儀(後編)
前編「2拠点体制の出版社、そこにいるから拾える声を届けるー一冊入魂の流儀」に続いて、後編をお届けします。後編では引き続き、本づくり、そして仕事について三島社長に伺います。いかに企画書から離れたものをつくるか、いかに当初想像もしなかったことが起こるかが仕事の醍醐味であると話す社長。出版業界に新しい風を吹き込むミシマ社の、一冊入魂の流儀をご紹介します。
いかに企画書から離れるかが本づくりであり、仕事である
育てるじゃなく、育つという感覚なんでしょうか。そういう人であってほしいってことなんですね。
大槻
![]()
本って、入稿してひとつの形になったら、もう完全に自分たちの手を離れていくんです。あとは読者とのあいだで、それぞれ育っていく。だから、コントロールするっていう意識はあまりないですね。ビジネスでも、目標の部数やアクセス数から逆算してしまいがちですけど、そうじゃないんじゃないかっていう意識がすごくあって。答えを求めるっていうことが、やたら強すぎると思うんです。

たしかに、数値目標から逆算して考えてしまいがちですね。
大槻
![]()
ミシマ社は、創業当初から「原点回帰の出版社」ということを謳ってますけども、最近すごく面白かったのが能楽師の安田登先生のお話で。中国古代から、中国では「問う」っていう言葉の対義語が「答える」だったと思われていますが、問うに対する対義語はそもそも答えるではなかった。「問う」と「答える」がセットで考えられるようになったのは、近代のちょっとした短い間の話で。人類において、問うということはひとつの能動的な行為で、あくまで問うだけなんですよ。
その発想はなかったです・・・ 「問い」を立てることそれ自体が1つの完結する行為であると。
大槻
![]()
そもそも答えはないっていうところから始まっている。それを便宜上、効率的にいろんなことを動かして生産性を上げるための近代のロジックによって、答えるってことが対になってきた。仕事においても、このやり方が正しいとされるものがあったり。僕は、答えを先に設定してやる仕事っていうのは、ちょっとつまらないって思っています。
その答えっておっしゃっているのは、仮説に置き換えてもいいんでしょうか。
大槻
![]()
仮説というか、数的目標ですね。もちろん仕事は遊びじゃないですから、数的なものを常に満たさないといけない。でも、そこにいくために逆算してやっていくっていうものだと、どうしてもパワーが出ないというか。結果はその通りになるんですけど、なんだかこじんまりとしたものになってしまう。仕事って、初期の段階では想像もしていなかったことが起きるっていうことだと思っていて。
それは面白い考え方ですね。
大槻
![]()
前の会社で、三島さんのつくる本はいつも企画書と全然違うって言われたことがありました。当たり前だろって思ったんですよ。企画書からいかに離れるかっていう本づくりしかしていなかったので。編集者がそういうことを意識していたら、著者もそこに反応してくれるので、著者自身もこんな風に書くと思っていなかったというような原稿が出来上がってくるんです。そうして一冊の本になったものが、初めて生命力、命を持ったものになる。
ミシマ社が掲げる、まさに一冊入魂の書が生まれるんですね。
大槻
![]()
企画書通りの本っていうのは、工業製品をつくってるのと同じです。それはあくまでもプロダクトでしかなくて、一つの生命体ではない。商品ではあるけれど、本当のプロダクトは生命を持ったものではなくていけないので。最初の出版社ではとにかく売ることが価値で、それはそれで重要なことですけど、その両方が大事だと思っています。

「企画書からいかに離れられるかで、本に生命が生まれるんです」
バランスがすごく難しそうですね。
大槻
![]()
2年前に、河出書房さんから出していただいた私の著書に『計画と無計画のあいだ』があります。計画通りにやるっていうのは優等生的な答えでしかなくて、一方で、本当に無計画で何も考えずに毎日適当にやっていますっていうのもそれは仕事じゃない。無計画でやれる範囲っていうのは、自分の感覚を最大限に使って、その範囲内で大きな一歩を踏み謝らないっていう部分のことで。計画通りにやっていくのはマニュアル的で、それはできると思うんですが、ここのあいだの範囲がどれくらいかっていうのがその人の仕事のキャパかなと。
なるほど。やりたい人のやる気がすべてであって、数字ではないんですね。ミシマ社さんでも、メンバーと一緒に仕事をする上で重視しているのはそこなんですか?
大槻
![]()
なんかみんなが生き生きと楽しくしていてほしいです。それを、この『仕事のお守り』っていう本に詰め込みました。いまビジネス書って、2週間で仕事が100倍できるための本みたいな、結果を出すための本で溢れかえっていますよね。何かを決めて、そこに向かうっていう。
若い頃の自分も、そういう本をよく読んでいました・・・
大槻
![]()
だけど仕事ってそういうものじゃなくて、そういうのはどれも通過点でしかない。じゃあ、なんで目標的なものがあるかというと、目標を達成することは当然で、それによってその人のキャパが人間的に広がったり、成熟したりするからだと思うんですよ。設定された高いハードルを目指すときに、おそらくいまの自分のやり方だけではたどり着けないので。自分のなかに、これまでにない異物を取り入れていかなきゃいけない。閉じている人には絶対に無理ですよね。新しいことを吸収できないし。なんかよくわからないけれど、とにかくやってみるっていうことが伸びていくために何より大事だと思っています。
異物を取り入れることで、成長し、成熟していくと。
大槻
![]()
自分が尊敬する方々が出してくる球って、意味がわからないんですね。たとえば、会社をつくるときも、いまも師と仰いでいる内田樹先生のところに相談に行きました。「出版社をつくろうと思うんです」、って言うか言わないかのところで、「それがいいよ」って。
何か、先回りされた感じですね(笑)。
大槻
![]()
そんな風に言われたら、そこから後退できないんですよ。相談じゃなくて、そこからのスタートになるというか。自分から頼む前から、先生が「僕、原稿はぜんぶそっちで書くから」って。そうしたら、もうなんとしてもいい出版社にするしかないってところにスイッチが切り替わる。
会議は月曜の朝のみ、あとは動く
ちょっと話題が変わりますが、普段はどういう風に仕事をされているんですか?
大槻
![]()
毎週、月曜の朝の全体ミーティングから始まります。その時間に、企画会議、営業のミーティングも全部やって、決めることを決める。アイディアがある人も出してもらう。その場で大きな方向の共有をして、あとは各自が動く。無駄な会議とか形式的な会議が嫌いなんです。
一緒に仕事をしていく中で、先ほど個人個人のパッションが大事だっていうお話がありましたけど、共同作業で何か工夫されていることはありますか。
大槻
![]()
朝の掃除もそうです。あと、ひとりでミシマ社を始めたときに、たまたま三島大社に行くことがあって。あまりにもいい神社だったんで、そこでちょっとしたお札と神棚みたいなものを買ったんですが、新しいメンバーが増えてからも毎朝それを拝むことが続いています。宗教的な意味は全然ないんですけど。なんか音とかが合うと気持ちいいですよね。そんなもんじゃないかなって思いますね。

オフィス内の様子。左手奥、ちゃぶ台の上方に神棚がある。
身体性を重要視されているんですね。
大槻
![]()
言葉でなにか言っても、それって頭で理解しているから感覚が共有できているわけじゃない。音とか呼吸とか、そういうもので合っていくっていうのが一番かなと。それこそ、ちゃぶ台を囲んでみんなでご飯を一緒に食べたりとか。
書籍の企画から著者さんとのやり取りはどのように?
大槻
![]()
いまはほとんど僕がやってるんで、本によってほかのメンバー数名に一緒に組んでもらって手伝ってもらいます。そうやって少しずつ覚えてもらってますね。『自由が丘の贈り物』という本は、メンバーが主体的に動いてくれました。今後は、僕がメインで動くっていうことを減らして任せていきたいと思っています。
250人超のサポーターに向けてつくる「みんなのミシマガジン」
最後に、ミシマ社の今後の構想を教えていただけますか。
大槻
![]()
いま一番がんばっているのは、「みんなのミシマガジン」ですね。これは京都のオフィスに移って良かったことのひとつなんですが、京都っていう場所でメディアを運営していきたくて。ずっとウェブマガジンをやっていましたが、今年4月に「みんなのミシマガジン」に名前を変えてリニューアル創刊しました。
頭に「みんなの」と付けた理由は?
大槻
![]()
運営していくにあたって、スポンサー企業をいっさい募らない自主独立が出版社としてのあり方だっていう僕の考えがあって。でも、全部持ち出しで運営するのは難しいタイミングに来ていて、サポーターの方々にお金をいただいて、皆さんとの共同運営という形をとろうと思ったんです。

サポーターに毎月「贈り物」として「紙版」をプレゼント。
たしか年間20,000円くらいのサポーター費でしたよね。
大槻
![]()
毎日更新していくウェブ雑誌で、1ヶ月の終わりの30日、31日に編集後記を書くんです。その1ヶ月かけて完成するウェブ雑誌を「紙版」にまとめて、毎月サポーターの方にプレゼントしています。普通、8月には9月号が出ますが、ミシマガジンは8月中旬に7月号が届きます。毎月ぜんぜん違うデザインで、紙質も毎回違う。もちろん非売品ですし、サポーターの人にいかに驚いて、喜んでもらうかを考えてつくっています。
これは作るのが楽しそうだ(笑)
大槻
![]()
表紙が2つに切られているような面白いデザインもあるんですが、それをつくってくださる印刷屋さんもサポーターです。無料で印刷なんて自分でもありえないと思いながら提案しに行ったところ、そういうのを待ってたんですっておっしゃってくださって。
ほかの出版社さんの参考にもなりそうな取り組みですね。
大槻
![]()
うちでは読者ターゲットという言葉は使いません。老若男女、面白いものはみんなにとって面白いはずだという方針なので、マーケティング的なことを一切やらない。人って、まさに磯辺の生き物で。でもマーケティングは、全員が回遊魚だっていう設定のもとでないと成り立たない。30代出版社勤務の男性だからこれ好きでしょって送られてくるもののほとんどが、まったく興味のないものばかり。
たしかに年齢や性別などで一緒くたにされることには違和感があるかもしれませんね。
大槻
![]()
こういう風に自分がひとくくりにされること自体が不快なことで、世界の大多数の人がそう感じていると思っています。そういう方ひとりひとりに向き合っていきたいですね。ミシマガジンのサポーターには0歳から91歳までいて、その方々のリアクションがダイレクトに届いています。
ミシマ社が作り出す「面白いもの」に共感してくれたひとたちが集まってくれたんですね。
大槻

まず三島社長がいちばん楽しんで「みんなのミシマガジン」を作られている様子が伝わってきた
![]()
サポーター、ひとりひとりに向き合っていきたいと思っています。ウェブでもそれはできますが、紙版をつくることで、それが媒介となって世界に開かれていくのはかなり面白い。ミシマガジンは、一冊一冊にサポーターナンバーが印字されている、その人のためだけにつくられたものなんです。
えっ、それはすごい。今サポーターの方は何名ほどいらっしゃるんですか?
大槻
![]()
いま250人超のサポーターがいますけども、この方々だけに向けてつくっているから、何千、何万っていう数字の商業出版とはまったく違うつくり方ができる。これは自分にとっても、すごい発見でした。これを贈与経済って呼んでますけど、お金を介さない経済と商業出版の2つ、これを両方やることによって幅が広がっています。これからは、それが影響し合った本づくりをしていきたいと思っています。
これからもミシマ社のご活躍を期待しております。今日はありがとうございました。
大槻
※ミシマガサポーターにご応募希望の方はこちらまで!
SNSシェア
撮影・イラスト
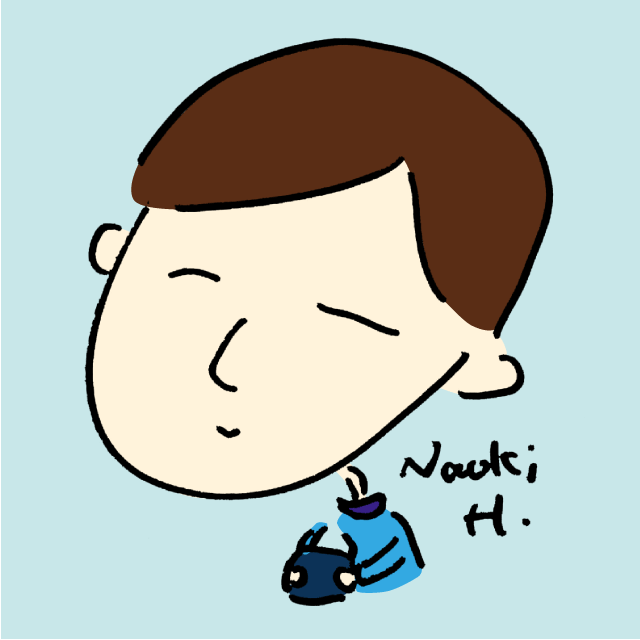
編集