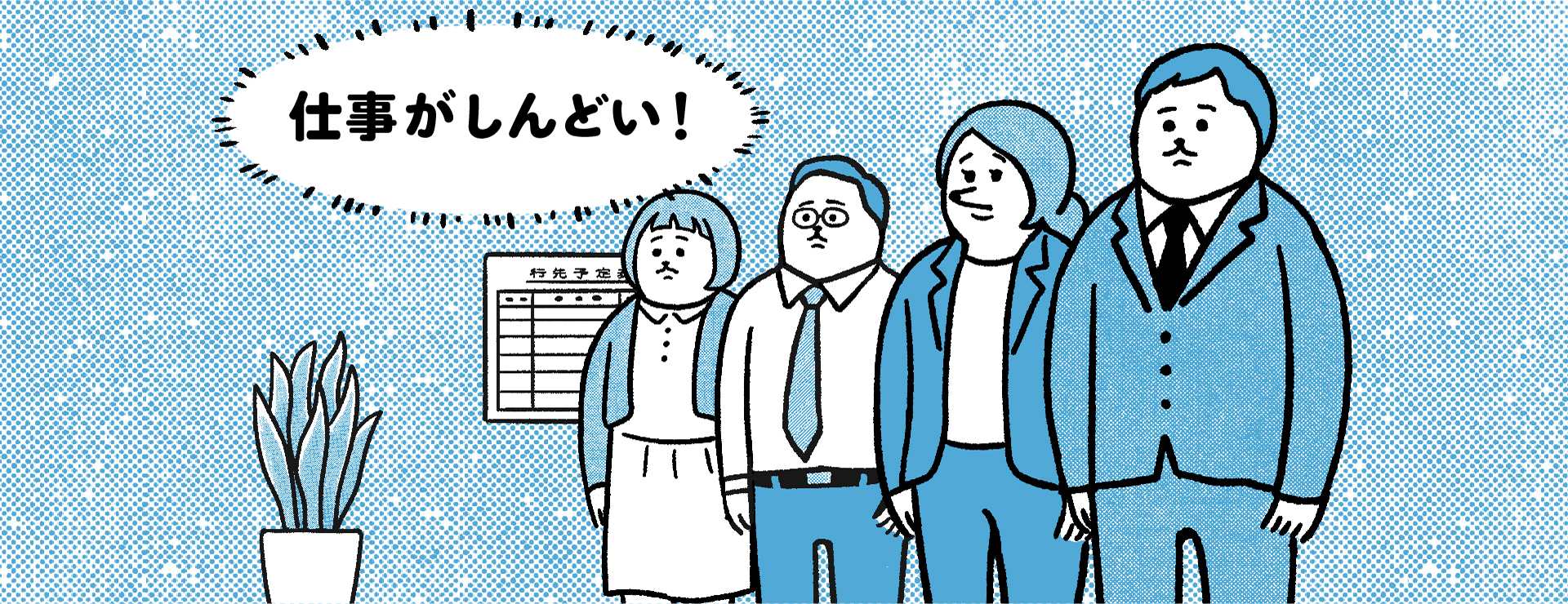仕事の「しんどい」を変えるのは、一人ひとりの「越境」とチームの「景色合わせ」だった

「仕事がしんどい」──誰しもが、こういった経験を一度はしたことがあるのではないでしょうか。
人間関係や過度な仕事のようなしんどさもありますが、「変わらない組織」や「決まらないジレンマ」、「望まないワークスタイル」によって感じるしんどさもあります。
そこで、組織開発や人材開発がご専門の沢渡あまねさんに、ワークスタイルからくる「仕事のしんどさ」と、個人として、チームとして「仕事がしんどい」にどう関わっていけばいいかについて聞きました。
決まらないジレンマ



沢渡 あまね(さわたり・あまね)。作家。組織開発とワークスタイル改革の専門家。日産自動車(株)、(株)NTTデータ、大手製薬会社などを経て、現在はあまねキャリア株式会社 代表取締役CEO。『人事経験ゼロの働き方改革パートナー』をうたい、ITやコミュニケーションの観点から組織改革を進める。著書に『職場の問題地図』『新時代を生き抜く越境思考』(技術評論社)、『チームの生産性をあげる。』(ダイヤモンド社)などがある

規模が大きいだけに、物事が前に進まない。また、日本と海外との綱引きや覇権争いもあって、「決まらないジレンマ」が大きかったんです。
その前に勤めていた企業では、それなりに権限も与えてもらい、チームを引っ張って仕事をしていました。でも、最後の会社に転職して給与は上がったし、ポジションも上がったけれど、自分で自分のハンドルを握れなかった。


当時、30代後半でした。いわゆる働き盛りです。世の中を見回すと、まわりはバリバリ仕事を前に進めているように見えました。そこで思ったんです。「自分は、このままでいいのかな?」と。働き方の多様性もなかったですし。
しばらくして、「気持ち的に、もう無理だな」と思いました。
就職は「人生の墓場」――新卒のときの気持ち




先ほどお話したように、グローバル企業の綱引きゲームと、大企業の支配的な働き方に限界を感じて、「もう、大企業のサラリーマンはいいや」と思って2014年にフリーランスになりました。
でも、よく考えてみると、わたしが人材開発や組織開発に携わるようになったのは、最後の会社にいたときの無力感だけではなく、自分の原体験として、新卒のときから「日本の組織文化に対する違和感」を抱いていたんです。


大学を卒業して、本当は航空業界に行きたかったんです。ところが、社会人になった1998年は就職氷河期で、航空会社の門戸が開かれていませんでした。
その時点で、仕事に対してあまりやる気がなくて、「みんな会社に入るから、仕方なく就職するか」みたいな感じでしぶしぶ就職しました。「もう、自由がなくなるんだ」と思うと、就職は「人生の墓場」だと思っていたんです。
損をしている「日本人の働き方」

当時わたしが配属されていた日本の職場は、サービス残業や休日出勤が当たり前でした。若手が上司より早く帰れないとか、上司に付き合って、遅くまで丁稚奉公しなければいけないとか。


気がつけば、日本から出張しているわたしが一番最後まで仕事してるんですよ。スーツとネクタイで(笑)
金曜日にもなると、同僚は夕方から中庭でバーベキューをやってるんです。手招きして「こっち来いよ」って。串の鶏肉を食べ、沈んでいく夕日を眺めながら思ったんです。「あぁ、日本人って損しているな」って。



その時に、「Because, We are japanese.」としか答えられなかったんですよ。あのときの悲しさと言ったらなくて。
帰りの飛行機で成田空港に近づけば近づくほど、どんどんブルーになっていく。そして、思うんです。「あぁ、またあの日々に戻るのか」って。
そんな原体験があったこともあって、フリーランスになったとき、日本の働き方を変えていきたい。大企業病を脱していく発信がしたいと思うようになったんです。
「しんどさ」にどう向き合うか?


1つ目が「とにかくやれることから行動してみること」。 2つ目が「やっている人を応援すること」。
まず、「とにかくやれることから行動してみる」ですが、たとえば、今回のCOVID19で広がったテレワーク。いままでは「できない」と思っていた人が多かったと思うんです。
けれど、やってみたら、意外と「できるよね。やれるよね」になった。つまり、テレワークができるか否かの差って、「体験したか、していないかの差だけ」なんですよ。


だから、 できることからまず行動してみる。


それならば、周りでやってる人に「それ、いいね」って声をあげてみるとか、話を聞いてみるとか。つまり、行動している人を応援する、ファンになるっていうのもいいと思います。
「この人はこういう考え方なのか」「この人はこういう興味関心があるのか」「実はわたしも、そういう働き方に興味があるな」
そんな、半径5m以内から共感の輪が広がっていく。そこから組織内の、小さな世論、社内世論が生まれることってあるんですね。
自分の「境」を越える



しんどさを自分ひとりで抱えていたり、自分の組織の中だけで抱え込んでいたら、新しいやり方、新しい発想、新しいチャンスって入ってこない。気づくことも、気づかせることもできないですよね。
そこで、社内だけではなく社外に目を向けていく。外の知識を取り入れる。情報のシャワーを浴びる、ないし浴びさせる……組織を変えるためには、こういう行動って大事なのかなと思ってます。
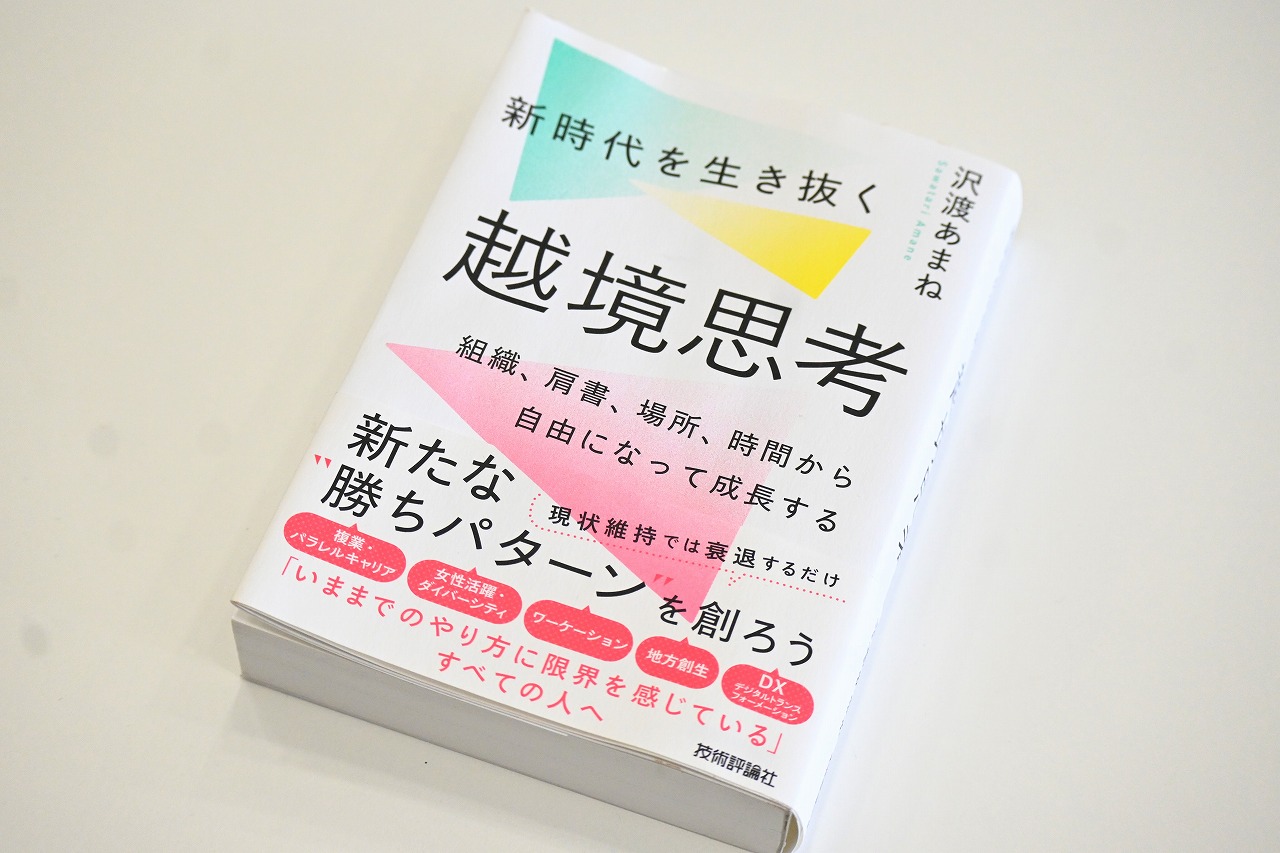
沢渡さんの書籍『新時代を生き抜く越境思考』(技術評論社)。組織・会社をはじめ、わたしたちのまわりにはさまざまな「境」がある。越境することによって価値観が揺らぎ、新しいやり方、新しい発想、新しいチャンスが生まれる

本ってその人の気持ちとか、体を表すじゃないですか? 「この人はこういうことを考えているんだ」「こういう考え方ってあるんだ」って、周りに知ってもらう効果ってあるんですね。


自分の関心があることを知ってもらい、広めることによって、自分の問題、課題に共感する人を増やして行くんです。
チームの「景色」を合わせる


一人ひとりの意識っていろいろあるから、なかなか噛み合わなかったりするじゃないですか。
ところが、相手に対して「こういうことを考えているんだ」「こういう考え方をする人なんだ」のように、相手を理解する、景色を合わせることならできると思うんですよね。
一方がテレワークで、一方がオフィスワークだったり、一方が対面のほうが好きで、一方がチャットベースのほうが好きだったりしても、お互いが理解をし合えば景色が合いやすくなります。


「しんどさ」とチームの「心理的安全性」

そんなとき、「しんどい」をみんなで分散できたらいいな、と。そのあたり、組織論からみてどうですか?




「あ、この人には弱音はいっちゃいけないんだ」……そうすると抱え込んじゃいますよね。そして、あるとき爆発します。これって敵がいる状態なんですよね。


心理的安全性は、馴れ合ったり、仲良しクラブを作るためにあるのではありません。個々のパフォーマンスを発揮する、いい仕事をするためにあります。
そのためには、お互いの強みや弱み、考えていること、仕事に対する価値観も含めて、お互いの理解が必要ですよね。
「敵がいない環境」をつくる3つの屋台骨




たとえば、話をする場が対面しかなければ、意見を言いづらい人や、口下手な人は本音を伝えられません。でも、中には「文字のほうが伝えやすい」という人もいます。
グループウェアやチャットのような、対面以外の場があると、伝え方の選択肢が増えますよね。


ある会社で、リーダーが変わったら、職場の空気がガラッと変わった事例があるんです。そのリーダーは何をしてたかというと、「1叱り3褒め」を徹底してたんですね。 1つ叱るときは、その代わりに3つ褒めるっていう。
日ごろから「それいいね」と褒めたり、「そういう考え方があるのか。確かにね」って共感したり、賞賛を示す行動をする。それでも、厳しい指摘をするときはする。これによって関係性がガラリと変わったんですよ。




たとえば、若手から上司に「この仕事ははじめてなので、こういうところをサポートしてほしい。自分なりには、ここを頑張ろうと思います」のように伝える。これって、相手の期待役割と自分の期待役割を伝え合う行為ですよね。


「この人にはこういうことを期待できるのかな?」「こういうことが得意なのかな?」「コミュニケーションが心地いいのかな?」みたいな。
このように、期待役割を伝え合うことで、立場や環境が違っても、同じ釜の飯を食っていなくても、合意形成しやすい。
そこから、仕事のゴール到達に向けた、心理的安全性が高い、話しやすい、受け止めやすい関係構築ができていくのかなと思います。
SNSシェア
執筆

竹内 義晴
サイボウズ式編集部員。マーケティング本部 ブランディング部/ソーシャルデザインラボ所属。新潟でNPO法人しごとのみらいを経営しながらサイボウズで複業しています。
撮影・イラスト

高橋団
2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。