インターン大学生の疑問
その場にいる人が間違いを受け入れてしまえば、それは「間違い」じゃなくなる──菅原直樹×小国士朗

多様性のある組織には、さまざまな価値観を持つ人が集まります。ときにはわかりあえず、相手にイライラしてしまうこともあるかもしれません。そんなとき、どのようにして違いとつきあっていけばいいのでしょうか?
今回登場していただく菅原直樹さんと小国士朗さんは、ともに「異なる価値観」を持つ人たちと向き合う活動を続けています。
菅原さんは、演劇と介護を結びつけた劇団「OiBokkeShi」を主宰しており、小国さんは、"注文をとるスタッフが全員認知症"というコンセプトを持つ「注文をまちがえる料理店」を企画しています。
違いを楽しみ、新たな価値を生み出す2人の対談をお届けします。
ごく当たり前の、むしろ豊かだと思えるような暮らしを送っている方々がいた

「注文をまちがえる料理店」のコンセプトは本当にユニークですよね。


"注文をとるスタッフが全員認知症"というコンセプトを持つ「注文をまちがえる料理店」。(撮影:森嶋夕貴 D-CORD)




小国士朗(おぐに・しろう)さん。日本放送協会(NHK)制作局 開発推進 ディレクター。2003年に入局し、情報系ドキュメンタリー番組を中心に制作。2013年に社外研修制度を利用して大手広告代理店で勤務した後、NHKのスマホアプリやSNS向けサービスなどの企画・開発に携わる。個人的プロジェクトとして、認知症の人がホールスタッフを務める「注文をまちがえる料理店」などを手がけている。


菅原直樹(すがわら・なおき)さん。俳優、介護福祉士。四国学院大学非常勤講師。大学時代に演劇の道を志し、卒業後はフリーの俳優として小劇場で活動。新進劇作家・演出家の作品に多数出演し、平田オリザが主宰する青年団に俳優として所属。同時にホームヘルパー2級を取得し、2010年からは特別養護老人ホームの介護職員として勤務する。2012年に岡山へ移住し、介護と演劇の相性の良さに着目して「老いと演劇」OiBokkeShiを立ち上げる。

でも実際に施設を訪れてみると、ごく当たり前の、むしろ豊かだと思えるような暮らしを送っている方々がいて。


入居している認知症の方々は700メートルほど離れた市場へ買い物に行き、自分たちで食事を作る。僕も取材の合間にごちそうしていただきました。
その場にいる人が受け入れてしまえば、それは「間違い」じゃなくなる




でも、ふと気づいたんです。僕がそれを言うと、ここにある"普通の暮らし"がぶち壊しになってしまうんじゃないかと。



そこでは僕だけが浮いていたんですよ。そして、そんな自分に違和感を持ち始めるようになりました。


それで「注文をまちがえる料理店」というコンセプトが浮かんだんです。たかがハンバーグと餃子かもしれないけど、僕にとってはとても大きな体験でした。
祖母のボケを正すべきなのか、それとも受け入れるべきなのか







そうすると祖母が「しょうがない子だね、あの人にあげようと思ったのに」と言うんですよ。






ボケを正そうと思えば「おばあちゃん、タンスの中に人はいないよ」とたしなめる。
逆にボケを受け入れようと思えば「ごめんね、他のものを冷蔵庫から探すよ」と声をかける。




介護のプロは、受け入れるんです。



役割や肩書きに縛られているから、イライラしてしまうのかもしれない

「しっかりしたおばあちゃんでいてほしい」と思えば思うほど、イライラしてしまう。

と。

んです。


特に息子や娘は、しっかりしていた頃の親の姿を知っているから、当たり前のことができなくなった姿を見て許せなくなってしまう。


たとえば「時計屋の◯◯さん」と突然話しかけられても、時計職人を柔軟に演じることで合わせるわけです。


認知症の親は役割から解放されて自由になっているけど、子どもはずっと「息子」や「娘」という役割のままで。


これは父親も息子も役割に縛られて、自由に動けない状態なんですよね。
でも息子が友だちを連れてくると、ちょっと状況が変わります。息子はいつもより優しく父親に接したり、父親のほうもいつもとは違う関わり方になったり、役割が変化するんです。


「『認知症の◯◯さんだ』と見るのではなく、『◯◯さんが認知症なんだ』と見るべき」と。


たとえば「サイボウズ社長の青野さん」ではなく、「青野さんがサイボウズの社長をしているだけ」と考えるのが、本来あるべき姿なのかなと。



おそらく、役割から解放されたことで純粋に日々を楽しめているんだと思うんです。認知症にはそんな側面もある。

ちょっとした非日常の、自分が楽になれる場所があってもいいような気がします。

演劇で批判されれば「俺は介護福祉士だし」と考え、介護の仕事でうまくいかなくても「俺は役者だし」と考えるという(笑)。


組織には「決めるべきルール」と「ゆるさ」が必要


組織や会社でも、考え方の違う人が集まれば同じようになるでしょう。

「注文をまちがえる料理店」のプロジェクトでも、違う考え方や能力を持つ人を、ものすごく意識して集めるようにしました。
そこから生み出される化学反応がすごくて、ずっとワクワクしていました。

そんな中で、少しずつすりあわせをしていくという。面倒だけど、その分楽しい。


OiBokkeShi『よみちにひはくれない』と『カメラマンの変態』美作公演の舞台写真。(撮影:hi foo farm)1枚目右側、2枚目中央に写っている人物がOiBokkeShiの看板役者、岡田忠雄さん。岡田さんは、菅原さんが作った「老いと演劇のワークショップ」の参加者だった。菅原さんは、そこで岡田さんと一緒に演劇をつくってみたいと思い、現在まで共に活動している。




私も「適当でいいや、とにかくやってみよう」と開き直って準備を進めて。



するとおもしろいことに、遊んでいた子たちも普段とは違う空気を感じて舞台に上がろうとするんです。


一生懸命みんなで作品を仕上げることも大切だけど、ゆるく、みんなでハプニングを受け入れるような舞台も素敵だな、と思うようになりました。



「◯◯さん、3番テーブルのお客さまを担当してください」と言って、後は認知症の方に任せる。お客さまとのコミュニケーションがあり、ときには「まちがい」もあるという。


想定外のことが起きないと、仕事って、どこか塗り絵を完成させるような作業になってしまうじゃないですか。

「遊び」って、完璧にやる必要がないじゃないですか。できてもできなくてもいい

そういえば、介護現場には遊びをリハビリに活用する方法論があります。


むしろ、できないから人間味があっておもしろいわけで。これがリハビリに生かされるんです。




「なぜ自分はできないんだ」と嘆いてばかりいるよりは、「老いとはこういうものだ」と楽に構えていたい。
注文をまちがえる料理店に行く意味は、そうした遊びの価値観を学べることにもあるんじゃないでしょうか。



でもその場所に常に笑いがあれば、なんとなく許せる雰囲気が出てくる。注文をまちがえる料理店でも、自然に笑いが起きるんです。


そんなフラットなコミュニケーションが大事なんだと実感します。

日頃の役割から解放されれば、互いの新たな一面が見えてくるかもしれないですし。



執筆・多田慎介/撮影・橋本美花/企画編集・木村和博
サイボウズ式特別編集「多様性は大切だけど、わかりあう必要ってあるの?」
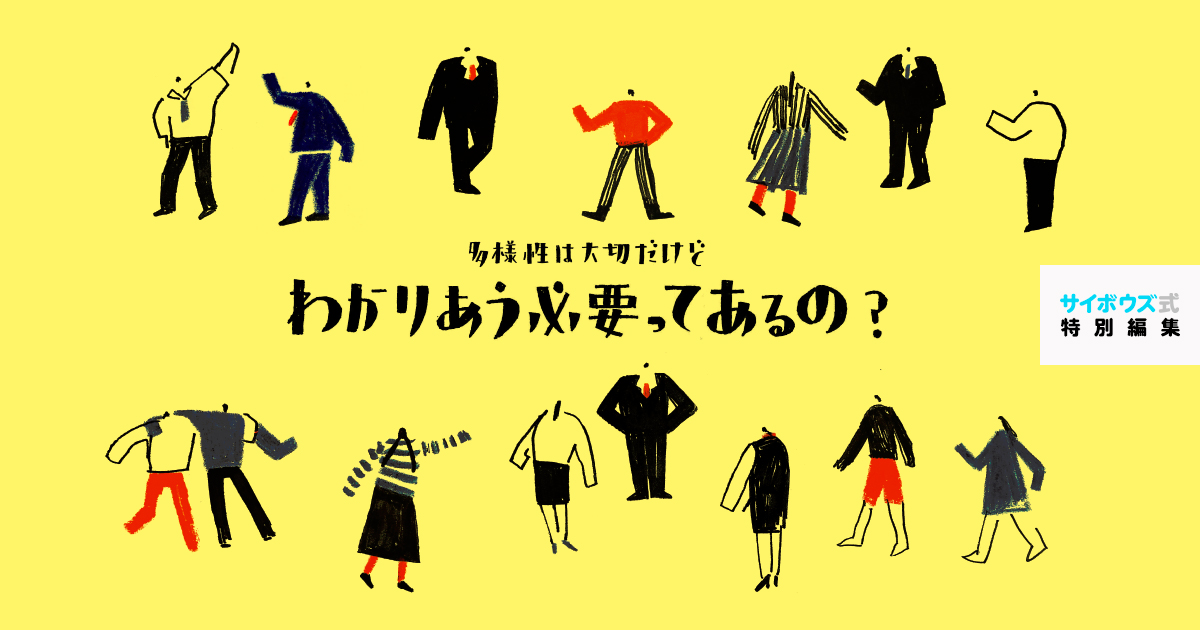
SNSシェア
執筆

多田 慎介
1983年、石川県金沢市生まれ。求人広告代理店、編集プロダクションを経て2015年よりフリーランス。個人の働き方やキャリア形成、教育、企業の採用コンテンツなど、いろいろなテーマで執筆中。
撮影・イラスト

橋本 美花
主に人物写真を撮らせていただいているカメラマンです。お仕事以外では海外へ行ってスナップ写真を撮ることが大好きです。自転車に乗りながら歌うことも好きです。





