評価から離れてただ共にいる時間をつくる。光明寺・松本紹圭さんに聞く、おそれに強いチームの生み出し方
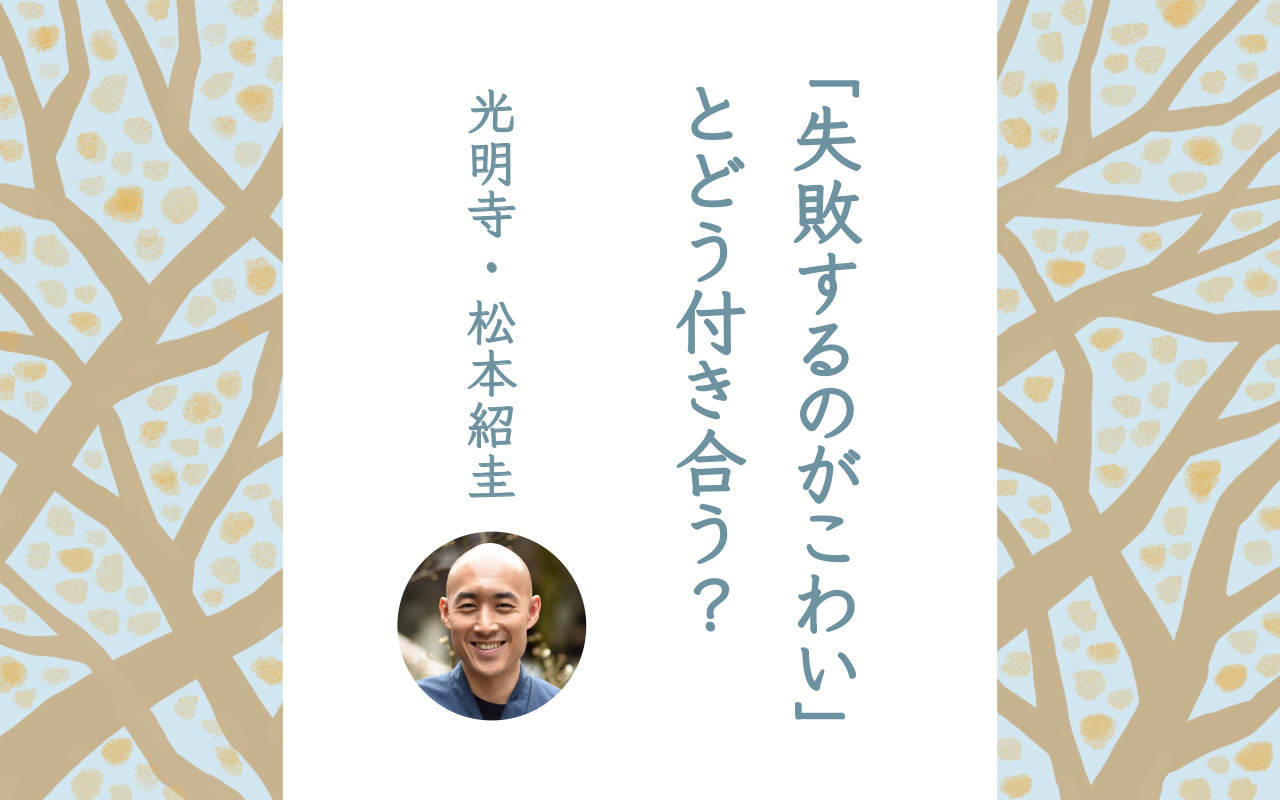
「失敗してもいいから、やってみて」
先行きの見えなさがつのる、今のビジネス環境。日本でもこの数年、“イノベーション”や“チャレンジ”を意識し、具体的な取り組みを進める企業がかなり増えたように感じます。
とはいえ、誰だって「失敗するのはこわい」。まして仕事にかかわることとなると、自分のキャリアへの影響を考えてしまい、新しい挑戦に踏み出しきれない人も多いでしょう。
そうした「おそれ」を克服するヒントが、長く人の心と向き合い続けてきた仏教にあるのではないか。光明寺(東京神谷町)の僧侶である松本紹圭さんにお話を伺いました。

松本紹圭(まつもと・しょうけい)さん。1979年北海道生まれ。現代仏教僧(Contemporary Buddhist)。世界経済フォーラム(ダボス会議)Young Global Leader、Global Future Council Member。武蔵野大学客員准教授。東京大学文学部哲学科卒。2010年、ロータリー財団国際親善奨学生としてインド商科大学院(ISB)でMBA取得。2012年、住職向けのお寺経営塾「未来の住職塾」を開講し、8年間で700名以上の宗派や地域を超えた僧侶の卒業生を輩出。著書多数、『お坊さんが教えるこころが整う掃除の本』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)は世界15ヶ国語以上で翻訳出版。「松本紹圭の方丈庵」noteマガジン発行。「Temple Morning Radio」ポッドキャストは平日毎朝6時に配信中
「他者からどう見られるか」の視点がおそれを生む?



たとえば、私には4人の子どもがいます。彼らを育てるなかで感じるのが、幼い頃は色んなことにためらいなくチャレンジしていたのに、成長していくなかで失敗をおそれる回数が増えているってことなんです。
どうしてだろうと。

その変化にはおそらく、「自我」の確立が大きく関係しているのではないでしょうか。


自我が確立すると、“自分”と“他者”をわけてとらえられるようになります。言い換えると「人からどう見られるか」という視点が獲得されるんです。
そうすると、自らが思い描くイメージと、他者から見られている姿との“ズレ”が気になってきます。


実際に他者になって自分を見ることって、『君の名は』のようなことが起きない限りはできませんよね(笑)。
おそれについて考えるときに、“ひとり相撲”になっていないかは見直すといいと思います。
やりたいことや夢、目標は呪いにもなり得る





たとえば就職活動だと、そこで求められる人材や価値を把握して、必要なスキルを磨き、アピールすることで内定を得ていきますよね。


やりたいことや夢を、今は達成していないものととらえると、「自分には足りないものがある」感覚が生み出されます。それは、ある種の“呪い”にもなり得ると思うんです。


でもそれらが実現できなくても失敗ではないと思うんです。


たとえば、佐々木さんが5年後に「こうなってたらいい」という理想を描いたとします。実際に5年後の自分が、以前と同じ理想を描いていると思いますか?


つまり、今掲げている理想は、現時点で自分が決めたものに過ぎないわけです。


やりたいことや夢、目標をモチベーションのひとつにすることはあっていい。それらを実現しようとする行為自体にやりがいを感じることもあるはずです。
ただ、必ず実現しなければいけないと考えるとおそれを生む場合があります。とらわれ過ぎないようにすることが大切です。
自分の外に共有することで不安の肥大化をさける


自分の中だけで考えていると、過去の失敗パターンをあてはめて、どんどん不安を肥大化させて「モンスター」を生み出してしまいます。

自分が当たり前だと思っていても、他者にとってはそうじゃないことがたくさんある。だからこそモンスターをチームに共有して、個人の認識をとらえなおしていけると考えています。
今年のテーマは「モンスターへの挑戦状」。ここでのモンスターとは、実在するものではなく、私たちが頭の中で作り出している思い込みを指します。会場ではみなさんのモンスターを募集中です。 pic.twitter.com/xbItbxRyZF
— 青野慶久/aono@cybozu (@aono) December 5, 2019




他部署の人とお互いの仕事について情報交換してみたり、社外の人が現在のチームに出入りしたりすることで関係性が変わる場合もあるのかなと。

自分の状態を安定させるには、常に動き続けた方がいいんです。自分自身を外に開いて移り変わっていく。その揺らぎが既存の関係のなかでも変化を生んでいきます。
仕事の成果や評価から離れて“ただ共にある”環境をつくる


リーダーが自分の不安や苦手をさらけ出すことで、メンバーも「誰しも完璧じゃないんだ」と思えるようになるのではないでしょうか。
その結果「わたしも不安を共有してみようかな」と連鎖が生まれてくるはずです。


その人が抱えている不安やおそれと付き合っていくには、まず本人が気づいて自分自身で行動を起こしていくしかありません。
決して誰かが代わってあげることはできない。そのためにも、まずは自ら言葉にしてもらうしかないんですね。
それがしやすい環境を作り、話をしてくれたら、ただ聞く。それが大切だと思います。


掃除は、そこに上下のヒエラルキーが発生しづらく、人とも比較しにくいからです。出せる価値とか、アウトプットをさほど気にしなくて済むんですよ。




こう考えると、リアルオフィスは「ただ一緒にいるための口実」が意識せずとも作りやすい環境だったのかもしれませんね。


すると生産性の物差しから離れるのが難しくなって、おそれが生まれやすい状況になっているのかもしれません。


SNSシェア
執筆

佐々木 将史
保育・幼児教育の出版社に10年勤め、’17に滋賀へ移住。保育・福祉をベースに、さまざまな領域での情報発信、広報、経営者の専属編集業、インタビューギフトサービスの運営などを行う。保育士で4児(双子×双子)の父。
撮影・イラスト

あさののい
千葉県出身、2012年から岡山県に移住。書籍やチラシ、webなどさまざまな媒体でマンガやイラストを描いている。岡山県奈義町での生活を綴ったマンガ「こんにちは、なぎさん」をwebにて更新中。
編集





