「仕事がしんどい」は変えられる。心のメカニズムと、チームで乗り越えるヒントを聞いてみた

仕事がつらい。プレッシャーに押し負けそう。「つらかったら言ってね」と言われるけれど、なかなか言い出せずに、しんどさを抱えたまま過ごしてしまう。これって、どうすれば解消するのでしょうか。
そのヒントを探るべく、「#サイボウズ式Meetup vol.17」では、心療内科医の鈴木裕介(Dr.ゆうすけ)さんと、株式会社NOKIOO取締役の小田木朝子さんをゲストに迎え、「仕事のしんどさ」をテーマとしたトークセッションを開催。
サイボウズ式編集部の竹内義晴がモデレーターとなり、しんどいと感じる心のメカニズムから、それを解決するためのチームコミュニケーションについて、語り合いました。
「しんどい」と感じるのはなぜ?


心のメカニズムとしては、たとえば「しんどい」と感じたときに、身体がどうなっているかを考えてみるとわかりやすいかもしれません。
感情の前段階として、情動と呼ばれる身体的な感覚があります。胸がキリキリしたり、喉が締まるような感じがしたり、そわそわしたりする。そういう身体の感覚をキャッチして、脳が「これは不安なのではないか、しんどいのではないか」と感情をラベリングしていくんです。

鈴木裕介(すずき・ゆうすけ)。心療内科医。秋葉原内科saveクリニック院長。ライフワークとしてメンタルヘルスに取り組み、「Dr.ゆうすけ」として、講演やSNSなどでの情報発信を行なっている。


たとえば同じニュースを見ても、つらいと思う人もいれば、気にならない人もいる。それはその人がそれまでの人生でどのような傷つきをしてきたのか、という点で違ってきます。



しんどさの自覚を難しくする“ブレーキ”

実際、しんどいと感じたことのない人なんていないと思うんですけどね。それに、しんどさはその人の経験にもよるものだから、自分の身体に聞いてみないとわからない。そもそも比べるものではないんです。

だからこそ、他人から客観的に「それってしんどいよね」と定義してもらうだけで、グッとラクになるときもある。

小田木朝子(おだぎ・ともこ)。株式会社NOKIOO取締役。企業の人材育成・組織開発支援を担うHR事業を立ち上げ、ヘルプシーキングを含む多数の人材育成カリキュラムの開発・講師および講師育成を手掛ける。2022年4月に『仕事は自分ひとりでやらない』を出版。



たとえば、わたしは「迷惑をかけたくない」という気持ちがとても大きくて。「迷惑をかけてはいけない」という思い込みが、助けを求めることを躊躇してしまう原因になっています。
あと「すみません、できません」という言葉。自分の脳内で「すみません、わたし仕事自体ができません」という意味に変換されてしまって、言えなくなる。
「頑張るからこそ成長する」という価値観に囚われてしまうのも、ブレーキの1つですね。


だから、自分にどういうブレーキが働きやすいかと知っているだけでも、しんどさの自覚のしやすさや周囲への頼りやすさがだいぶ変わりそうです。
「自己開示の強要」に要注意

とすると、チームでの関わり方を変えていく、あるいは、「しんどさ」の前提から変えていく必要があるのかもしれません。

竹内義晴(たけうち・よしはる)。1971年、新潟県妙高市生まれ・在住。ビジネスマーケティング本部コーポレートブランディング部 兼 チームワーク総研に所属し、新潟でNPO法人しごとのみらい代表でもある。本セッションではモデレーターを担当。

だから、弱音を吐くことのコストに対して、自覚的にならないといけないと思います。
誰かを頼るというのは、過去に頼ってよかったという経験がある人じゃないと難しい。そういう成功体験がない人が、頼るというリスクをおかせないのは、当たり前のことです。


その人が抱えている内容が深刻であればあるほど、それを誰かに打ち明けることは「清水の舞台から飛び降りるほどの勇気が必要なこと」なんですよね。
組織としての雰囲気が「自己開示ヤクザ」のようになっていないか、気にする必要があります。自己開示が難しい環境では、「大丈夫です」というビジネス自己開示にとどまってしまう。


でも残念ながら、「心理的安全性が大事なんだ!」と迫ってきて、「いや、その態度が心理的安全性じゃなくしているんです!」という状況も時々見受けられます。

「頼る」というリスクを払った以上のリターンが得られる経験の積み重ねが必要なんです。まずは、そうしたリスクを払ってくれたこと自体が承認されるカルチャーを育てていくことが望ましいと思います。
「助けて」を言えるスキル、ヘルプシーキング


ポイントは、頼ることを「スキル」として身につけること。助けを求めることがチームに必要とされ、それが成果に結びつく行動なのだ、という価値観を日々広めています。
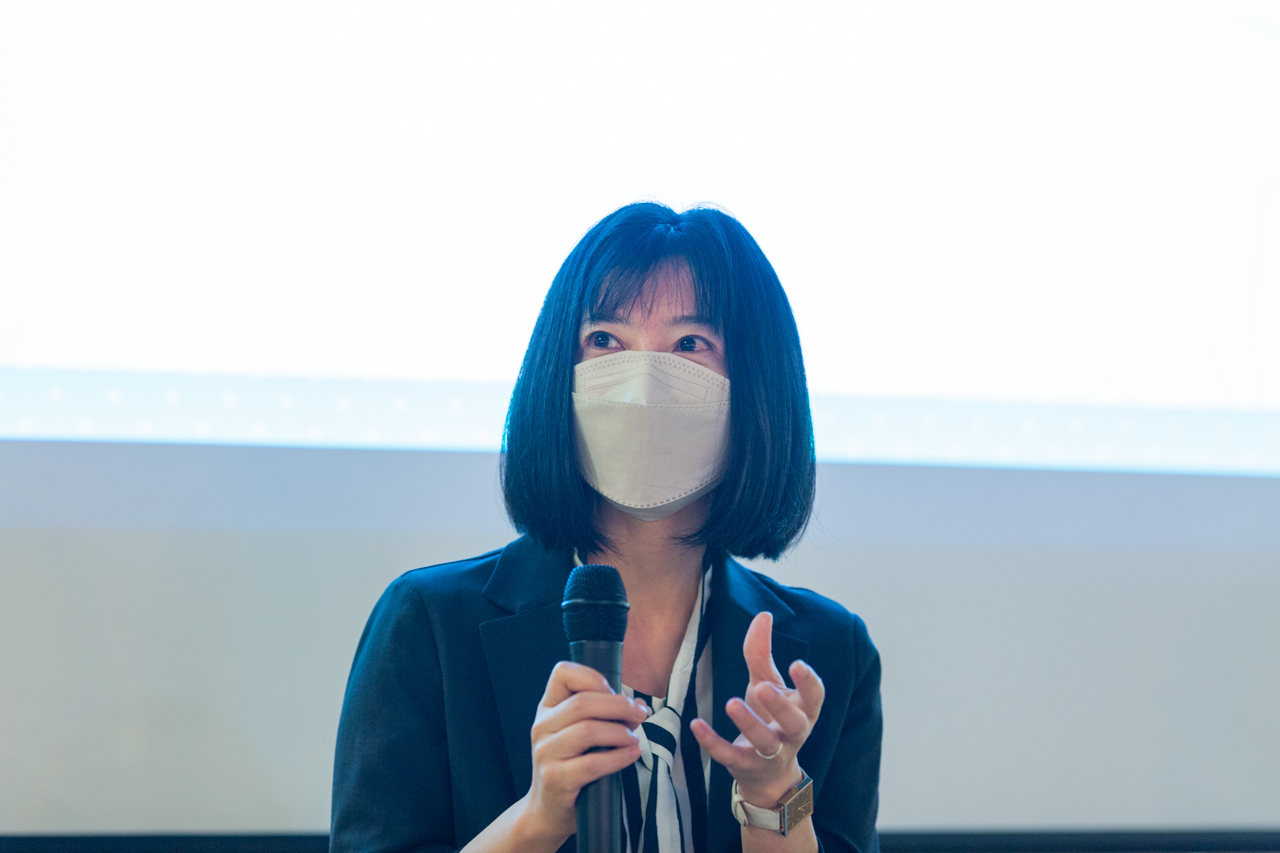


一般的には、困った人が助けを求めて、困っていない人が助ける、という前提がありますよね。そして、この考え方の延長線上には、若手は助けを求める立場で、リーダーはそれを受け止めて助ける側という、固定された関係性があります。


つまり、一人でなんでもできちゃう人が承認されるのではなく、助け合える人が承認されるチームを目指していくんです。


まずは「いまの仕事のやり方だとしんどくない?」といった現状のリスクに共感してくれる人を、チームの中で集めることから始めてみるといいでしょう。

「しんどさを共有する」ことを前向きにとらえる

助け合う関係性を求められるなかで、変われないリーダーを責めるのは、ヘルプシーキングの考え方に当てはまりません。
リーダーが正しい情報や知識を得て、頑張り方の価値観を変えるための支援を組織全体で行っていくことが求められます。

それでも、最終的には自分たちのためになるんだと、組織全体でスキルを育てていけることが大切だと思います。
「しんどさを一人で抱え込む」ことって、現状を変えない点において実はラクなんです。でも、頼ることが誰かのためになると考えて、現状を変えていく。
頼ることがスキルとして伸ばす価値のあることなんだ、という共通認識を組織全体で持てるといいのかもしれません。

「頼る」は人生の奥行きに直結する


背中を預けられる喜びや頼もしさを感じられることが、僕にとっての「組織で働く」の真骨頂だと思っています。それはスキルであると同時に、人生に直結する奥行きのあるものだとも考えられます。



明日からできる「しんどい」の伝え方





「困っていることを共有したら、その行動が肯定された」という体験がチームに広がると、「自分も開示していこう」という雰囲気が醸成されていきます。その先に、しんどさが言い合える関係性や場が実現するのかなと思うんです。




そう考えられたら、明日からでも「困りごと」を共有するという、最初の1歩が踏み出せそうですね。
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集





