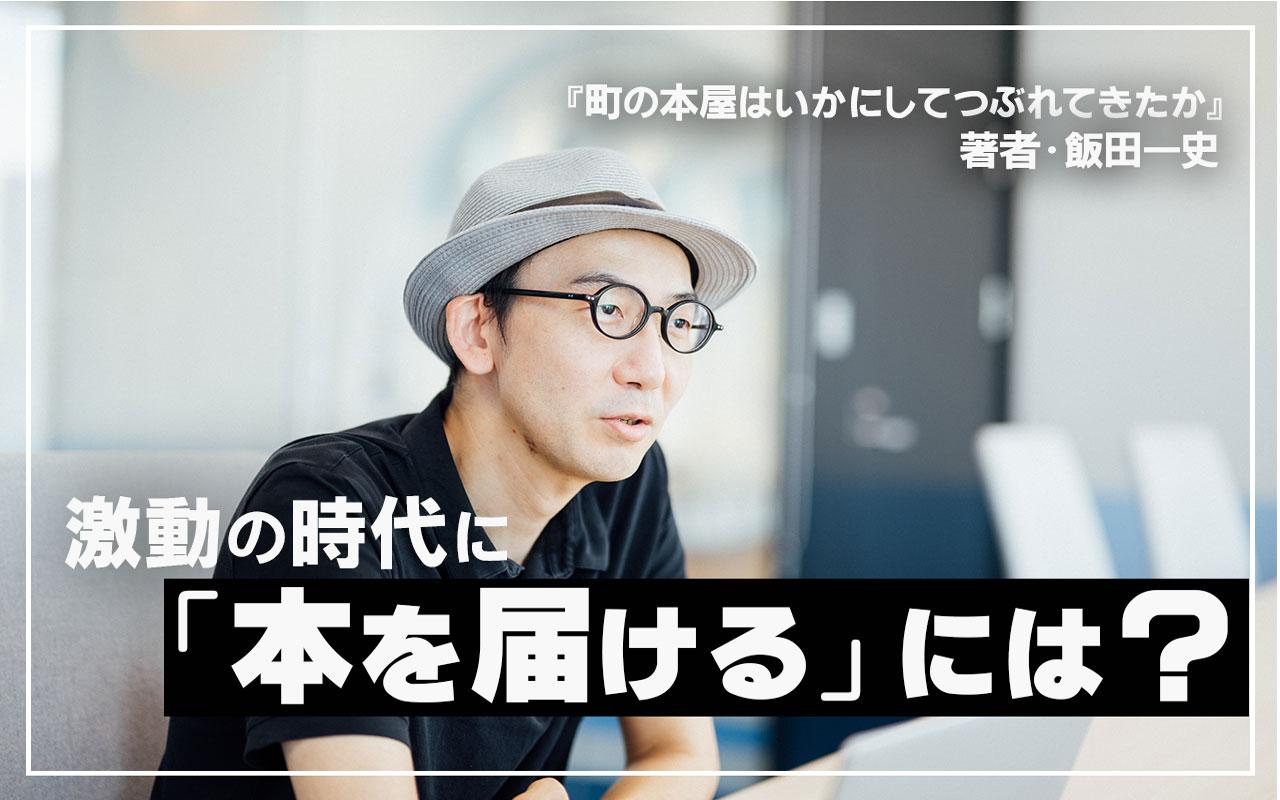本とはたらく
「半身で働く」「本を読み、他者の文脈に触れる」──朱野帰子・三宅香帆の仕事観

9月7日、東京・下北沢のBONUS TRACKにて散歩社とサイボウズ式ブックスが合同で開催した「BOOK LOVER'S HOLIDAY ーはたらくの現在地ー」。はたらく価値観が多様化する今の社会において、本を通してあらためて自分の仕事について見つめ直す機会をつくりたいという思いで開催した本イベント。
イベントの中では、これからの「はたらく」を考えるための3本のトークをご用意しました。
その中のひとつが、2019年にTVドラマ化もされた人気小説『わたし、定時で帰ります。』の作者である朱野帰子さんと、新書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』がヒット中の三宅香帆さんとの対談です。
会社員、兼業作家、自営業としての作家──。これまでさまざまな立場で働かれてきたおふたりに、仕事観について対談していただきました。
本がヒットしたあとの仕事事情


朱野帰子(あけの・かえるこ)。1979年東京都生まれ。8年の会社員生活を経て、2009年に第4回ダ・ヴィンチ文学賞大賞を受賞してデビュー。『わたし、定時で帰ります。』シリーズはドラマ化もされて話題に。他の著書に『海に降る』、『科学オタがマイナスイオンの部署に異動しました』、『対岸の家事』など。『急な売れに備える作家のためのサバイバル読本』、『キーボードなんて何でもいいと思ってた』など作家の労働に関する技術同人誌も刊行している。




三宅香帆(みやけ・かほ)。文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年高知県生まれ。京都大学人間・環境学研究科博士前期課程修了。小説や古典文学やエンタメなどの幅広い分野で、批評や解説を手がける。著書『人生を狂わす名著50』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』等多数。

『急な「売れ」に備える作家のためのサバイバル読本』は、その時の体験を同人誌にまとめた本なんです。私が滑って転んでしまった分、あとに続く人たちには、同じところだけは転ばないようにしてもらいたいなという思いがあったので。お役に立てたならよかったです。


朱野さん、なぜそんなに働くことが好きなんですか?



お会いすればするほど、朱野さんはどう考えても、定時で帰りたい主人公の真逆の方なんです(笑)。
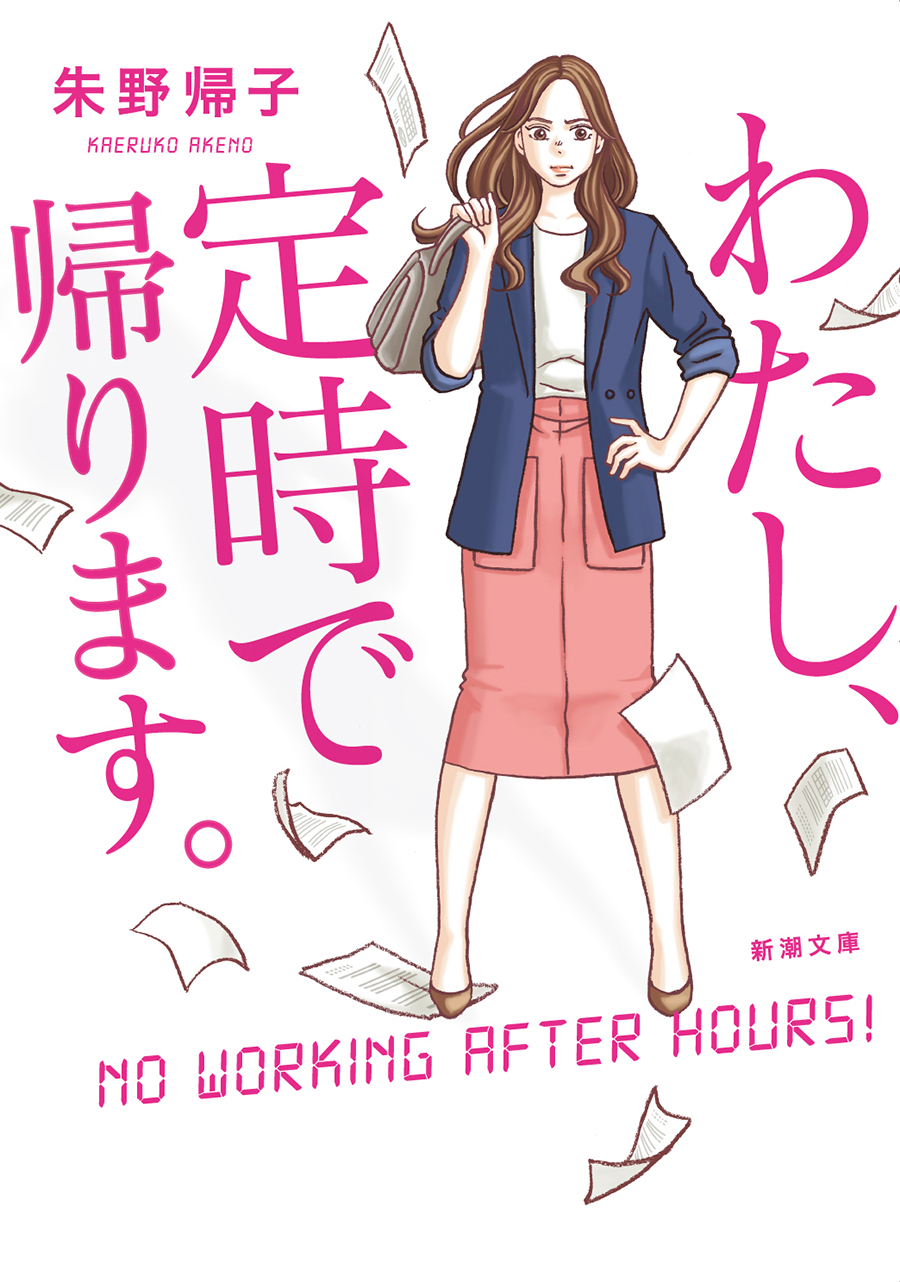



私の祖母も、70歳過ぎまで家族全員に止められても働いていましたし、父も、定年退職してから会社を作るなんて言い出して。多分、動いてないと苦しい一族なんだと思います。

※晃太郎:『わたし、定時で帰ります。』の中に登場する、仕事大好きなキャラクター。ワーカホリックで、日曜にも出勤して仕事をするくらい仕事が好き。


でも、40代を過ぎてから突然それが通じなくなってきました。今まで100の力でできたことが80になり、60になり……。どんどん力が減っていくことを考えたときに、エネルギーがもともと少ない人たちのことや、自分のこれからのことも考えるようになったんです。
たくさん働きたい気持ちと、とは言え無理じゃないか?という気持ちの両方を抱くようになって書いたのが、『わたし、定時で帰ります。』です。


「半身で働く」とは、仕事を半分に減らすわけではない



三宅さんご自身は、現段階のライフヒストリーを振り返ったときに、「全身で働くこと」と「半身で働くこと」についてどのように切り替えてこられたのでしょうか。

「8時間でやっていた100の仕事を、4時間で50の仕事をしよう」という意味ではなくて、極端なことを言えば、「4時間で100の仕事をできるように頑張って、あとの4時間は他のことに使おう」というイメージです。



「全身」は、「仕事は人生において最優先されるべきである」という前提をもって、たくさんの仕事を、たくさんの時間を使ってこなすイメージです。だけどそれがスタンダードの社会では、やっぱりほとんどの人は疲れてきてしまう。そうではなく、もっと仕事以外の場の優先順位も上げられるように、みんなで時間の使い方を考えていきましょうと。
たとえば私自身の経験で「全身」で働いていたなと思うのが、新卒1年目の時です。フルタイムで残業もある会社員として働いて、かつ1年に本を3冊出していたんですよ。そうすると本当に寝れなくて、睡眠時間を削って仕事していた。じゃあその時って仕事の効率が良かったのか? と聞かれると、微妙だったんです。疲れてぼーっとしていた時間も結構あった。
フリーランスになってからのほうが、遊びの予定を入れたり、寝る時間を確保したりできるので、時間をコントロールしながら働けています。リフレッシュできるからその分仕事に精も出て、結果的に効率もいい。だからフリーランスになった今、やっと「半身」になることができたなという感じです。
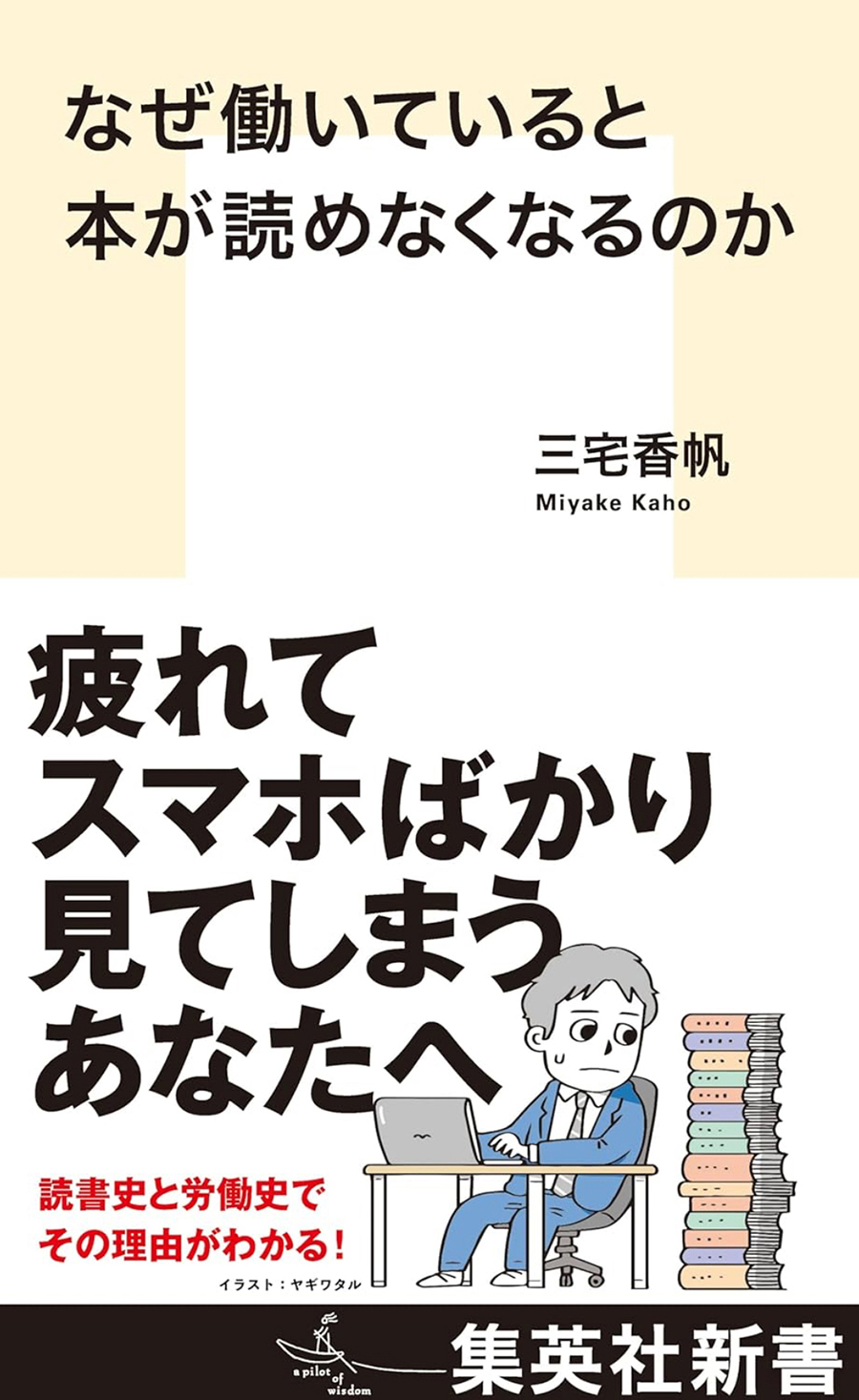
半身社会は、リーダーが作っていかなければいけない



個人が努力する必要はもちろんあると思いつつ、いち会社員だと変えられる部分と変えられない部分は確かにあるので、仕組みを作っている人が気づいてくれないと半身社会は実現しません。
現状の会社でそれが難しいのは重々承知ですが、今後労働人口も減るなかで、必要ない仕事を減らしたり、会議の優先順位をつけたりする必要があるのではと。


30代後半で、働き方への「マインドチェンジ」が起きた









影響力が増えていくと、やはり「自分だけ」では生きていけなくなる。でも、自分自身の意識ってそう自然と変わるものではないんですよね。毎朝鏡に向かって「もう若者ではない!」と自分に言い聞かせ、「次の世代のことを考えよう」と頑張ってマインドを変えていきました。


周囲からの見られ方も立場も変わってくる30代後半の方々に対しては、できるだけいろんな本を読み、他者の文脈に触れてほしいと思います。
昔は、自分と近い趣味や、近いキャリア、近い価値観を持つ人たちの本ばかり読んでいたんです。でも、まったく違う生き方の人たちがいるということを頭に入れておく。それだけで、仕事に対する意識が変わっていくと思います。


SNSシェア
執筆

あかしゆか
1992年生まれ、京都出身、東京在住。 大学時代に本屋で働いた経験から、文章に関わる仕事がしたいと編集者を目指すように。2015年サイボウズへ新卒で入社。製品プロモーション、サイボウズ式編集部での経験を経て、2020年フリーランスへ。現在は、ウェブや紙など媒体を問わず、編集者・ライターとして活動をしている。
撮影・イラスト

藤原慶
1993年 神奈川県生まれ。2年間のバックパッカー経験を経てフォトグラファーになることを決意。最終的にたどり着いた名古屋でアシスタント勤務を経て上京。