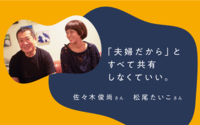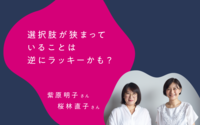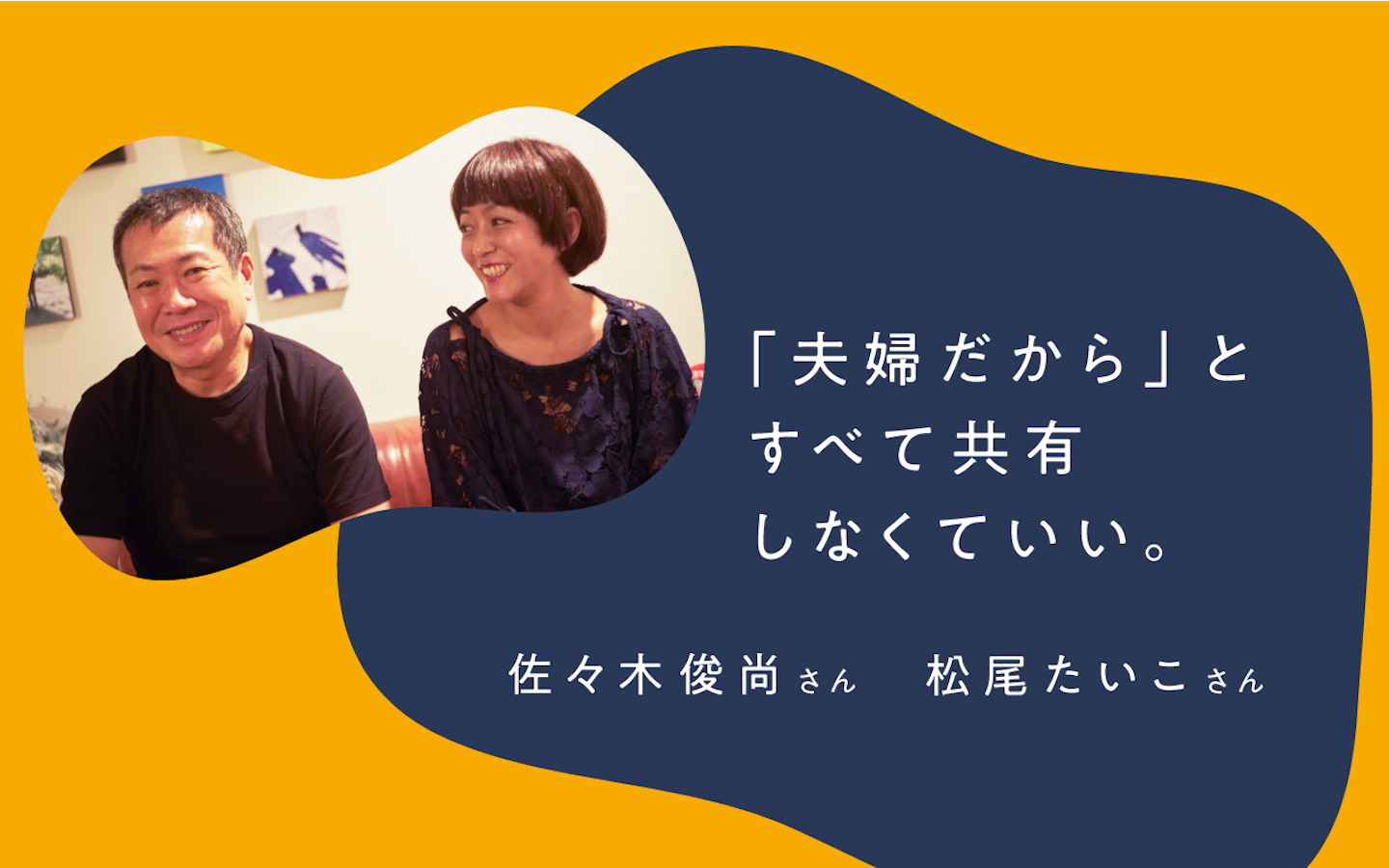これからの家族と、仕事のカタチ。
シェアハウスで共同子育て。一番の良さは、「親以外の手が増えること」ではないんです──東京フルハウス

フルタイムで働き、日中は子どもを預けているけれど、急なお迎えが必要になった時に対応が難しい。自分が風邪を引くなどして誰かを頼りたくても、実家が遠くて両親には頼れない──。共働き「核家族」での子育てに限界を感じている人は少なくないのではないでしょうか。筆者もまさに、その一人です。
そんな中、夫婦でシェアハウスに住み、血縁にかかわらず家族を拡張して「共同子育て」をしている場所があると聞きました。
その場所とは、西新宿にあるシェアハウス「東京フルハウス」。3階建ての1軒家に、現在は、家族を含む男女11人が暮らしています。住人は、1歳から35歳まで、大学生に秘書、広報、ゲームクリエイター、編集者など、年齢も肩書もさまざま。
ある休日の朝、東京フルハウスを訪ね、1歳の息子さんの子育てをする栗山和基さん・茂原奈央美さんご夫妻と、一緒に暮らす阿部珠恵さんにお話を伺いました。
シェアハウスの家事分担と同じように、子育てもシェアできたらいいんじゃないか

その頃からずっと、結婚しても子どもが生まれてもシェアハウスで暮らしたい、という話をしていました。

子どもが生まれる前までは遅くまでバリバリ働いていた先輩も、産後復帰してからは16時に切り上げて帰っているのを近くで見てきて、「働きながらちゃんと子育てをできるのだろうか」と不安に感じていました。
おたがいに子育てをするようになったら、保育園の送り迎えを分担することもできるから、残業もできるかもしれないね、と。

その時に、この人と結婚するかもしれない、と思いました(笑)。

(写真左)栗山和基(くりやま・かずき)さん。シェアハウス「東京フルハウス」発起人。大学時代、神田川のほとりで友人らとシェアハウスを始めて以来、就職、結婚、子育てと、そのフェーズに合わせたシェアハウスを企画・運営している。ゲーム会社で企画開発の仕事をしながら、週末は実家の絵画教室で子ども達に絵の指導も行う。2018年からは新宿と三浦半島でのニ拠点シェア居住を始めた。
(写真右)茂原奈央美(もはら・なおみ)さん。2017年10月に出産し、シェアハウス「東京フルハウス」で子育て中。大学生向けのキャリア支援・就職活動支援会社に勤務。著書に『現役大学生による学問以外のススメ』『シェアハウス-わたしたちが他人と住む理由』『結婚してもシェアハウス!〜普通の婚活はもうやめた〜』がある。
そうして2年半くらい経った頃、いい物件が見つかったので友だちに声をかけて規模を大きくしました。それが今の東京フルハウスです。
そのなかに夫婦がいるので、子どもが生まれることは、自然なことだと思っています。

阿部珠恵(あべ・たまえ)さん。2010年からシェアハウスを始め、2012年にシェアハウスのリアルな毎日や動向、将来への展望などをまとめた書籍『シェアハウス わたしたちが他人と住む理由』を出版。2016年からは、幻冬舎plusで『結婚してもシェアハウス〜普通の婚活はもうやめた〜』を連載し、電子書籍として出版。メディアや講演などを通じて、新しい家族やコミュニティの在り方について発信を続ける。
「親以外の手があることではなく、子どもの成長を一緒に喜んでくれる人が増えること」がうれしい
でも、シェアハウスだと夫婦だけでは“少しはみ出る部分”を補ってもらえるので、すごく助かります。たとえば、トイレへ行く時に見てくれたり、危ないことをしようとする時に止めてくれたり。


取材中、筆者の子もすっかり住人の方の腕のなかに
はじめの半年間が大変なんだということも含めて、子どもを産む前に子育てを知ることができてよかったです。もちろん計り知れない部分はあるけれど。


近所に住むJJさん。
日中、買い物にもついていって、抱っこ紐をつけてバスに乗ったら、生まれてはじめて席を譲ってもらって、感激しました。この世界は善意にあふれている! と。

でも、そんな日も、住人が仕事から帰ってくると、大人の会話ができるので気分転換になります。何より、子どもの小さな変化に気づいてくれるのが嬉しくて。「まつげ伸びたね」とか「腕の筋肉がついてきたね」とか。

離れて暮らす自分の両親やきょうだいは会えても1ヶ月に1回くらいなので、大きな変化にしか気づかない。でも、毎日会っている住人は、小さな変化に気づく。保育園の連絡帳を見て喜んでくれます。それが、嬉しいんですよ。
たくさんの"常識”があるから、僕たちは喧嘩をしたことがない


僕らは、犯人探しはしないで、住人の共有LINEで注意をします。

10人いれば10通りの常識があることがわかるから、押し付け合うんじゃなくて、「じゃあ、僕らはどうする?」という議論に発展します。



でも、シェアハウスは、いつでも出入り自由。留まるのも出ていくのも本人が決められます。
仕事で落ち込んだ日も、シェアハウスに帰ってくると前を向ける

でも、仕事で嫌なことがあったり、疲れたりして、飲みたい! と思った時に、ここで飲めるのはいいですよ。誰かに声をかけてわざわざ外へ行かなくてもいい。

そのやり方を見つけるためには、まず違いを受け入れて、解決策を柔軟に考えていく力が必要です。
異なる価値観や考え方を柔軟に受け入れているからこそ、人が集まってくるし、円滑に生活ができる。誰も排除をしないコミュニケーションスキルがすごく高いんです。
シェアハウスは、結婚しても子どもを生んでも、個人が自由であるための選択肢の一つ

そのために、いろんな人と出会ってさまざまな価値観に触れてほしいと思っています。今のところ、いろんな大人が出入りするこのシェアハウスは最適だと思っていますね。

その意味で、親子が依存し合うのではなく、周りに頼れる人たちがいるシェアハウスの今の環境はいいなと思っています。

どちらかが仕事を辞める時が来るかもしれないから、どちらか一方の収入には頼らない。共働きなので、彼も2ヶ月育休をとって、ふたりで保活をしました。
今はこのかたちがいいと思っているからそうしているけれど、私自身、将来的には別の暮らし方を選ぶかもしれません。状況に合わせて、常識にとらわれすぎずに模索し続けたいと思います。
 文:徳瑠里香/撮影:三浦咲恵/編集:柳下桃子・明石悠佳
文:徳瑠里香/撮影:三浦咲恵/編集:柳下桃子・明石悠佳
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

三浦 咲恵
1988年大分県生まれ、サンフランシスコ市立大学写真学科卒。帰国後都内のスタジオを経て、鳥巣祐有子氏に師事、2016年独立。雑誌や広告、Webなどで活躍。
編集

柳下 桃子
サイボウズ式編集部のインターン大学生。 大学卒業後、さらに学士入学をしたため、すこし長めの学生生活を送る。学生中に家庭を持ち、多様性や家族についての関心を広げる。