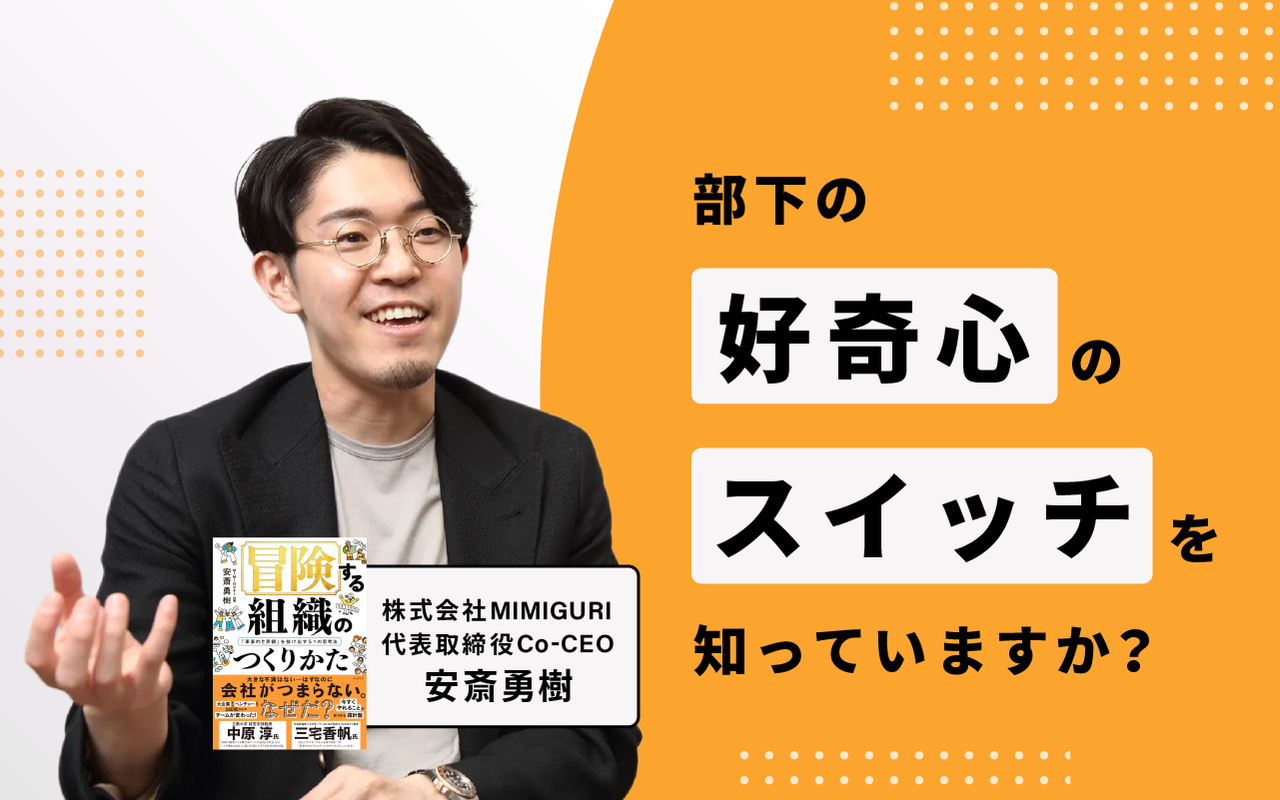「情報は共有しないほうがリスク」の徹底が、米軍を強い組織に変えた──「見守りつつ手は出さない」元司令官の覚悟

歴史上の偉大なリーダーと聞いて、軍の司令官を思い浮かべる人は少なくないのではないでしょうか。
映画や小説では、戦場の英雄たちがすべての情報を掌握し、決断する姿が数多く描かれてきました。経験と実績を兼ね備えたリーダーがすべてを一任し、彼らの判断のもと、組織や軍隊は効率的に規律正しく運営されていました。
「それはインターネットが登場する前の話だ」と話すのは、スタンリー・マクリスタル元米軍司令官です。
現代の脅威はいつにも増して複雑で、戦争で勝つために必要な情報を1人のリーダーが効率的に管理することは非現実的だとすら言えます。
マクリスタル元米軍司令官とサイボウズの代表取締役社長 青野慶久による対談。前編前編に続き、後編では、透明性と情報共有の必要性によって再定義されるリーダーシップについて語ります。
組織では、情報を共有しないほうがリスク

軍隊で、誤って情報が漏えいした場合、打撃は相当大きいはずです。

ところが、扱う情報の大半は、私たちが思うほど極秘にする必要がなかったのです。状況が刻一刻と変わっていくため、ある情報が今日は極秘だったとしても、2日後に公になったところで、支障はありませんでした。

スタンリー・マクリスタル。元米軍司令官であり、国際治安支援部隊の一員。統合特殊作戦コマンドの元司令官。軍の司令官を引退後、2011年にアドバイザリーサービス、経営コンサルティング、およびリーダーシップ開発会社であるMcChrystal Groupを設立。また、イェール大学ジャクソン・インスティテュート・フォー・グローバル・アフェアーズの上級研究員としてリーダーシップに関する授業を開講。著書に『TEAM OF TEAMS 複雑化する世界で戦うための新原則』(日経BP社)など

組織内部から情報共有に抵抗が出始めたとき、彼らにまずこう伝えました。


例えば、私たちのエージェントの名前が公になったときの打撃は計り知れないため、その点は念を押して教育しました。「極秘の環境下で、情報共有を頻繁にしつつ動いてほしい」という彼らへの期待値も明確にしました。


各組織がそれぞれパズルの1ピースを抱えている限り、全体像は見えてきません。お互いのピースを共有することで、より良い成果が生まれることを伝えました。
これらの手順を踏んだ結果、私たちのオペレーションの効率は急激に上がりました。
そして、内部競争を減らすために、個人や小規模のチームではなく、かかわった全員の貢献を認めるようにしたんです。




彼らに対して、情報を共有するリスクより、共有しないリスクのほうが上回るという点をしっかり伝える必要がありました。


すべての情報が機密扱いされていたのに、結局どの情報にも機密性はなかった

青野慶久(あおの・よしひさ)。1971年生まれ。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立した。2005年4月には代表取締役社長に就任(現任)。社内のワークスタイル変革を行い、2011年からは、事業のクラウド化を推進。著書に、『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない』(PHP研究所)など




アルカイダのメンバーは当然、その中身を把握しており、情報が私たちの手に渡っていることも知っています。口外しないことで、一体何を守ろうというのでしょうか?
これが数年前なら、情報が外に出ることは決してなかったでしょう。組織の文化が変わったからこそ、入手した情報を有効に活用できたのです。


なぜなら、厳しく制限された一部のグループだけに情報がとどめられ、漏れた場合は、極めて厳しい処罰が待っていることを全員が理解していたからです。
真の機密情報だけに注意を払うことで、関係者全員がその情報を敏感に扱うことができたのです。

しかし、統合特殊作戦コマンドの場合、隠すものと共有するものを積極的に決めることで、機密情報の保持をより厳格にできるようになったんですね。

以前は、情報を隠そうとするのがデフォルトの文化でした。どんな情報共有もトラブルにつながる可能性があると考えられていたのです。
一方、私たちは「その情報を必要としている人に共有しないとトラブルになる。ただし、一部の機密情報だけは、共有する前に特別な許可を得てほしい」ということを明確にしました。
すべての情報が機密扱いされていたころは、結局どの情報にも機密性はありませんでした。ですから、絶対に漏れてはいけない情報を明らかにする必要があったのです。
リーダーの役割は、環境を見守りつつも手を出さないこと


その上、承認する立場にありながら、私は現場ほど多くの情報を把握していませんでした。私による承認は、意思決定のプロセスに何も貢献していなかったのです。


この新たな役割では、何1つ見落としてはいけないため、過去のどんな役割よりもエネルギーと注意力を使いましたね。

オンラインでの対談。写真右は、サイボウズ式編集部のアレックス。

今、リーダーに求められているのは、環境を作り、そこに一定のルールを設け、組織文化を定義することです。
そして、社内コミュニケーションのスピードを上げ、迅速に動けるように人に権限を与え、彼らから学ぶことなのです。


リーダーの存在はこれまでと同じく重要ですが、リーダーシップの種類が変わりつつあるんです。
「すべての情報を把握できている」は幻想。米軍でマイクロマネジメントは有害無益だった

では、人員のリソースも豊富な軍隊の中で、マイクロマネジメント(過干渉)しないリーダーシップをどう実現しましたか?


一度、彼らを戦場に送り込むと、物理的にコントロールすることは不可能だったためです。


フルモーションの動画をリアルタイムで見られるだけでなく、部隊のすべての無線通信の内容が耳に入ってきました。
そのため、リーダーは「すべてを把握している自分が指揮を執るべきだ」という欲求にかられました。


1万フィートからの動画とライブの無線通信をもってしても、起きていることを現場の人間のように完全には把握できません。
私たちは指揮を執るのではなく、ITで得た情報をもとに戦場への理解を深めました。今、戦闘がどのように進められているかを理解できたため、援軍や火力支援、医療避難を効率的に準備できたんです。


もし、リーダーがマイクロマネジメントをしていたなら、それは組織にとって有害無益だったでしょう。

「透明性が効果的な経営につながる」と理解している企業は、より進化できる


軍隊を退いてから、私は経営コンサルティング会社を起ち上げ、多くの組織を見てきました。情報共有がオープンな組織もあれば、苦戦している組織もあります。その概念を理解するのと、実践するのとは別物だからです。




私は軍隊に人生を捧げてきました。自ら意思決定をして指揮を執りたいからこそ、人は司令官を目指します。
でも実際には、意思決定をする頻度は徐々に減り、私の仕事は大きく変わっていきました。


私は2つのことから満足感を得ます。1つは勝利することです。
もう1つは、私が指示を出さずとも部隊が自ら判断して前進していく姿でした。彼らの能力の高さにはたびたび驚かされ、部隊の勝利はこの上ない誇りでした。
過去のように指揮を執らない私を批判する人もいるでしょう。でも、誰が何と言おうと、肝心なのは、私はすばらしいチームを率いていたということです。
私があれこれ言わないことで彼らが向上するなら、それで一向に構わないんですよ。

SNSシェア
執筆
撮影・イラスト

高橋団
2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。
編集

三橋ゆか里
IT関連の話題をビジネス誌や女性誌などで執筆。BBC(英国放送協会)などで日本文化について発信し、2018年にイギリスで本を出版。海外の子育てネタを扱うポッドキャスト「HearMama」を配信中。ロサンゼルス在住。