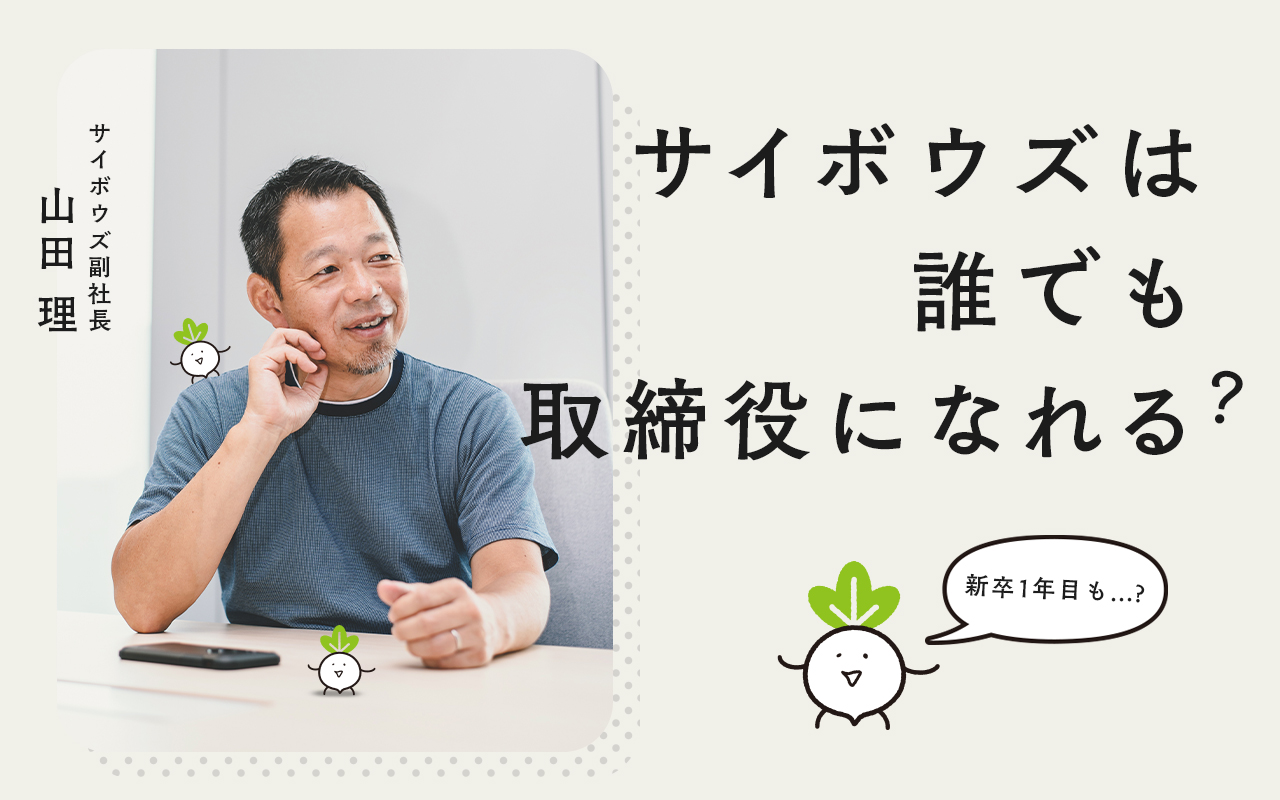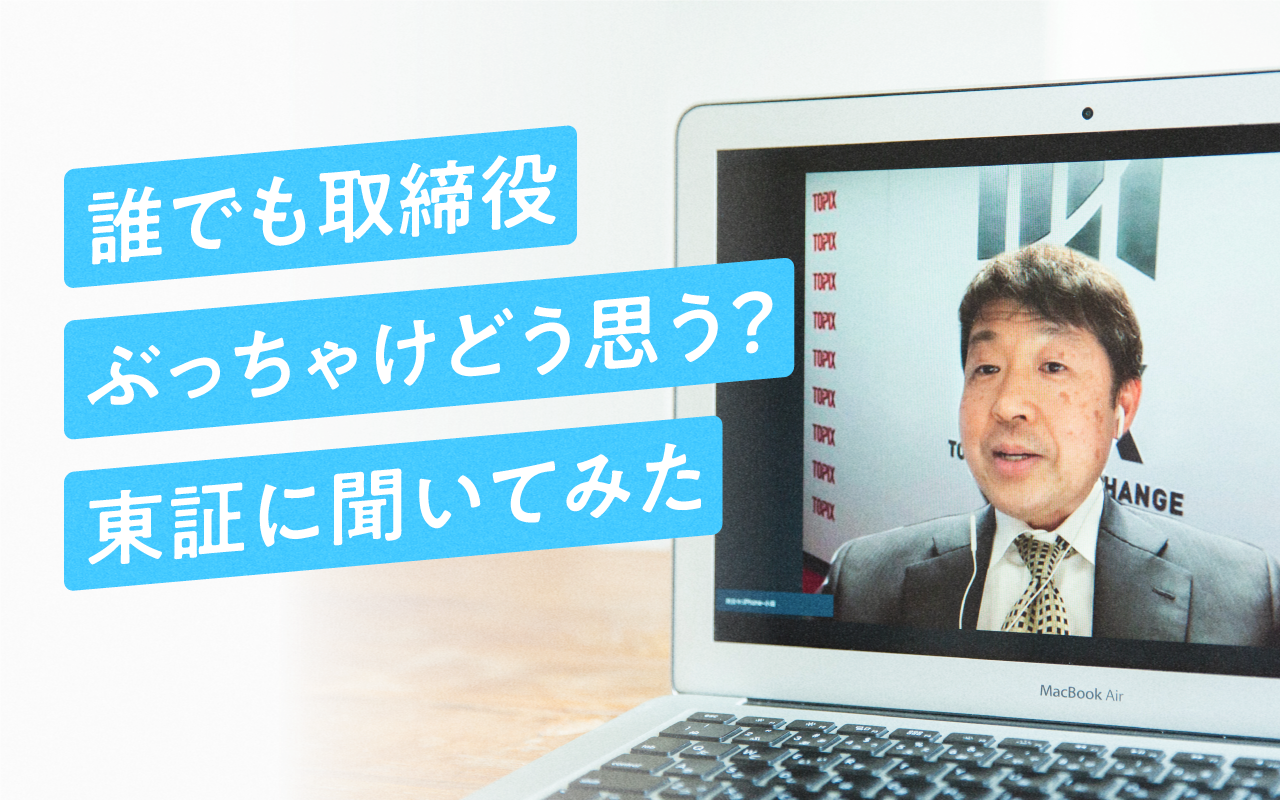サイボウズ ESG情報開示報告書 2021──せっかくなので、青野社長のインタビュー記事でつくってみた
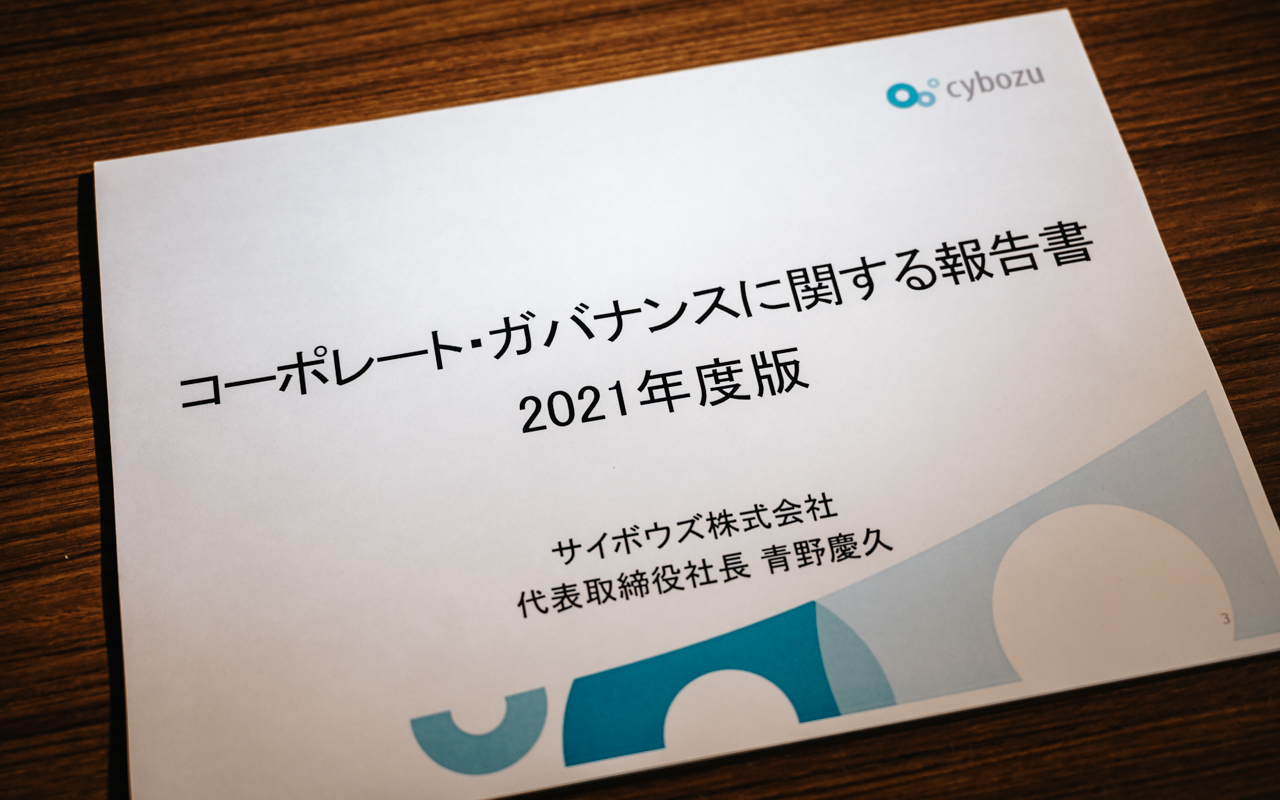
「12月30日までに、ガバナンス報告書を提出せよ」
東京証券取引所(以下、東証)は、2022年4月より市場区分を再編。それに先駆けて2021年6月に、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)が改訂されました。現在、各企業は12月30日までに、改訂に沿ったガバナンス報告書の提出が求められています。
でも、報告書ってどうしても形式的になりがち。どうせ作成するなら、どの会社も同じような内容の作文ではなく、経営者自身の言葉を伝えるべき。
そう考えたサイボウズのIRチームは、代表取締役社長の青野慶久へのインタビューを行い、公開した記事を報告書として東証へ提出することにしました。
本記事では、改訂のポイントである「中核人材の登用等における多様性の確保」、「取締役会の機能発揮」、「サスティナビリティへの取り組み」の3点について、財務経理部の田中那奈とコーポレートブランディング部の大槻幸夫が、青野に聞きました。
中核人材の登用等における多様性の確保について

そこでまずサイボウズの現状をお伝えすると、下図のようになっています。
中核人材の登用等における多様性の確保について(サイボウズの現状)
▼管理職における女性数 (2021年11月末時点 ※管理職:副部長以上)
→16名、24.2%
▼管理職における中途採用者数 (2021年11月末時点)
→50名、75.8%
▼外国籍社員数 (2021年11月末時点)
→20名以下
▼障害者雇用者数 (2021年3月末時点)
→7名(障害者雇用率:1.01 %)
▼男性育休取得者数 (2021年11月末時点※育児休業給付金申請者が対象)
→32名 (平均取得期間:1.9か月)

続いて、管理職における中途採用者の比率は75%を超えており、新卒と中途での昇進障壁はないように思います。
最後に外国人の比率に関しては、サイボウズ単体だと20名以下とまだまだ少ないのが実情です。
これらの状況について、青野さんはどう見ていますか?

表面的な要素で人をカテゴライズするのではなく、各個人の内面にある多様性に着目できるようになればいいな、と。
ただ、サイボウズにはまだまだ「隠れジェンダーギャップ」があると思っていて。
たとえば、Cybozu Days 2020のセッションでは、若手女性メンバーから「サイボウズで働く先輩ママを見ていると、将来が不安になる」という声が上がりました。
育休取得が進んでいるサイボウズでも、「産休後の給与が新人よりも低くなってしまう」、「子どものお迎えの度に申し訳なさそうに退勤している」など、いまだに出産する人だけが背負う損失がある。
そういうギャップはまだまだ残っているはずなので、意識的に変えていきたいと思っています。

青野 慶久 (あおの よしひさ)。サイボウズ代表取締役社長。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年サイボウズを設立。2005年に現職に就任し、現在はチームワーク総研所長も兼任している。著書に『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。』(PHP研究所)など

サイボウズは本部長のほとんどが40〜50代と現役なので、無理に世代交代をしなくてもいい。その結果、この10年間ほとんど代わっていない。
これは事業としては問題ないかもしれません。ただ、属性が固定化されることで、僕たちの隠れたジェンダーギャップが残り続ける危険性もあって。経営陣に関しては自分も含め、入れ替え制にしていきたいと思っています。

どんなに多様なメンバーを経営陣にそろえたとしても、入れ替えが起きないと、やっぱり価値観が固定化されてしまうと思うんです。
だから、経営陣を任期制にするのは、ひとつあるかもしれません。



サイボウズでは、誰でもプロジェクトを起案できますし、関係するメンバーからアドバイスをもらう「助言プロセス」を取り入れています。
新人であっても、このプロセスに参加することで、会社の大きな意思決定に携われる仕組みです。
したがって、実質メンバー全員が取締役と同じ役割を担えるので、誰が取締役になってもいいじゃないか、と。そういう背景から社内募集をしたわけです。
本部長(経営陣)もそれと同じ形にすればいいかもしれません。「本部長」という肩書きをつけたい人はつければいいけど、実質的にはみんなが本部長と同じ役割を持っている、という。


たとえばチーム内の人事の問題に関して、マネージャー1人で意思決定するのではなく、本部長とも人事とも話せる。多数の意見を参考にしながら、意思決定できれば、ストレスなく立ち向かえる気がします。



サイボウズはグループ全体で1000人規模となっており、いまはアメリカ(Kintone Corporation)のメンバーともプロジェクトを進めています。
そんなふうにグループ全体で仕事をしていくなかで、自然と混ざり合うのが理想だと考えています。だからこそ、強引に外国籍の人を引き入れることには、とまどっていて。おたがいにとってよいことなんだろうか、と。

そうした点において、意識的に外国籍のメンバーを入れることは意味があるのかなと思っていて。そのあたりはいかがでしょうか?

さらにインフラが整備されると、同じ属性をもつ人たちも入社しやすくなる。この流れはどんどん作っていきたいと思っています。

そんな意識をもつ日本人メンバーには、どういうマインドをもってほしいと考えていますか?

何より、いくらビジョンに共感してくれていても、「英語が使えない」という理由で入社が制限されてしまうのは大きな損失です。
正直、言語の部分は同時通訳機能などのテクノロジーに期待したいところです(苦笑)。


サイボウズには「質問責任・説明責任」がありますが、言いづらいこともあるはず。だからこそ、日本人・外国籍メンバーが双方向で寄り添うべきだと思います。

そうすれば「〇〇については整備がまだまだだな」とわかるし、そこから「この部分はもう少しよくしていきたいよね」と思えるメンバーが増え、全社として意識が上がっていくのかなって。

そう考えると、管理職の女性・外国籍・中途採用者の比率といった指標ではなく、僕たちが目指している世界観での指標を設定できたらいいですよね。
いかに権限を分散できたかを測る指標として、「管理職撤廃率」を設定するとか。
取締役会の機能発揮

プライム市場では、独立社外取締役の割合は3分の1(必要に応じて半数)以上選任することが要請されています。
これはガバナンス強化のためという側面が強いかと思うのですが、サイボウズでは取締役の社内募集などまったく異なるアプローチを取っていますよね。

だから、形式的に社外取締役の割合を増やすよりも、どれだけの情報にアクセスできるのか、内部の不祥事をどれだけ見つけられるのか、その辺の仕組みづくりを重視したほうがいいのでは、と思っています。



あと、そもそもサイボウズでは、社外取締役の割合を高める以上に、遥かに社外の意見を取り入れている実感があります。
というのも、サイボウズではこの数年間、新人社員や中途メンバーを100人以上採用しており、その全員があらゆる情報にアクセスできて、発言しやすい環境をつくっています。
つまりイメージとしては、毎年社外取締役を100名採用しているようなものです。
常に新しいメンバーの声が入ってくるため、自分たちの考えに固執して整合性を保てなくなる、というのもないように思います。
サスティナビリティへの取り組み

これらを踏まえて、青野さんはどう受け止めていますか?
サステナビリティに関する取り組みについて
▼災害支援活動 (2021年11月末時点)
・災害支援ライセンス:46団体
・社内災害支援チーム:41名
・災害支援パートナー:14社
▼チーム応援ライセンス
・2,400ドメイン (2021年11月末時点)
▼地域クラウド交流会
・2019年11月に、糸魚川市開催にて累計参加者2万人突破
・22都道府県、65市町村、160回を超える開催実績 (2021年11月末時点)
▼スクール&ペアレンツライセンス ※2021年7月1日提供開始

その点、サイボウズの場合、kintoneなど情報共有ツールを通じて働く上での課題を解決するなど、事業自体が社会貢献につながっています。
ほかにも、kintoneを導入している会社から「ペーパーレス化に成功して紙を使わなくなった」という話を聞いたこともあります。
サイボウズの事業は次世代のためのものなので、事業を頑張るのもサステナビリティへの取り組みの一環なのかなと思いますね。


その点、先日Twitterで盛り上がっていた「過去5年間、サイボウズの平均年収が変わっていない」という話は人的投資に当たりますよね。
ご指摘をありがとうございます。これは見逃せません。サイボウズは日本の平均を上回る昇給率を続けてきた認識ですが、有価証券報告書に掲載されている平均年収の数字が上がっておりません。状況を確認するとともに、社内の隠れたジェンダーギャップとともに見直しを進めさせていただきます。 https://t.co/dI638ddeaB
— 青野慶久/aono@cybozu (@aono) November 8, 2021

実際、サイボウズ社内では昇給率が高まってきていると盛り上がっていたので、実態をしっかりお伝えしたいです。

それに、働きやすさなど給与以外の要素を含めて、評価しているメンバーも多いと思います。

持株会なども福利厚生としてありますし、そういう見えない報酬も含めて、指標を出していきたいですね。




ただ、他社の環境報告書を読んでみると、すごくよくまとめられている一方で、「やらされている感」があるようにも思えて……。
サイボウズにも、こうした専門の部署・役職は必要だと思いますか?

だから僕としては、メンバーの自発性に期待したいところがあります。

その意味では、サイボウズにはサステナビリティに関心の高い若手メンバーも多いので、彼らといっしょに理想をつくってみるのは楽しそうだな、と。


逆に「これをやると、こんないいことがありました」といった根拠や目的を示せると、「いいね」という実感を持ってもらえて、物事が速く進むイメージがあります。

最後に

長時間労働や飲みニケーション、紙・ハンコなどのアナログ文化、不透明な意思決定、パワハラ・セクハラ……。
こうした古い価値観のもと同質性を強いる「オッサン文化」が、若者や女性たちの活躍を妨げ、経済を停滞させている、と。


同質性を求めることが、平和や環境などさまざまな問題を引き起こしていると考えれば、このオッサン文化を崩さないことには何も進まないと、より強く感じましたね。


このオッサン文化を壊すためには、何から始めるといいですかね?


ただ、セッション内で若手女性メンバーとの対話を通して、「たしかにアップデートしていかないといけないね」と思えたわけで。
やはり自分の常識にとらわれずに、相手の言葉に耳を傾けることが大事ですよね。

考え方が違う人が対話をやめた瞬間に、何の交わりもなくなって、進歩も生まれなくなる。
違う人同士が話さない限り、物事は変わらない。だから対話から逃げないでほしい。上がってきた意見に蓋をせず、耳を傾けてほしいです。
対話があらゆる課題のスタート地点なので。
企画:大槻幸夫(サイボウズ) 執筆:中森りほ 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト)
【サ式YouTube】サイボウズの給与の決め方について、取材してみました!
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集