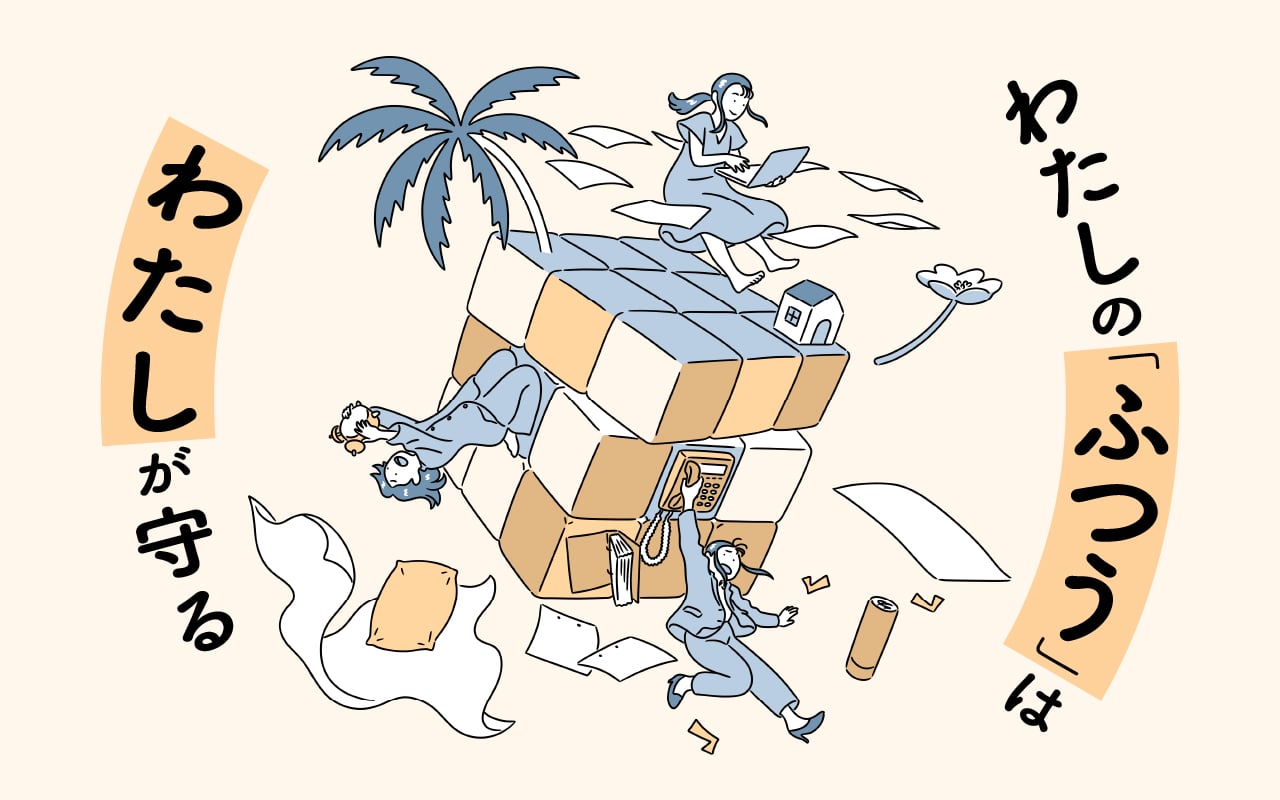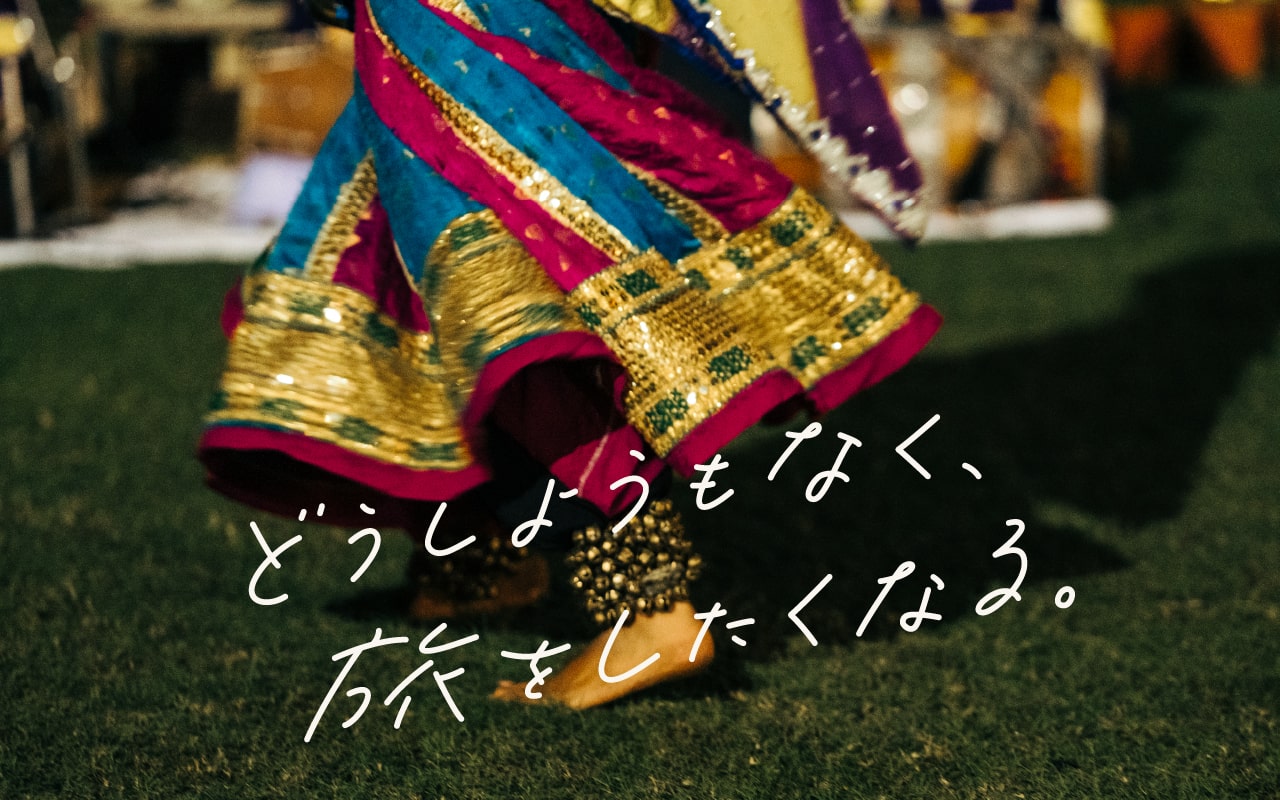「ふつう」を、問い直してみよう。
「ていねいな暮らし」をなぞる前に、自分にとって快適な状態を知ろう

本特集『「ふつう」を、問い直してみよう。』では、サイボウズ式ブックスから発売された書籍『山の上のパン屋に人が集まるわけ』をきっかけに、さまざまな人と一緒に「ふつう」について考えていきます。
今回は、『世界は夢組と叶え組でできている』著者・桜林直子さんに、「丁寧な暮らし」についてコラムを寄稿いただきました。
「時間とお金の使い方」を考えた30歳
「働きかた」とか「暮らしかた」という言葉をよく聞くようになり、すっかり耳や目に馴染んで久しい。しかし、それについて考えようとすると、なんとなくふわっとしたイメージに留まってしまう言葉でもある。
わたしは、「働きかた」「暮らしかた」が何を指しているかといえば、つまり「時間とお金を何に使うか」ではないかと思う。
働き始めてすぐの若い頃は、仕事と休みがくっきり分かれていた。単純に、仕事の時間以外は自由時間だったし、お金は仕事で稼いで休みで使うというわかりやすい構造だったので、限られたその自由時間とお金を何に使うかを考えて、やりくりしていた。
子どもが生まれ、シングルマザーになってからは、仕事の時間が終わってもやるべきことが山のようにあって、家事や子どもの世話をやっつけるように片付けるのが日常になった。大袈裟ではなく、寝ている時間以外は常にやることに追われていた。
そんな日常に疑問をもち、このままではいけないのではと思うようになったのは30歳に差し掛かる頃だった。それまでは、どんなに大変でも、疑問や不満をもったところで、シングルマザーという立場上、家事も育児も収入を得ることも、「他にやる人がいないのだから自分ひとりでやるしかないわけだし」と、考えることすらやめていたのだと思う。
時間が足りないのは「仕方ない」のだろうか?
子どもを育てていると、仕事と家事と育児の時間をすべて十分にとるのはむずかしい。大抵の場合は、まず仕事の時間が固定され、それ以外の時間をどう使うか、難易度の高いパズルに悪戦苦闘することになる。
しかし、それだとどうにも時間が足りないのだ。仕方なく睡眠時間を削ったり、子どもと一緒に過ごす時間をとれないままになったりする羽目になることに、「いやいや、それじゃ困るんだけど、本当に仕方ないのだろうか?」と、怒りにも似た疑問をもつようになった。
そこで、生活を「仕事の時間」と「それ以外の時間」に分けずに、すべてひっくるめた「時間」をどう使うかについて、根本的に考えることにした。
通常は夫婦ふたりで手分けしてできることも、わたしはひとりでやらないといけないので、時間が足りなくなることは明確だ(話を聞いていると、どうやらふたりでも足りないらしい)。どんなに願っても残念ながら1日の時間を24時間以上に増やすことはできないので、使い方を変えるしかない。
では、時間をどう使えば、ひとりで子育てをしても仕事と生活を両立できるのか。考えた結果、仕事の時間を固定せず、なおかつ仕事に使う時間を半分に減らして、収入をそれまでの倍にすること。それができないと、共稼ぎの夫婦と同じ時間の使い方ができないとわかった。
そんなことできるのか?と怯んだが、何度考えてもそれしかないので(大富豪に出会い突然経済面の解決をしてくれる可能性なども考えられるが、いささかファンタジーが過ぎる)、どうしたらできるかをひたすら考えた。
本気で考え続け、結果的には2年後に会社を辞めて独立し、自分で事業を始めることになった。
自分の欲を見つけるために、まず困っている状態をなくす
その2年間、考えるために徹底的に向き合ったことは、「自分がどうしたいか」の欲を見つけ、優先順位をつけることだった。
仕事とそれ以外に分けず、生活に望むものは何か。すぐにできそうなことから、高望みで到底できそうにないことまで、とにかくたくさん出してみる。それを、容易い順ではなく、本当に望んでいる順に並べ、優先順位をつけた。
ただ、わたしの場合、「こんな生活をしたい」と望む以前に、困っている状態があった。「こんな生活をしたい」と想像したときに「でも〇〇だからできない」と邪魔をするものがあれば、ひとまずそれを取り除く必要がある。
だから、まずは「困らない状態にすること」を最優先にした。わたしが困っていた要因は「時間が足りない」と「お金が足りない」だったので、とにかく「時間とお金を生み出すこと」だけを優先して、大事にすることにした。足元がグラグラで土台がないと、その先の望みは出てこないのがわかっていたので、一旦それ以外を捨てて全振りできた。
実際に働く時間を固定せずに減らし、仕事以外に使える時間を作り、収入を増やすことができたときに、ようやく「こんなことをしてみたい」と新たな欲が出てきた。そして、空いた時間で文章を書いたり、子どもと一緒にあちこちに旅行をしたりできた。やはり、まずは困っていることをなくし、平地に立たないといけない。踏み出せない状態では欲は出てこないのだと実感した。
誰かの真似ではなく、自分にとっての「快適さ」を知る
生活や暮らしについて改善しようとすると、つい理想を追いかけて背伸びをしてしまう。ただ、その理想の暮らしは、誰かから提案されたものや、誰かに羨ましいと思われるものなどで、なんとなく世間一般でいいとされているものでしかなく、自分にぴったりではないこともある。
とはいえ、雑誌の中の「ていねいな暮らし」を真似するのは楽しく、わたしもかつて試みたことがある。素敵なものを買うことで表面上は満足するし、生活に少し手間をかけることで心は潤うのだが、突き詰めようとすればどうしたって「結局はお金や時間に余裕がないとできないのか」とわかってしまい、中途半端に諦めることになる。
だから、誰かの「ていねいな暮らし」をなぞる前に、自分にとって快適な状態とは何かを知る必要がある。それは、100人いたら100通りそれぞれにあって、誰かのインスタを見てもライフスタイルを提案するお店に行ってもわからない。自分にしか知り得ないのだ。
「ていねいな」は所作であり、「快適な」は状態だ。暮らしについて考えるとき、所作の前に、まずは状態を整えるといい。住んでいる場所、同居家族の有無、時間の使い道、年齢、動かせない事情、譲れない希望、など、あらゆる条件が異なれば、「快適な暮らし」の形は当然人によって変わる。自分にとって快適な場所で快適な時間の使い方ができれば、ていねいに暮らそうがガサツに暮らそうがしあわせなのではないか。
自分にとって快適な状態とはなにか。自分だけのオリジナルの欲を知り、条件を探り、そのために何をすればいいか考える。もしも困っていたら、高望みしたり諦めたりする前に、まずは困らない状態にするのが先だ。
こうして「時間とお金を何に使うか」の配分を決め、具体的に何をすればいいかがわかれば、きっと「働きかた」「暮らしかた」をよりよくしていくための入り口が見えてくるだろう。
道のりが長く、気が遠くなるかもしれないが、これから先もずっと時間をどう使うかは決め続けるのだから、早いうちに考える癖をつけておくといいのではないかと思う。
執筆:桜林直子/編集:深水麻初/イラスト:芦野公平/デザイン:駒井和彬
サイボウズ式特集「ふつうを、問い直してみよう。」

世の中にある、「ふつう」という言葉。「みんなと同じ」という意味で使われていますが、「ふつう」って、実は一人一人違うもの。長時間労働が「ふつう」な人もいれば、家族第一が「ふつう」な人もいる。世の中ではなく、それぞれの「ふつう」を尊重することが必要なのではないでしょうか。サイボウズ式ブックスから発売された『山の上のパン屋に人が集まるわけ』をきっかけに、さまざまな人と一緒に「ふつう」について考えてみます。
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集

深水麻初
2021年にサイボウズへ新卒入社。マーケティング本部ブランディング部所属。大学では社会学を専攻。女性向けコンテンツを中心に、サイボウズ式の企画・編集を担当。趣味はサウナ。