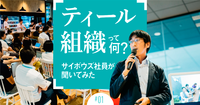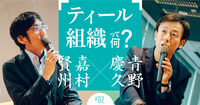ひどかったサイボウズがティール組織っぽく変われたのは、経営者の「深い内省」があったから──嘉村賢州×青野慶久
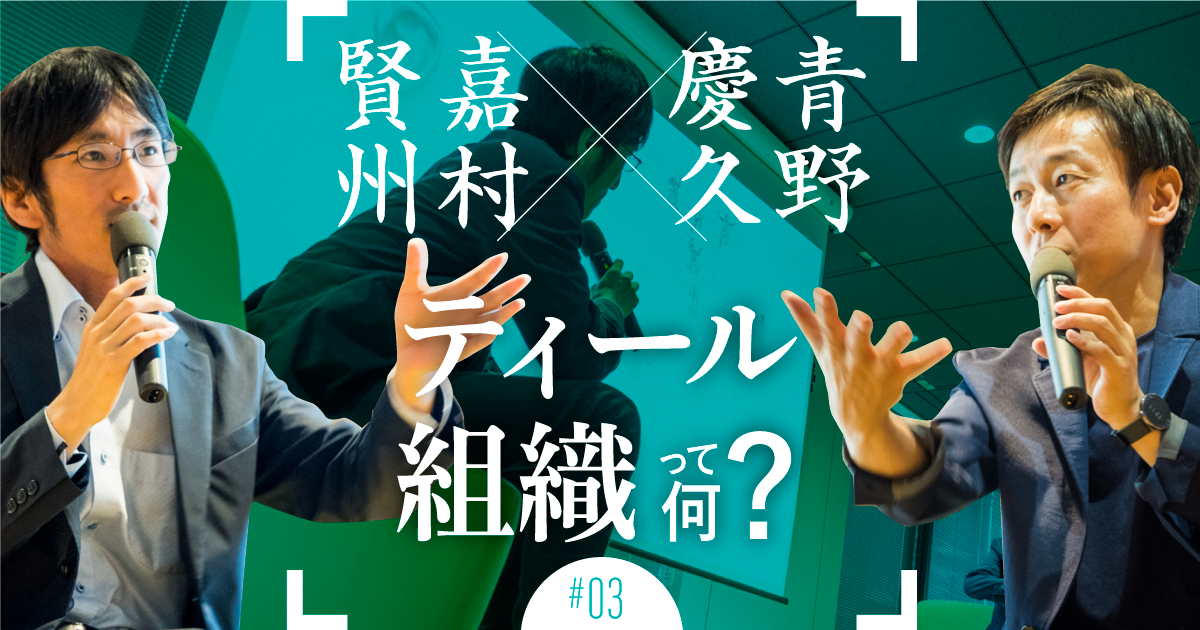
「組織形態に優劣はない」「個人がありのままでいられる組織が力を発揮できる」「ティール組織への変革は良いことばかりではない」
ティール組織を勉強するために、サイボウズで開かれた社内勉強会(第1回、第2回)。新メンバーが安心して本領発揮できるプロセスを段階的に会社に取り入れるべきなど、新たな学びもありました。
サイボウズとティール組織との違いや共通点が明らかになってきた本連載。最終回では、サイボウズの変遷から、これからの社会全体で求められる会社についてまで、ティール組織第一人者の嘉村賢州さんとサイボウズの代表取締役社長・青野慶久が話します。
経営者は半年から1年をかけて、まずは「内省」を。従業員に先に変革を求めるのはNG

「ティール組織に変革するためのたった2つの条件」という箇所です。これにはドキリとしました。

青野慶久(あおの・よしひさ)。1971年生まれ。愛媛県今治市出身。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現 パナソニック)を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立した。2005年4月には代表取締役社長に就任(現任)。社内のワークスタイル変革を行い、2011年からは、事業のクラウド化を推進。著書に『ちょいデキ!』(文春新書)、『チームのことだけ、考えた。』(ダイヤモンド社)、『会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない』(PHP研究所)など。




ティールの概念が広がったことで、「自分の会社をティール的に進化させるには、まず社員に何をさせればいいか」と経営者の方から相談をよく受けます。
ただ、この時点ですでに考え方が間違っているんです。

嘉村賢州(かむら・けんしゅう)1981年生まれ。兵庫県出身。京都大学農学部卒業。IT企業の営業経験後、NPO法人 場とつながりラボ home's viを立ち上げる。人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。2015年に1年間、仕事を休み世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会い、日本で組織や社会の進化をテーマに実践型の学びのコミュニティ「オグラボ(ORG LAB)」を設立、現在に至る。

その内省をせず、社員にいきなりティール的な働き方をさせようとして成功するのは、ほぼ不可能です。



「会社の危機に残ってくれたメンバーに、命を懸けてもいいと思った」





「上場企業だから、もっと会社を成長させないと」と思っていましたが、やることなすこと失敗の連続でした。
1年半で9社を買収するも、マネジメントができず大赤字で。持っていた現金はすべて使い果たし、借金で何とか回しているような状態で、当然離職率も高いわけです。



「これではいかん」と初心を思い出しました。まずはグループウェアに注力するため、買収した9社のうち8社を手放しました。売り上げは3分の1に激減しました。


社員全員が、退職してもおかしくないような状態だったはずなんです。それでも、残ってくれたメンバーがいる。本当にありがたかった。
ある意味、「青野慶久」は一度、死んだも同然でした。そこで残った命は、サイボウズに残ってくれたメンバーに懸けてもいいと思ったんです。




グリーン組織ではどうしても社長がちゃぶ台返しのように現場に介入してしまう機会が多く、ティール組織では、そういう機会がだんだん減っていく傾向にあります。青野社長の場合なにか「こういうときは口に出す」と決めていることはありますか?

“チームワークあふれる社会を創る”という理念に向かっていなければ、徹底的に突っ込みます。
それから、嘘をつくのもNGです。もし嘘が見つかれば、現場のどんな小さい嘘でも介入します。もし寝坊して遅刻したなら、「寝坊した」と言わなければなりません。嘘を認めると、多様な人たちが信頼関係を築けないからです。

経営者には経営者にしか果たせない役割がある

ティール組織における経営者の役割は大きく3つ。「組織の顔」「ソースにつながる」「ティールを維持する」です。


「株式会社は売り上げや利益を前年以上に増やすべき」など、資本主義の制度では“べき論” があふれています。その多くはティールの概念と考えが合いません。
そこで求められる経営者の大きな役割は、自分たちのソースとつながり続けること。外発的な”べき論”で組織の方向性を示すのではなく。本当はどうありたいのか?どこに向かいたいのか?を常に探求し続けること、そして組織がそこに向かっているかを感じ続けることです。
決してそれを指示命令で押し付けるのではなく、語り伝えたり、語り合える場を整えていくことです。


スティーブ・ジョブズのような創業社長はソースに立ち返る力が強いと思います。経営者のソースにつながる力が弱いと、組織としてぶれやすくなってしまいます。


組織のマネジメントや意思決定、問題発生時の介入などは、どんどん手放していいとされています。


プロジェクト単位での兼業や副業は、もはや当たり前の時代


「会社」という枠組みがあいまいになると同時に、プロジェクトがたくさん生まれて、連携する社会になるのではないでしょうか。


時代や社会に応じて、柔軟に変化する企業に人が集まり、プロジェクト単位での兼業や副業が当たり前になるんだと思います。



実際に、オランダの訪問医療会社ビュートゾルフは、5年で10人から9000人に成長しました。その過程で、自社のノウハウをすべて公開するどころか、ライバル企業の顧問を無料で引き受けていたりするんです。

会社という枠組み自体の概念が、変わっていきそうですね。これはおもしろいです。
ティール組織が当たり前になるには、会社法の抜本的な見直しが必要



株式会社の仕組みも、どうしても経営者が数字的な圧力を感じやすいですよね。


実際にヨーロッパでは、すでにそういう動きも始まっていますから。




ティール組織が増えれば、法改正も起こりうる。ますます変化が加速するかもしれません。

それにもかかわらず、ティール型組織の大多数が、同業他社に比べて売り上げや給料を上げています。これはおもしろいですよね。
ティール組織の誕生は時代の必然。「変革したい組織」をテクノロジーが後押しする




ティール組織において、採用時には「テストでふるいにかける」「人を使う」などの言葉は使われなくなります。人と組織はもっと対等な関係だからです。


ティール組織が誕生してわずか数十年。技術がこれからどう進化し、どのような新しいシステムが生まれてくるのか。可能性に満ちあふれる、わくわくする社会が広がっていると感じます。
構成:玉寄麻衣/編集:松尾奈々絵(ノオト)/撮影:二條七海 /企画:森信一郎
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

二條 七海
写真家→ホームレス→LIG.inc→フリーランスフォトグラファー。 現在は著名人や芸能人の人物撮影を中心に行っている。 多様な作風が持ち味。好きな食べ物はハンバーグ。
編集