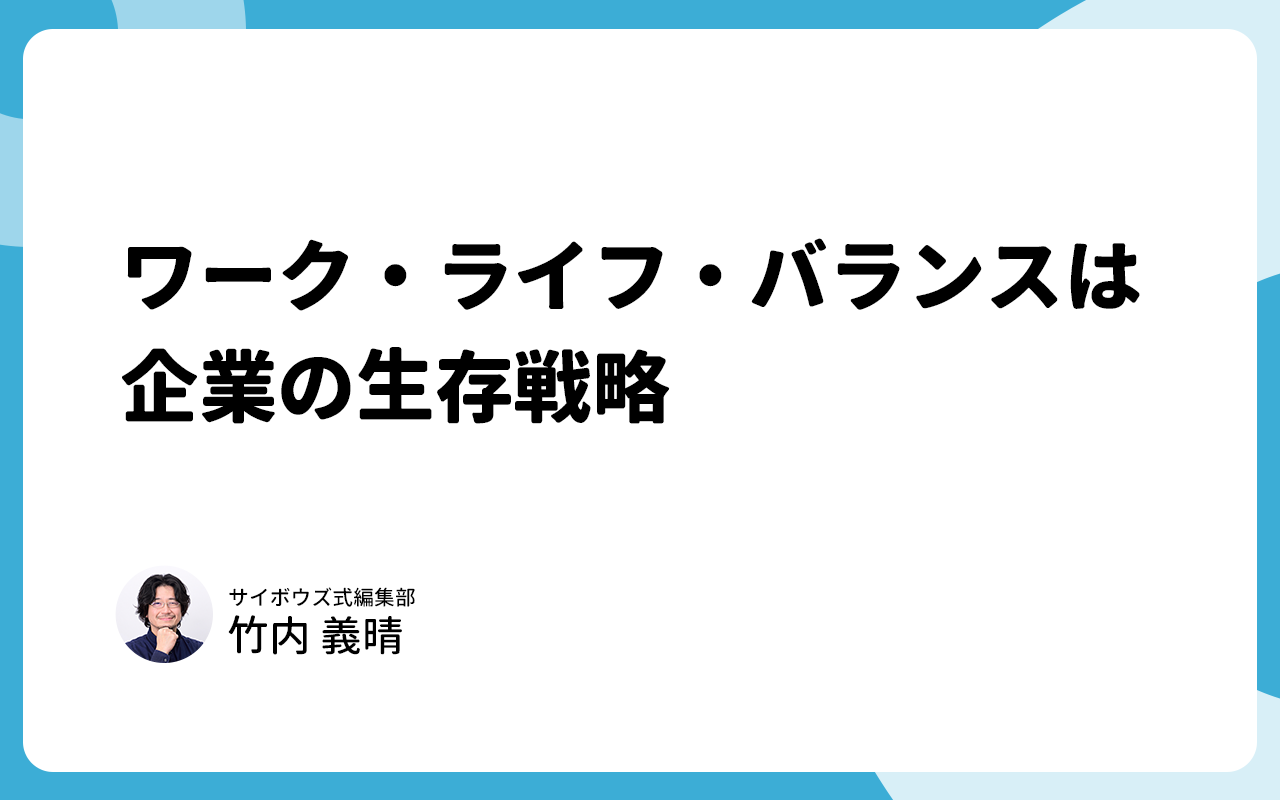長くはたらく、地方で
憧れの二拠点生活「でも何から始めれば?」――地方で複業する課題と理想を話し合ってみた

「二拠点生活」が実現できれば、これからの社会にどんな可能性が生まれるんだろう――。
ここ数年、住まいや本業を都市部に置きつつ、2つ目の仕事を地方で行う、「二拠点生活」や「地方での複業」に注目が集まっています。
自分らしい働き方の確立、地方での人材不足や「都市×地方」の交流による発展性など、さまざまなインパクトが期待されています。
しかし、実現するには「そもそも地方に受け入れ態勢はあるの?」「収入が減るのでは」「子育てはどうする?」などの課題もたくさんあります。
「地方×複業」のメリットやデメリットについて考えながら、自分らしく働くためのヒントを「#サイボウズ式Meetup Vol.11」で探りました。
今回のゲストは、Wantedly 広報の小山恵蓮さんと、新潟県妙高市役所 企画政策課の藤野加奈子さんです。そしてサイボウズ式編集部からは、東京と新潟で、複業&二拠点生活を実践している竹内義晴が登壇しました。
「二拠点生活」で地方の問題を解決できる? それって甘いんじゃないの?
僕はサイボウズで複業を始めてから、「都市部で働く人が地方の企業で複業できたら、とても良いことが起こるんじゃないか?」と考え始めました。
たとえば近年、二拠点生活に興味を持っている人が増えていると聞きます。二拠点生活って、都市部に加えて、地方とも関わることができるので、より自分らしく働けるんですよ。
そこから、地方で複業する人が増えると、人材不足を解決できたり、経験やスキルを地元に役立てられたり、それによって地方の衰退を防げたりするんじゃないかなと。
ただ、課題もあります。その想いをサイボウズ式の記事で書いてみたら「いやいや、そんな甘くないよ」という反応があって。

竹内義晴(たけうち・よしはる)。1971年、新潟県妙高市生まれ・在住。ビジネスマーケティング本部コーポレートブランディング部 兼 チームワーク総研 所属。新潟でNPO法人しごとのみらいを経営しながらサイボウズで複業している。コミュニケーションの専門家。「もっと『楽しく!』しごとをしよう。」が活動のテーマ。
「二拠点生活」や「地方×複業」って、どうすればうまくいくのか。今回のイベントで、そこを模索したいと思っています。

藤野加奈子(ふじの・かなこ)さん。1990年、新潟県妙高市生まれ。妙高市役所 企画政策課 未来プロジェクトグループ。市民税務、農林の業務を経て、現在は市における新たなプロジェクトの企画立案に向けた調査研究を担当している。
これからは「仕事を通して都市部の人と関わりを持てないだろうか」と、市としても模索しているところです。
地方の自治体さんでWantedlyを使うケースは増えています。理由は「若手のIT人材が足りていないから」ですね。
「複業」の検索数は今年に入ってから増えています。「複業をしたくてWantedlyで検索した」などのツイートもあり、ニーズは高まっているなと感じています。

小山恵蓮(こやま・えれん)さん。1989年、埼玉生まれ。新卒でサイボウズに入社し、マーケティングコミュニケーション部で中小企業向けグループウェアのプロモーションを2年半、自社カンファレンスの運営を1年間担当。その後、PR会社で広報とクライアントのPRを1年ほど経験し、現在はWantedlyの一人広報として奮闘中。
二拠点生活から始めればスムーズ? 移住との違い
一言でいうと、「気軽にできるかどうか」だと思うんです。
移住するまでの道のりって、かなりハードルが高いでしょう? 今の仕事を投げうってでも地方にやりたい仕事があるのか。家族は了解してくれるのか。子どもはどうするのか。いろんな問題があります。

どちらも良い点はありますが、まず、その地域に関わりやすいのは、二拠点生活ですね。
なので、もし地方に興味があっても、友達や知り合いがいない場所にいきなり飛び込めるかというと、やはりハードルが高いです。
そんな私のような立場からだと、とりあえず二拠点生活から始めて、そこから徐々に知っていく、というのはすごく大事なんじゃないかと思いますね。
自治体も企業も、どういった人やノウハウ、スキルが欲しいのかを考えて
もし、都市部のビジネスパーソンを複業で受け入れたら、その部分を補える可能性もありますよね。まだそこのメリットはあんまり気づかれていないんじゃないのかな。
藤野さんはメリットについてどう思いますか?
最近はそのような「地元のファン」「地域の仲間」のような人のつながりのことを「関係人口」とよんでいます。
ただ、自治体にしろ企業にしろ、どういった人やノウハウ、スキルが欲しいのがわからない状況だともいえます。
都市部で働く人も、自分のスキルが具体的にどういう場面で使えるか、なかなかわからないのかな、と。

移住はハードルが高いので、複業をはさむことによって、二拠点生活や移住がもっと活性化されるかもしれません。
「本当は地元で働きたい」という潜在ニーズがある?
1つは移住よりもハードルが低いこと。
2つ目は個人のモチベーションアップ。自分のノウハウによって、地域の活性化に貢献していると実感できます。
そして3つ目は、地方に対する興味につながることですね。自分が持っているノウハウや経験を地方で生かせるかもしれない。
ただそのメリットに気づいてはいても、実際に複業を始めるにはまだ課題がありますよね。地方で複業を始める場合、何から始めればいいんでしょう?
そうじゃないと、いいマッチングは生まれないですよね。

そもそも「都市部の人材を複業採用する」という考えがあんまり浸透していないので、どういった効果を生むのかを認識している経営者は、ほとんどいないと思います。
私の親は今75歳なんですが、親の老いをすごく感じます。もし僕が神奈川で働いていたら、親の様子が気になるけど何もできない状態になっていたでしょう。
「本当は地元で働きたいけど仕事がない」「戻りたいけど東京で生計を作ってしまったから、もう無理」というケースも多い。
そういう人が地元で複業できれば、今まで以上に関心を寄せられるメリットは大きいですよ。
何も知らずにいきなり「複業しに来ました」って言っても、来られた方からすると「はあ?」という反応になりますよね(笑)。
地方のニーズが都市部に伝わってない?必要なのは働き手をつなぐ仕組み
地方と都市部、双方が発信し合うことによって、良いマッチングができる可能性が出てくると思います。

お金優先なら都内にいたほうがいい 「想い」だけでモチベーションは保てるのか

今まで複業というと、なんとなく隠れてやるものでした。まずは、コソコソしないということ。「私はこんなことを、こういう想いでやりたい」と声に出すことが大事です。

モチベーションを保つためにどうすればいいでしょう?
ただ現実問題として、生活や家庭もある。二拠点生活をすると収入が下がるのは、ちょっと違う気がしていて……。難しいですね。そのあたり、行政の支援って、ありえますか?

「地域でスキルを生かしたい」「環境の良いところで住みたい」など、結局どこにポイントを置いて二拠点生活をしたい、と考えているのかによると思います。
それ以外の何かがあるからこそ「地方で複業」「二拠点生活」だと思うんですよね。
文:村中貴士 編集:松尾奈々絵(ノオト) 撮影:栃久保誠 企画:竹内義晴
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集