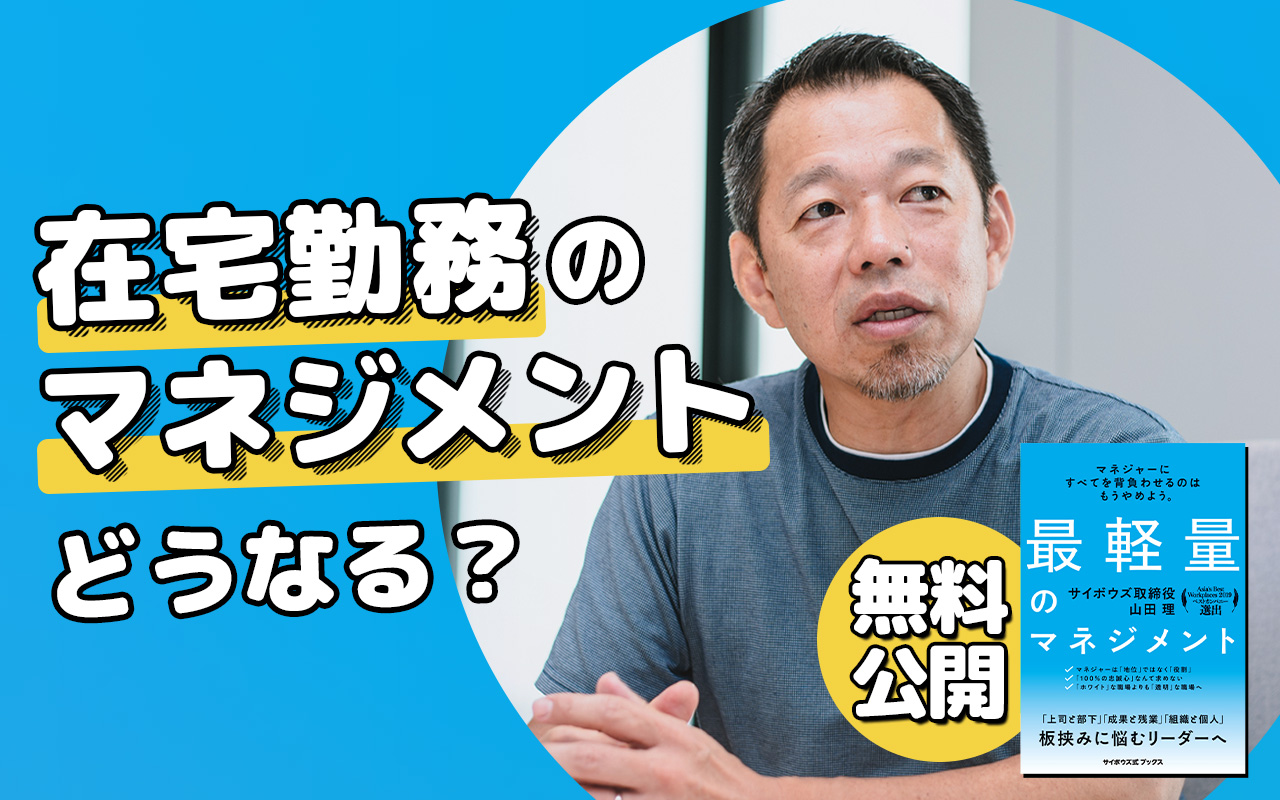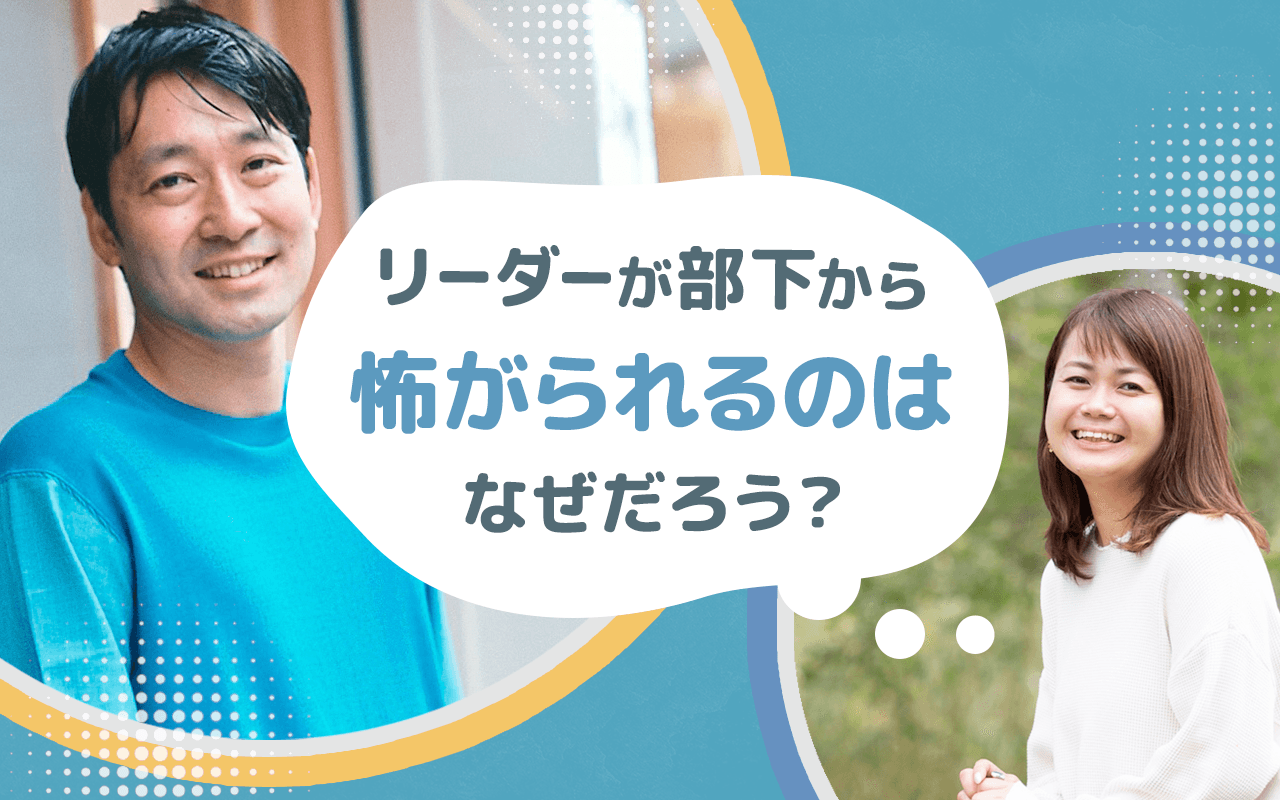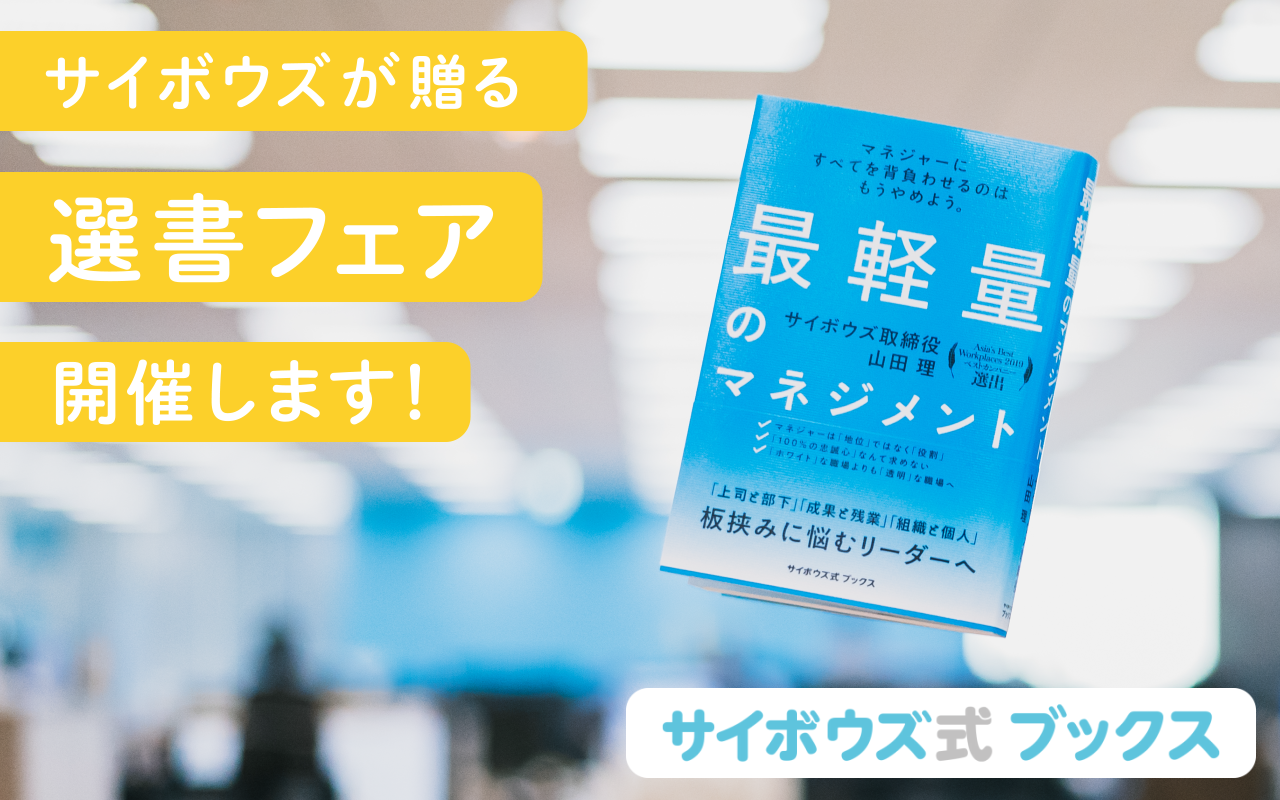これからのマネジャーについて、話そう。
上司がもみ消そうとしても、簡単にバレてしまう時代はもう来ている──『天才を殺す凡人』北野唯我×サイボウズ副社長 山田理
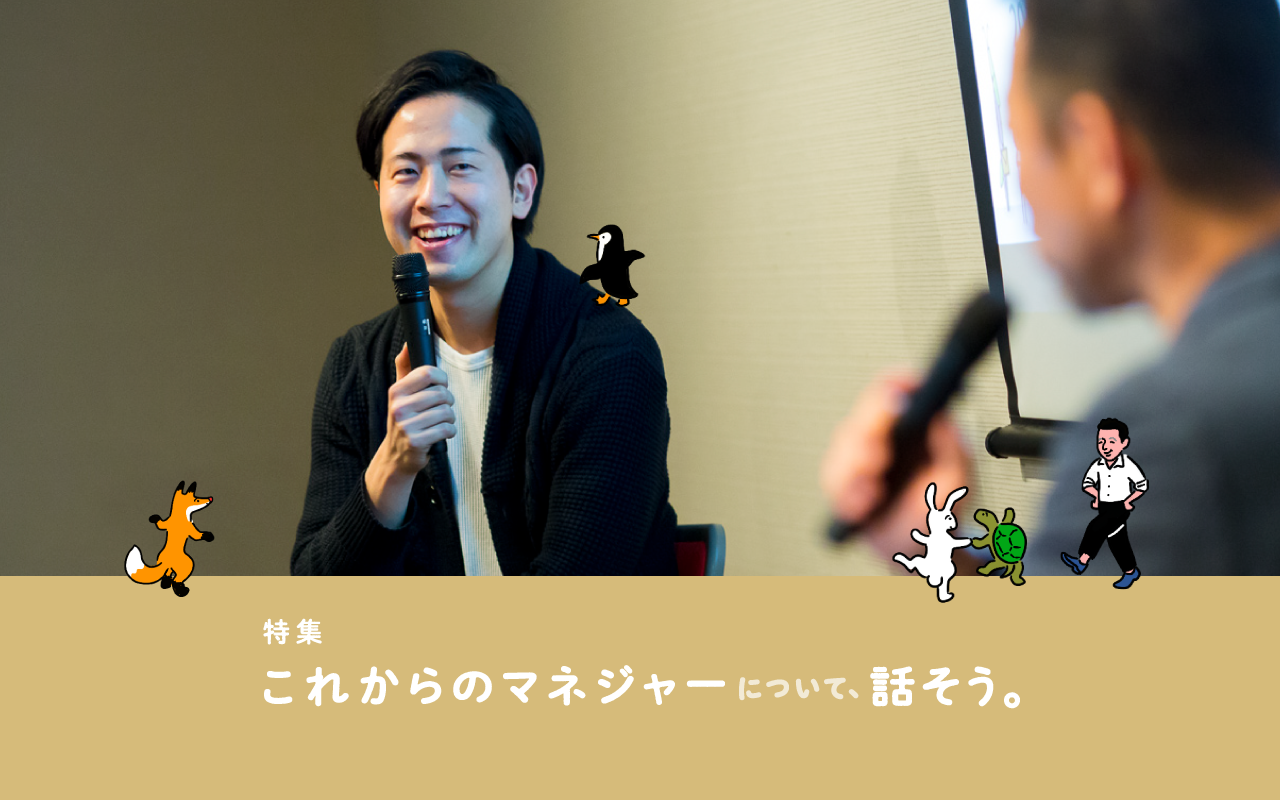
「これからの時代のマネジメントはどうあるべきか」についてまとめた本『最軽量のマネジメント』を出版するサイボウズ副社長・山田理。その出版前イベントとして、2019年1月に新著『天才を殺す凡人』を上梓した、ワンキャリア最高戦略責任者・北野唯我さんとの対談を行いました。
前編では「情報開示しない経営者は、天才を殺している」「ホワイトより透明な企業でありたい」「マネジャーには説明責任、メンバーには質問責任がある」など、組織やマネジメントのあり方について議論を交わしました。
後編では「ザツダンで心がけていることは?」「上司に質問をもみ消されてしまう」といった、参加者からの悩みや質問に答えていきます。
【質問1】メンバーとのザツダンで気をつけるべきことは?
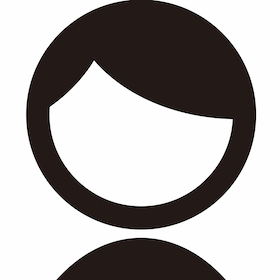
私は最近新しいチームに配属され、マネジャーのポジションに就きました。ただ、はじめての経験ということもあり、試行錯誤しています。
おふたりがどんなふうにメンバーとザツダンしているのか、気をつけていることがあれば教えてください。


仕事って、WhatとHowを聞く場面が多いじゃないですか。「何をしたの?」「どんな風にやったの?」とか。


たとえば、よく休む人にその理由を聞いてみると、家族の介護という事情があったりするんですよね。そういった行動の背景を把握しておくと、その後の行動について毎回質問しなくても理解できるようになるんです。
Whyを聞くのは、人間の存在自体を認めている。一方、WhatとかHowを聞くのは、その人の機能性の面だけを求めていると思うんですよね。

北野唯我(きたの・ゆいが)さん。兵庫県出身。新卒で博報堂。その後、ボストンコンサルティンググループに転職し、2016年ワンキャリアに参画、執行役員。2019年1月から子会社の代表取締役、ヴォーカーズの戦略顧問も兼務。30歳のデビュー作『転職の思考法』(ダイヤモンド社)が12万部。2作目『天才を殺す凡人』(日本経済新聞出版社)が発売3ヶ月で9万部。編著に『トップ企業の人材育成力』。1987年生。

ただね、僕は部下からよくこう言われるんですよ。「なんでなん? なんでなん? なんでなん? と山田さんから詰められる」と。


北野さんはWhyの聞き方で心がけていることはあります?






あとは、Whyを聞くために、Howはちゃんと工夫すること。例えば「◯◯さんは、何をしているときが幸せなの?」といったように、あえてオープンクエスチョンにすることで、「Why」の本質が見えてくる場合もありますよね。
【質問2】質問をしても上司にもみ消されることがある。説明責任、質問責任を受け止める関係性の作り方は?
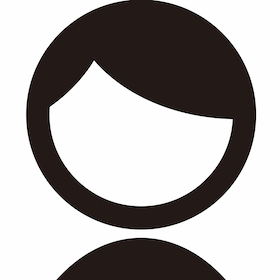
実際には上司が質問をもみ消してしまい、現場のメンバーが「やっぱり質問しなければよかった」と後悔するケースも多々あります。
説明責任、質問責任を受け止める関係性をつくるためにはどうすればいいでしょうか?

ひとつ言えるのは、密室はダメなんですよ。それは物理的な意味だけではなく、ツールを使っても同じで、ダイレクトメールとか誰も見えないところで質問すると、握り潰される。
でもみんなが見ているところで質問すると、上司は簡単に逃げられなくなる。僕もたびたび痛い目に遭っていますよ。社員全員が見られる掲示板で「これ、なんでですか?」ってツッコんでくる社員がいますから。答えないわけにはいかないんですよ(笑)。

山田理(やまだ・おさむ)。サイボウズ株式会社取締役副社長 兼サイボウズUSA社長。1992年日本興業銀行入行。2000年にサイボウズへ転職し、取締役として財務、人事および法務部門を担当。初期から同社の人事制度・教育研修制度の構築を手がける。2014年グローバルへの事業拡大を企図しUS事業本部を新設、本部長に就任。同時にシリコンバレーに赴任し、現在に至る。


会社の風土も関わってきますよね。そういうのを良しとする会社なのか、あるいは基本的にはトップダウンで「あんまり波風たてるなよ」という会社なのか。それによって質問する敷居の高さは変わるかもしれないですね。



チャレンジする価値はあると思いますけどね。どうですか?
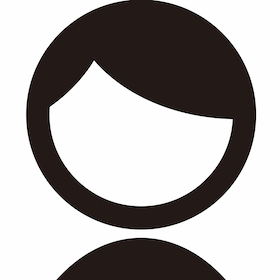
【質問3】企業が透明化されていく時代に、個人はどう選択すればいいのか?
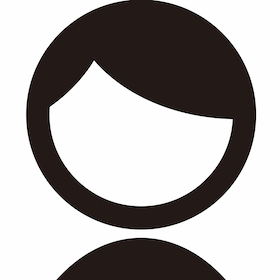
透明化がどんどん進んでいくと、情報や選択肢が増えていき、逆に選ぶ側の個人が迷ってしまうのではないでしょうか。
選択力が問われる世の中になったとき、個人はこれから何をするべきだと思いますか?


じゃあ何がいいかというと、「考えるより行動」なんですね。間違ったら次に行く。行動しながら学ぶことが大事です。
まずはやってみる、ダメならやめてみる。とにかく行動を起こして、答えを自分で見つけていく。逆にいえば、正しい答えを一生懸命考えなくてもいいんじゃないでしょうか。

グルメサイトで人気ランキング1位の店に行くのは、ある意味では思考停止じゃないですか。みんなが良いと言っているものを信じて行くことなので。


つまり、「思考の軸」を持っていない人はランキングに集約され、軸を持っている人はその軸に基づいて意思決定する、そういう時代になっていくなと思っていて。後者の人が増えた方が、きっといい社会になりますよね。


SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集