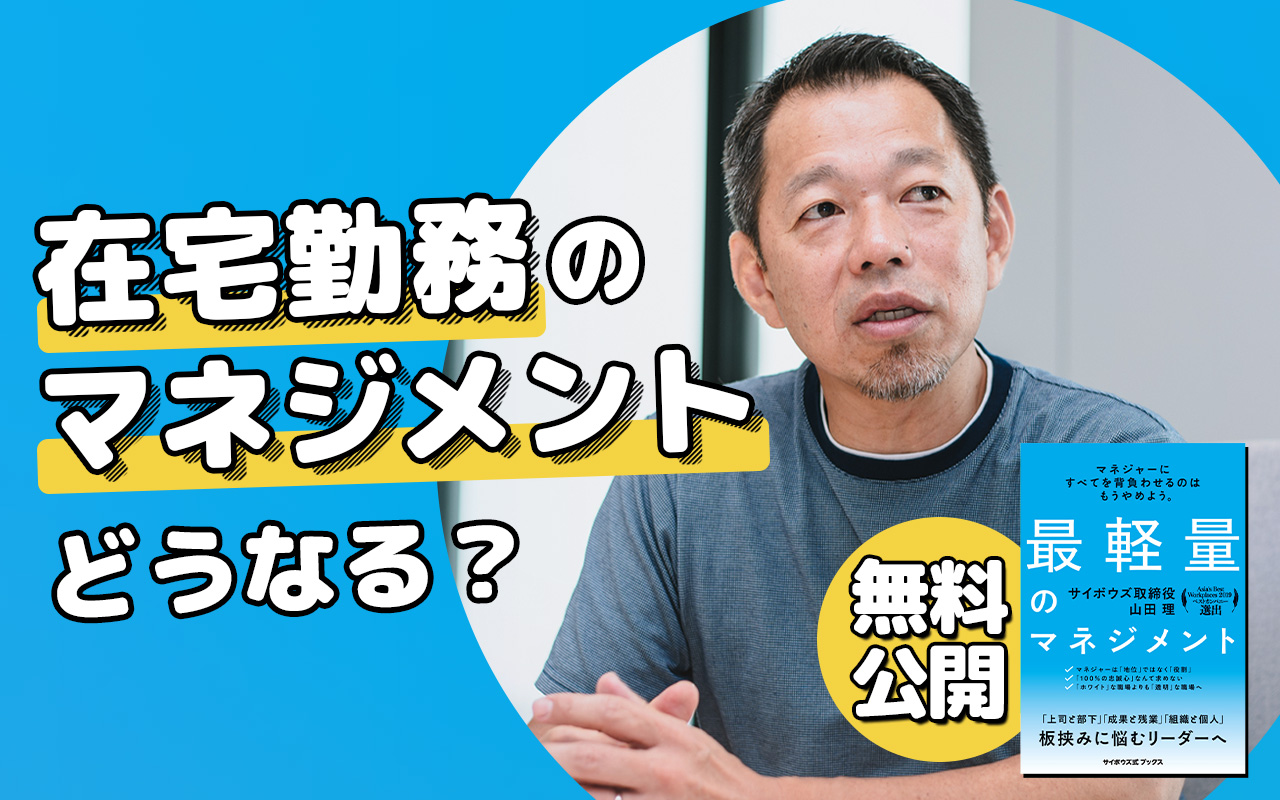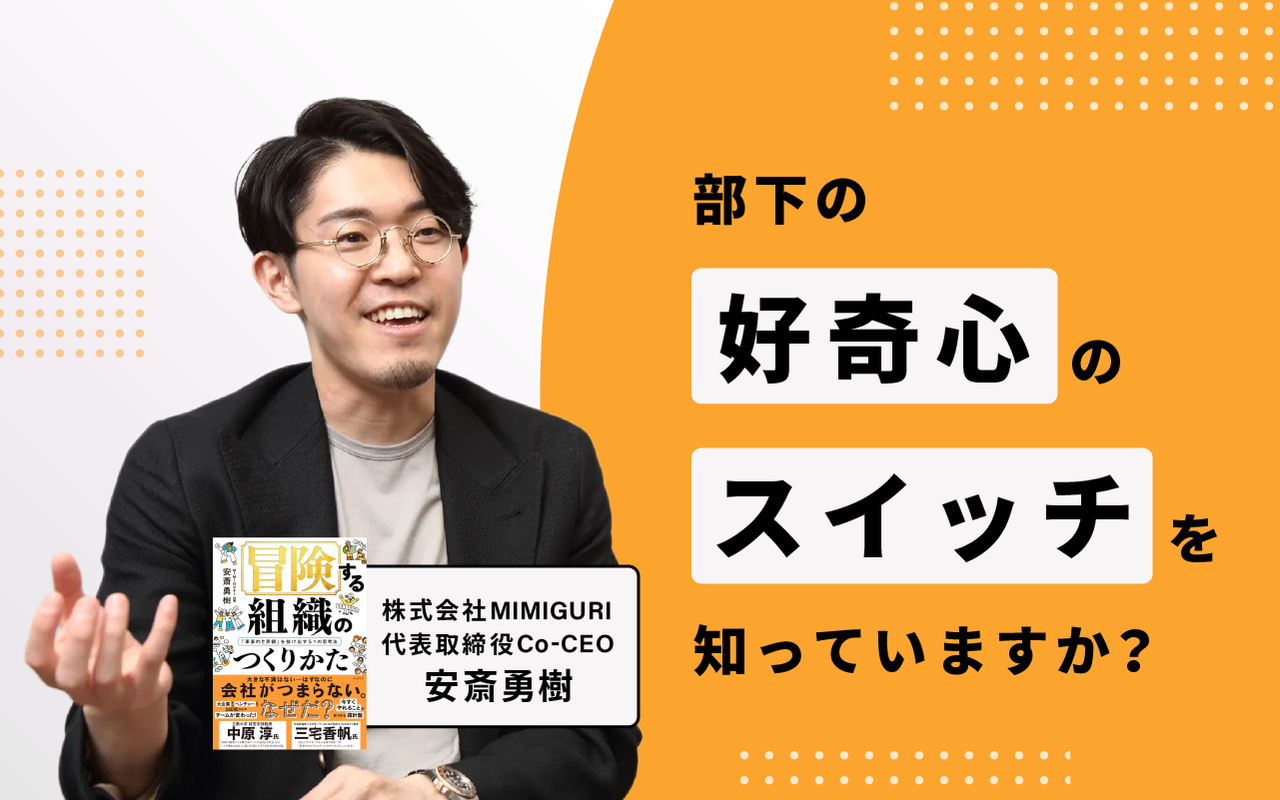これからのマネジャーについて、話そう。
マネジャーこそ「こんなの無理」「手伝ってほしい」と周りに言えばいい──サイボウズ副社長 山田理×ライツ社代表 大塚啓志郎

サイボウズ副社長、山田理の書籍『最軽量のマネジメント』が11月7日、サイボウズ式ブックスより刊行されました。2018年秋から進めてきた、新しいマネジメントを考える本プロジェクトがついに1冊の本に……!
マネジャーとして現場を率いる立場にある人は「こういうマネジメントをすべき」「こんなリーダーが理想」「マネジャーはチームで最も有能でなければならない」など、世の中でいう“理想のマネジャー像”を持っていることが多いのではないでしょうか。
しかし、20数年前にサイボウズに転職し、一社員としてジョインしてから、副社長として、管理部門の責任者として、そして一人のマネジャーとして、「100人100通りの働き方」を実現するまで動いてきた山田自身が、唯一自信を持って言えるのは「マネジメントって、ホンマに難しい」だといいます。
本書の発売に伴い、山田と本書を発行・編集したライツ社の代表大塚啓志郎さんが対談。いま、本書を出した理由やそこに込めた思いについて語りました。
風土が変わらないと、マネジメントも変わらない


でも、僕より上の先輩がどっと退職した時期があったんです。誰かがマネジャー職をしないといけないから、20代後半の若さで部長になって、経営会議に出るようになった頃、悩んでましたねぇ。
マネジャーって、どうして悩んでしまうんでしょう。

大塚啓志郎(おおつか・けいしろう)さん。編集者・ライツ社代表。1986年兵庫生まれ。大学を卒業後、京都の出版社で編集長を務めたあと30歳で独立。2016年9月、故郷の明石市でライツ社を創業。「write,right,light 書く力で、まっすぐに、照らす」を合言葉に出版活動を展開。編集した近刊は、ヨシダナギ『HEROES』、中村朱美『売上を、減らそう。』など

でも、その代わりになる新しいやり方を考えるところまではいってない。というのは、「昭和のやり方」で上手くいった高度成長期の記憶があるし、今でも昭和のやり方でそれなりに上手くいくから。






成果至上主義に走った会社のマネジメントは完全に崩壊していて、「このやり方、違うな。続けてたらマズいな」と実感できたんだと思います。
でも、「このやり方じゃダメだな」って気づきにくい社会の仕組みがある。これは今も変わらないんじゃないかな。

山田理(やまだ・おさむ)。サイボウズ 取締役副社長 兼 サイボウズUSA(Kintone Corporation)社長。1992年日本興業銀行入行。2000年にサイボウズへ転職し、責任者として財務、人事および法務部門を担当し、同社の人事制度・教育研修制度の構築を手がける。2014年からグローバルへの事業拡大を企図し、米国現地法人立ち上げのためサンフランシスコに赴任し、現在に至る

でも、本にメインとして書かれてあるのは、「ザツダン」と「情報の徹底公開」と「説明責任と質問責任」という「風土」に関する3つだけで、実際はとてもシンプルだと感じました。

マネジャーがすべてを背負う必要なんてない

兵庫県にいらっしゃる大塚さんとの対談は、テレビ会議システムを使って行われました

働き方改革が始まって、人々の働き方も変わったけど、マネジャーへの理想像は変わってない。それに気づいてもらう本になっていると思います。



それぞれ専門としてやっている彼らに任せて、代わりにマネジャーとして誰がどんなことを話しているのか、誰のどんなところが信頼できるのか、逆に信頼できないのかを知る方が大事だなと思ったからです。
そのために、とにかくたくさん「ザツダン(※)」をしていた時期があります。
(*)サイボウズで行っている1on1であり、「雑談」として何でも話していい時間。制度やルールとして決まっているものではなく、多くのマネジャーが自然発生的に行っている。目的はコミュニケーションの量を増やし、メンバーの状況を知ること。


でも、諦めるとかやめるっていうのは、結果的に新しいチャンスを生むことになると思うんです。


マネジャーは「こんなの無理です」「手伝ってほしい」と周りに言えばいいんです。

最軽量のマネジメントを実施することでみんなが自立して、最軽量のマネジメントはいつか最軽量のチームになっていくのかなと思いました。



マネジャーを「肩の荷が下りた」状態にしたい

若い人が「自分でもやってみよう」と、アクションを起こしてくれたらうれしいです。一番うれしいのは「肩の荷が下りた」と言ってくれることかな。
マネジャーとして辛さを感じている40%の人たちは、2冊買って1冊を上司に渡したりするのかな。それを読んだ上司が「新しい時代のマネジャーってこんな感じなんだな。応援したいな」と感じてくれるのもうれしいですよね。



おじさんたちははじめのうちは斜に構えて聞いてるんですけど、どんどん前のめりになるんですね。終了後「いい話だった!」と言われることもあります。
そんなとき、おじさんたちも悩んでいて、でもどうすればいいかわからないんだな、と感じるんですよ。


僕の理想は、若いマネジャーが最軽量のマネジメントをし、チームのメンバーは一緒に支えて役割分担をする。そして、マネジャーの上にいる人たちも共感によって、世代を問わず一緒に時代を作っていく流れが生まれることなんです。

普通の企業はそれをこれから体験するんですよね。10年前、周りからどんな反応がありましたか。


現場が成長しないといけないという大前提もあるし、成長したいという思いもある。数字を上げながらそれもやれってどうなの? と言われました。
一方で、現場社員は制度に賛成しているから、マネジャーが悪者になっていく構図がありました。


でも、時短にしてフレキシブルに働く人は、よりがんばるようになって、アウトプットの質と量が以前と変わらない。そんなプラスの展開も見られるようになりました。


マネジャーの言葉もどんどん変わっていきましたね。


多くの人がフレキシブルに働くのをマネジメントするのは大変なんです。組織が大きくなればなるほど難しい。


昭和世代もミレニアル世代もこれからの令和世代も、誰もが自分の経験を活かして上手くいったところ、上手くいかなかったところ、でもこうありたい、こうなるに違いないという理想を掲げて、チームワークを作ってほしいなぁ。



(*)大企業の若手有志団体による実践共同体。「大企業を変えること」を選んだ若手社員一人ひとりがつながり、希望を見出し、行動している。大企業からチャレンジする空気を作り出し、組織を活性化し、社会をより良くするための活動を行う。パナソニックや三越伊勢丹ホールディングス、東急グループなど、多種多様な大企業が参加。
SNSシェア
執筆
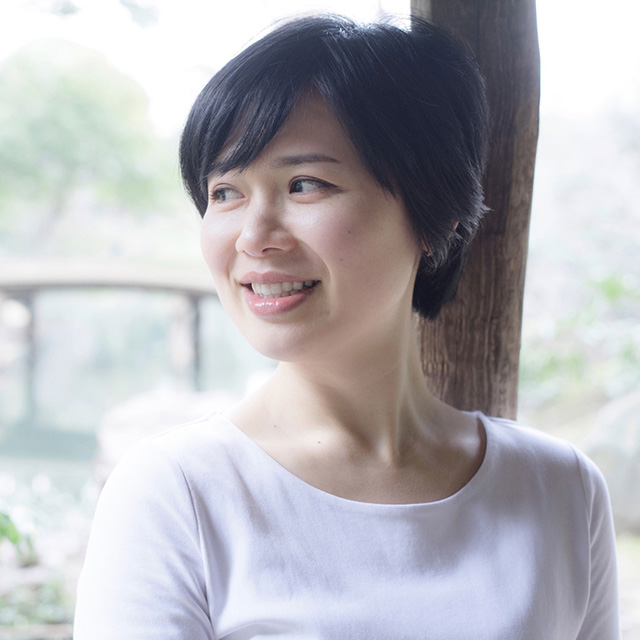
撮影・イラスト

高橋団
2019年に新卒でサイボウズに入社。サイボウズ式初の新人編集部員。神奈川出身。大学では学生記者として活動。スポーツとチームワークに興味があります。複業でスポーツを中心に写真を撮っています。
編集