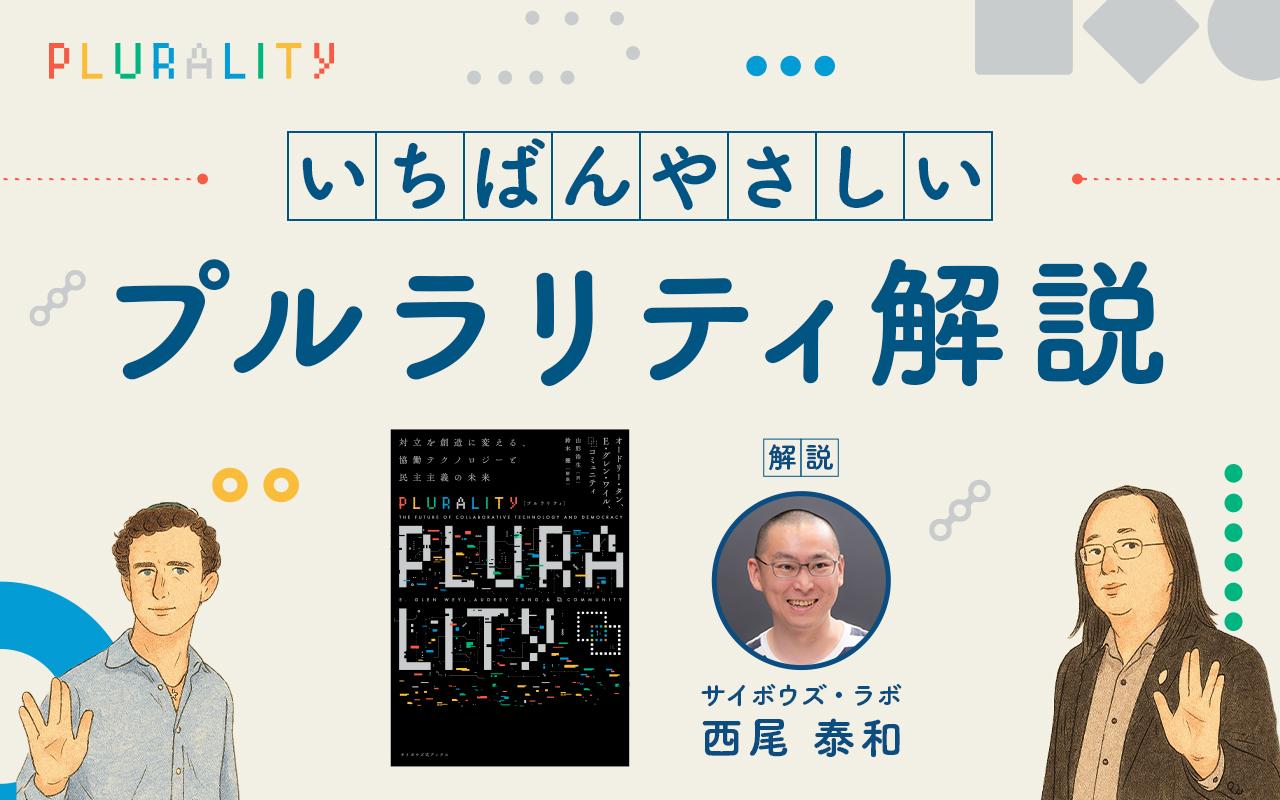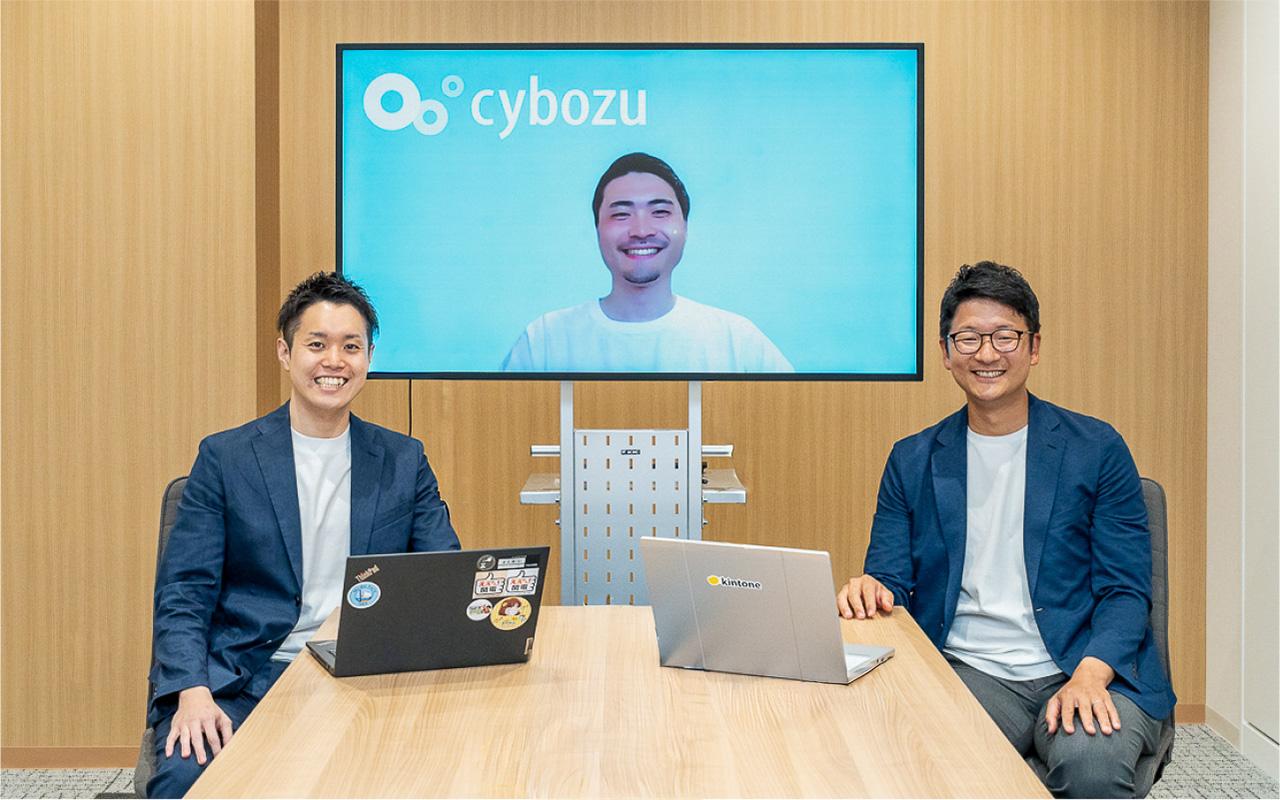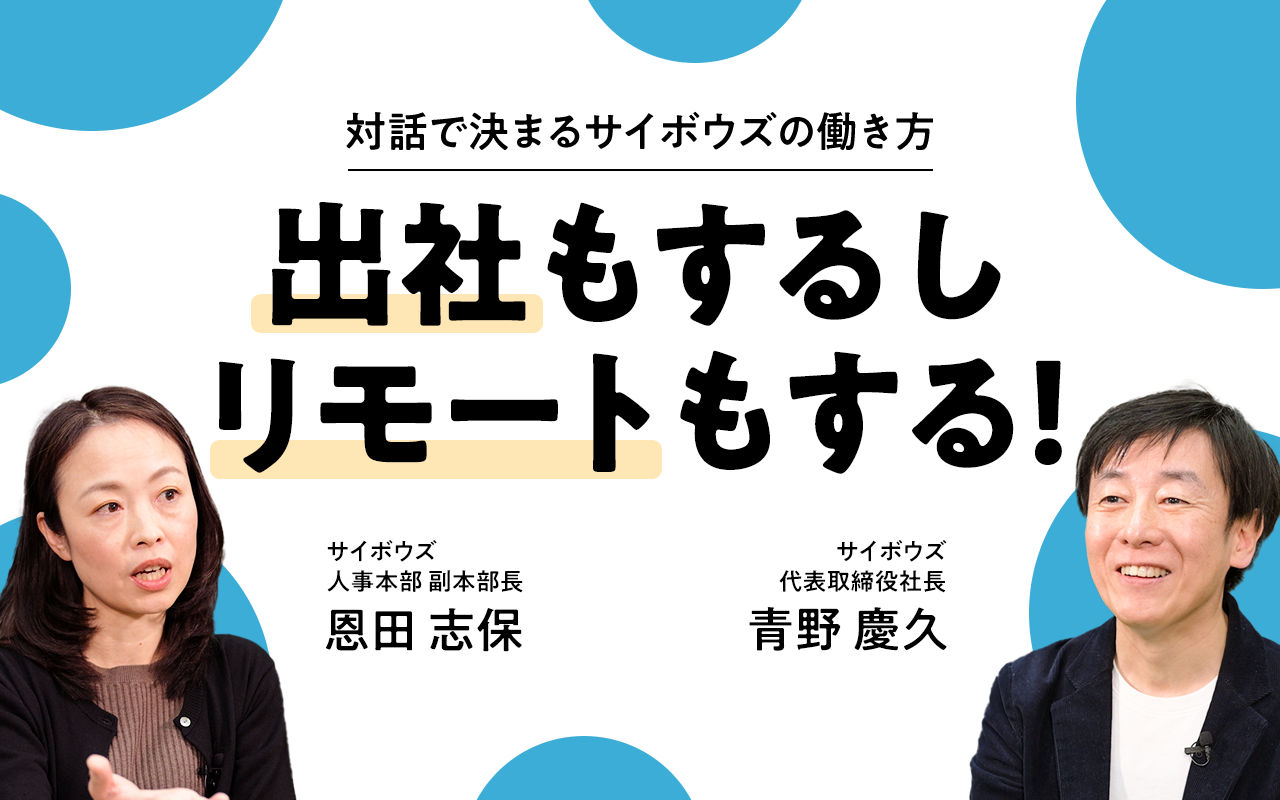大ザツダン
小さな変化を積み重ねた先に、大きな変革が生まれる。 社内が「腹落ち」する意思決定のあり方 ──アルペン 二十軒翔×サイボウズ 栗山圭太

大規模な組織では、現場の納得感を得ながら変革を進める難しさに直面することがあります。
社員数1000人を超えるサイボウズも例外ではなく、経営層の考え方と現場のニーズとのギャップに悩んでいます。
そこで、サイボウズのマーケティング本部長である栗山圭太は、スポーツ用品専門店を全国に約400店舗展開する株式会社アルペンに注目。
意思決定の過程や現場から納得感を得るための工夫について、同社専務取締役COO の二十軒 翔さんに迫りました。
EC全盛時代に、リアル店舗の旗艦店『Alpen TOKYO』を出店したワケ

新宿の『Alpen TOKYO』は、誰が最初に出店を提案したんですか?

前職のときは東京に住んでいて、そのころのアルペンのイメージといえば、やっぱりスキーとかウィンター系だったんですよね。
でも、実際のアルペンって、それ以外でもおもしろい取り組みを行っています。そのことをもっと多くの人に知ってもらいたいという想いを形にしたのが『Alpen TOKYO』です。

二十軒 翔(にじっけん・しょう)。東京大学法学部を卒業後、外資系戦略コンサルティング大手ベイン・アンド・カンパニーに入社。コンサルタントとしてキャリアを積む。2014年、より明確な方向性を求めてアルペンに転職。事業部長からスタートし、2年後には、経営戦略を担当する役員に就任。その後、人事制度の改革、物流やシステムの見直し、店舗開発、EC立ち上げなどの取り組みを通じて、企業の成長に寄与


「出店するなら、多くの人が集まる新宿駅周辺がいいだろう」と考えて、新宿の街を1人で歩き回ったり、店舗開発チームといっしょに情報収集をスタートしたりしたのが始まりです。


ただ、それだけでは目指すべき姿にはなれません。もっと違う取り組みもしなければいけないと考えた結果、関東圏でシェアを拡大することにしたんです。


われわれの取引先には海外の取引先もありますが、彼らが見ている日本市場というのは東京の市場が中心です。そこでのプレゼンスが全然足りていないと感じていました。



いきなり出店の話から始まったわけじゃなくて、大きなビジョンから出店の話がスタートしているので、みんなのなかで腹落ちしていたのかなと。


栗山 圭太(くりやま・けいた)。執行役員事業戦略室長 兼 マーケティング本部長。2003年、新卒で入った証券会社を辞め、第二新卒としてサイボウズに入社。公共営業、大阪営業所の立ち上げなどを経て、「サイボウズ Office」「kintone」のプロダクトマネージャーを経験。その後自身の強い希望で営業に戻り、ここ数年はアジアの拡販にも注力。アジア10カ国を訪問し、パートナー企業とのリレーションシップを図っている
「議論の末、たどり着いた」という納得感が「現場の腹落ち」につながる


ただ、基本から外れちゃうときもあるじゃないですか。わたしもサイボウズの経営に携わる立場なので、その難しさも感じているところで……。
アルペンでは、どんな工夫をされているんですか?







「世界にはどんな会社があって、どう活躍しているんだろう?」「なぜ、成長が実現できているのだろう?」こういうことを考えることで、自社とのギャップや新たな視点に気づけます。
おかげで、「アルペンが大きく変わるためには、国内の競合店だけを見るんじゃなくて、もっと広い視点が必要だ」ということの理解が深まったようです。






「毎年大変なんだよ(笑)」と言いながらも、楽しみにしてくれているメンバーがすごく多いんです。
合宿でいっしょにビジョンをつくり上げて、『Alpen TOKYO』の出店にも納得感を得られたことは、スムーズな開店準備にもつながって。
出店決定からオープンまで半年間しかなく、負荷のかかる業務でしたが、多くの社員が積極的に動いてくれました。



「次は何をやるんですか?」「おもしろい企画を持っているんじゃないですか?」とわたしに聞くメンバーも増えてきました。
変化への抵抗感じゃなくて、「次はどんな変化があるんだろう?」とワクワクしてもらえる環境になってきたなあと実感しています。

小さく変化し続けることが、大きな変化を生み出す

いまのサイボウズは売り上げが順調に伸びて安定した収益を得られているおかげか、社内には落ち着いた雰囲気が漂っているんですよね。
この雰囲気のなかで、社内に変化を促そうとしても、「うまくいっているから、このままでいいじゃないか」という意見もあるんです。
社員の意識や組織のベクトルを変えていくコツがあれば、ぜひ教えていただきたいなと。

ただ、わたしの仕事は変化の種を見つけて、促すことだと思うんです。
われわれのビジネスは多領域に広がっていて、部署も多いので、「どこだったら変えられそうか?」を日々探しています。



組織全体を見渡してみると、大きく伸びそうな部分もあれば、ちょっと我慢しなきゃいけない部分もあって。でも、伸びると思う部分にアクセルを踏まないと、結局ちょっとの成長で終わっちゃうんですよね。




それを繰り返していくと、「社内のどこかは常に変化している」という状態がつくられてくるんですよね。


われわれとしても、すべてを一気に変えることは難しいので、少しずつ変えていけたほうがいいですよね。それが成功の確率を上げているのかなと思っています。


もちろん、すべての変革が成功するわけではないんですけど、成功事例を全社に共有していくことで、ほかの部署やプロジェクトにいい影響を与えることもあります。そうやって小さな変革を積み重ねた結果、数年後には大きな変化を遂げられると考えているんです。
変化を引き起こすには「納得感のある評価基準」も必要

組織のいろいろな場所で、変化した人たちや、変化をリードした人たちを評価していく。その人たちが昇進していく。その様子を、みんなやっぱり見ているんですよね。


そういった評価と、周りが変化し続ける環境の組み合わせで、「あ、自分も変わっていったらこうなれるのかな」っていう人たちが出てくると、会社が変化してくんじゃないかなと。



その基準には「どれだけ新しいことに挑戦し、変化をもたらしたか」「変化に対してリーダーシップをどれだけ発揮したか」といった挑戦的な要素も加味して、アルペンのビジョンと評価基準を一致させたんです。


そこで、評価基準を統一する場を設けました。社員の評価を決めるとき、上司同士が集まって自分の部下の評価を持ち寄って、ほかの社員と評価について意見交換をしています。



評価に対する期待が生まれて、個人の変化が促されることで、会社自体も変わっていくことができるのだと思います。
「アルペンのDNA」を守りながら、3000人のマネージメントに挑む

そこで、約3000人を管理するためのマネジメントチームをお持ちだと思うんですけれども、これはどうやって構築されているのでしょうか?

ここ10年間で、組織の体制を少しずつ整理し、いまの形になりました。


とはいえ、最初は「誰に任せたらいいのか」を考えるのは、正直すごく難しくて……。
適任者が社内にみつからなければ、社外に目を向けて人を探してくる必要もあります。ずっと、誰がいいんだろう? というのを考え続けています。


ただ、その人がアルペンで即座に能力を発揮できるとは限りません。だからといって、簡単に外してしまうわけにもいかないのが、組織の難しいところです。


結果として、現在の役員や部長は10年前とは大きく入れ替わっています。変化を受け入れ、新しい挑戦を推進できる人を高い役職に配置できているので、わたしが指示しなくても自発的に行動する組織に成長してきたかなと思います。


でも、そういう自分とは異なる考え方や強みを持った人を増やしていきたいです。そうした人たちを組織に迎え入れることで、会社の成長につながると信じています。





「変化に強いメンバー」が理想ではありますけど、やっぱり組織として変えてはいけない価値観もありますよね。そのバランスをどう考えていらっしゃるのでしょうか?

とくに人事については、社員の士気や組織文化に大きく影響するので、慎重な判断が必要です。周りの意見を必ず聞いて、「候補者が企業の文化や価値観と合致しているか」「チームに溶け込めそうか」などを確認した上で、人を採用しています。

最後に、「意思決定と組織の納得感」でいちばん大事にしていることを、改めて教えていただけますか。

組織を変えるにしても、納得してもらうにしても、一度やったからといって、うまくいくわけではありません。だからこそ、あきらめずにやり続けることが、いちばん大事なのだと考えています。
企画:神保麻希 執筆:流石香織 編集:モリヤワオン(ノオト)
サイボウズ式YouTubeで、対談動画を公開中!
SNSシェア
執筆

流石 香織
1987年生まれ、東京都在住。2014年からフリーライターとして活動。ビジネスやコミュニケーション、美容などのあらゆるテーマで、Web記事や書籍の執筆に携わる。
編集