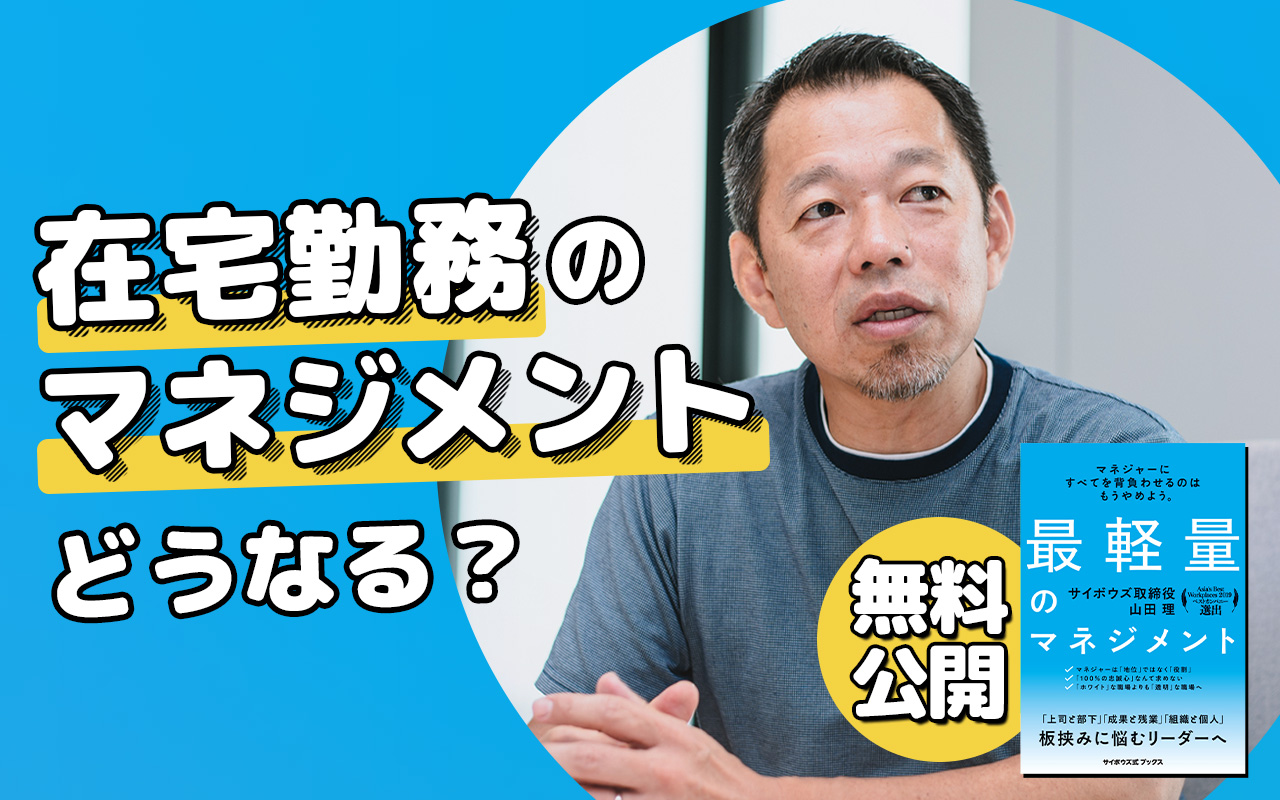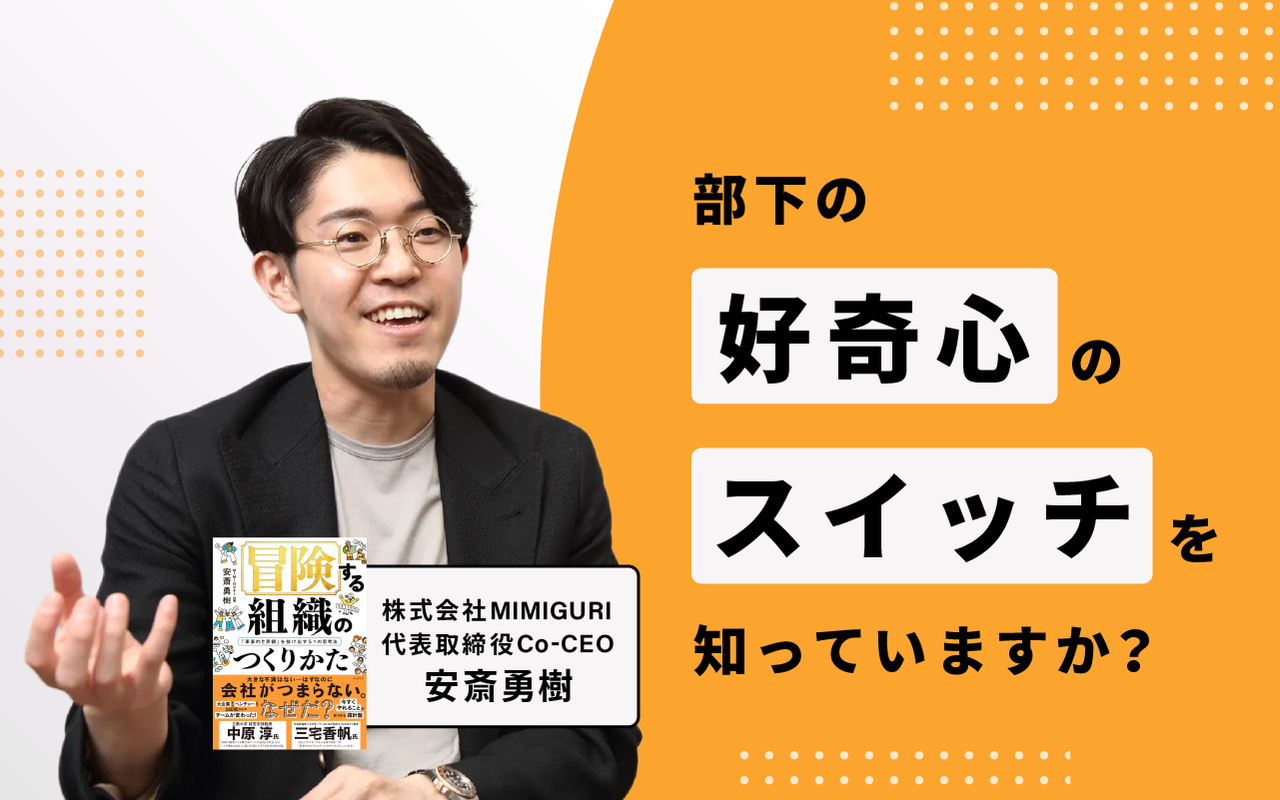これからのマネジャーについて、話そう。
「フラットな組織」は目指してなるのではなく、結果──部下と1on1をしたら、組織全体が見えてきた。ヤフー伊藤羊一×サイボウズ山田理

『1分で話せ』 の著者で、ヤフー企業内大学・Yahoo!アカデミア学長の伊藤羊一さんと、11月にマネジャーに関する本を上梓する予定のサイボウズ副社長・山田理のマネジメントについての対談の後編です。
前編では、それぞれのリーダー観を中心に話を聞きました。後編では、過去に350人の部下と1on1を実施し、数多くの場でマネジメントを経験してきた伊藤さんと、山田の実体験から、マネジメントのヒントを探っていきます。
ふたりの話から浮かび上がってきたのは、「人は思った以上にコミュニケーションが取れていない」という課題。その解決には、1on1やザツダンにヒントがありました。
マネジャーの業務は、コントロールすることでも、支配することでも、チェックすることでもない


今でも細かい課題はありますが、「マネジャーの業務は、コントロールすることでも、支配することでも、チェックすることでもない」という考えは、全社員に浸透しています。

伊藤羊一(いとう・よういち)。ヤフー株式会社 コーポレートエバンジェリスト・ヤフー企業内大学「Yahoo!アカデミア」学長。東京大学経済学部を卒業し、1990年日本興業銀行入行。企業金融、債券流動化、企業再生支援などに従事。2003年プラス株式会社に転じ、ジョインテックスカンパニーにてロジスティクス再編、事業再編・再生などを担当後、執行役員マーケティング本部長、ヴァイスプレジデントを歴任、経営と新規事業開発に携わる。2015年4月ヤフー株式会社に転じ、Yahoo!アカデミア本部長として、次世代リーダー育成を行う。著作『1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術』は32万部を超えるベストセラーに


(*)アドバイスではなく、「問いかけて聞く」ことで、相手からさまざまな考え方や行動の選択肢を引き出すよう支援すること



一方、定期的に1on1をして現状を話し合っていれば、評価を聞いたときに納得できるんですよね。

「こういうキャリアに進みたいならこの勉強したほうがいいよ」とか「こういう人に話を聞くといいよ」とか。
一人ひとりの話を聞いてみたら、組織全体が見えてきた
成果主義で評価する一方、業績も頭打ちになって離職率が28%になったときでした。

山田理(やまだ・おさむ)。サイボウズ 取締役副社長 兼 サイボウズUSA(Kintone Corporation)社長。1992年日本興業銀行入行。2000年にサイボウズへ転職し、責任者として財務、人事および法務部門を担当し、同社の人事制度・教育研修制度の構築を手がける。2014年からグローバルへの事業拡大を企図し、米国現地法人立ち上げのためサンフランシスコに赴任し、現在に至る
すると社員から「どうしてこんな制度があるんですか」というような、今まで聞かれなかった質問がポロポロ出てきたりして。
質問に答えながら、その内容をブログにまとめて、社内に周知していきました。


その言葉だけを聞くと、手が付けられない、大変なことが起こっているんじゃないかって思うじゃないですか。
でも、一人ひとりとザツダンして「それは具体的に誰が言っているの?」と聞くと、少しずつ状況がわかってきて。
全員と話すことで、全体像が見えるようになったんです。
フラットな関係だけを目的にせず、まずはザツダンや1on1の環境をつくること

僕が前職のプラス株式会社でカンパニーのヴァイスプレジデント、No.2になったときにひとまず部下350人と1on1しようと決めて実行しました。
人事部や周りからは「部下から要望を言われて実現できなかったらどうするんですか?」と言われて大反対されたんです。
でも「ひとまず聞いてみないとわかんないな」とスタートしたので、おそらく山田さんとスタンスは同じなんですよね。

事務一筋20年という方にとある営業所まで会いに行ったんです。会うなり「ライン長クラスの立場の人が会ってくれるなんて、思いもしませんでした」と涙が止まらない様子で。
その後見せられたノートには「こうしたら会社がよくなる」ってことがびっしり書かれていて。僕もウワーって泣いちゃいましたよ。


ザツダンすると、自分が持っている情報についてメンバーに聞かれたら答える。だから情報がオープンになって、自然とフラットになっていくんです。
そのことと、いい組織になることはリンクしていると思うんですよね。

だからフラットな状態は、結果なんだと思います。
無理やり心を開かせなくてもいい。まずはコミュニケーションのルートを開通させよう
僕はなかなかそういうことができなくて、最終的に人との距離の取り方を改めるようになりました。気が合う人とは、盛り上がって話せばいい。
一方、僕に対して心を開かない人に対しては、無理やり心を開かせようとせず、そのままの距離感で付き合えばいいのかなと思っているんです。


それを繰り返していくと、個別のメッセージが相談しやすいルートにもなる。
話が盛り上がらない、距離が縮まらない人もいるけど、全員とルートは開通していることが大事で。ルートを使うか使わないかは本人の自由ですしね。
人って思った以上にコミュニケーションが取れていない

それをそのまま放置せずに、ポジティブなことでもネガティブなことでも、伝えることで相手を認める。承認するだけでも、距離って縮まってくるのかなって思うんですよね。

社内をプラプラ歩きながら話すんです。フロアを歩きながら「いいペン買ったね」「そのお菓子おいしそうだねー。いいなー」とか。

1on1はオフィシャルな仕組み。一方、MBWAはアンオフィシャルなことが聞けるんです。

顔が見えていないと、頭でっかちな施策しか考えられないじゃないですか。

「50人と雑談する時間なんてないでしょ」ってよく言われますが、生産性がないミーティングをやるくらいならザツダンをしたほうがいいですよ。

マネジャーはオーガナイザー。一人ひとりリスペクトして対応すること
「このチームでこのゴールを目指すために、どんな方法があると思う?」と聞きつつ、「その代わり意思決定は僕がさせてもらうからね」と伝えて。
マネジャーも今までの上から下への命令型のようなマネジメントから、組織を編成して盛り上げる、オーガナイザーのようなあり方に変わっていくのではないかと思うんですよね。


結局チームのゴールは1つだけど、その役割をどう果たすかは、コンディションやモチベーションによって変わるので、人それぞれ。
大事なのは一人ひとりの状況を認識しておくこと。それでアサインも違ってきますよね。

ひとつは、安心安全で行きたくなるような職場環境にすること。もうひとつは、個人のパフォーマンスを最大化すること。


1on1をすることで、その人のことが理解できて適材適所な配属ができるかもしれないし、できることを増やせるかもしれない。
でも所属や承認の欲求をすっ飛ばして、自己実現、成長、目標を考えている職場やマネジメントが多い気がするんです。
「所属している」という欲求でさえ十分満たされていない人は、意外と今の世の中で多いのではないかと思っていて。

それがその人の自信になり、自己実現に向かってくと思うんです。

リアルに感じてもらうためにはリアルで話したほうがいいから。

SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集