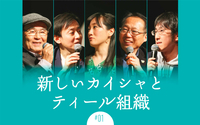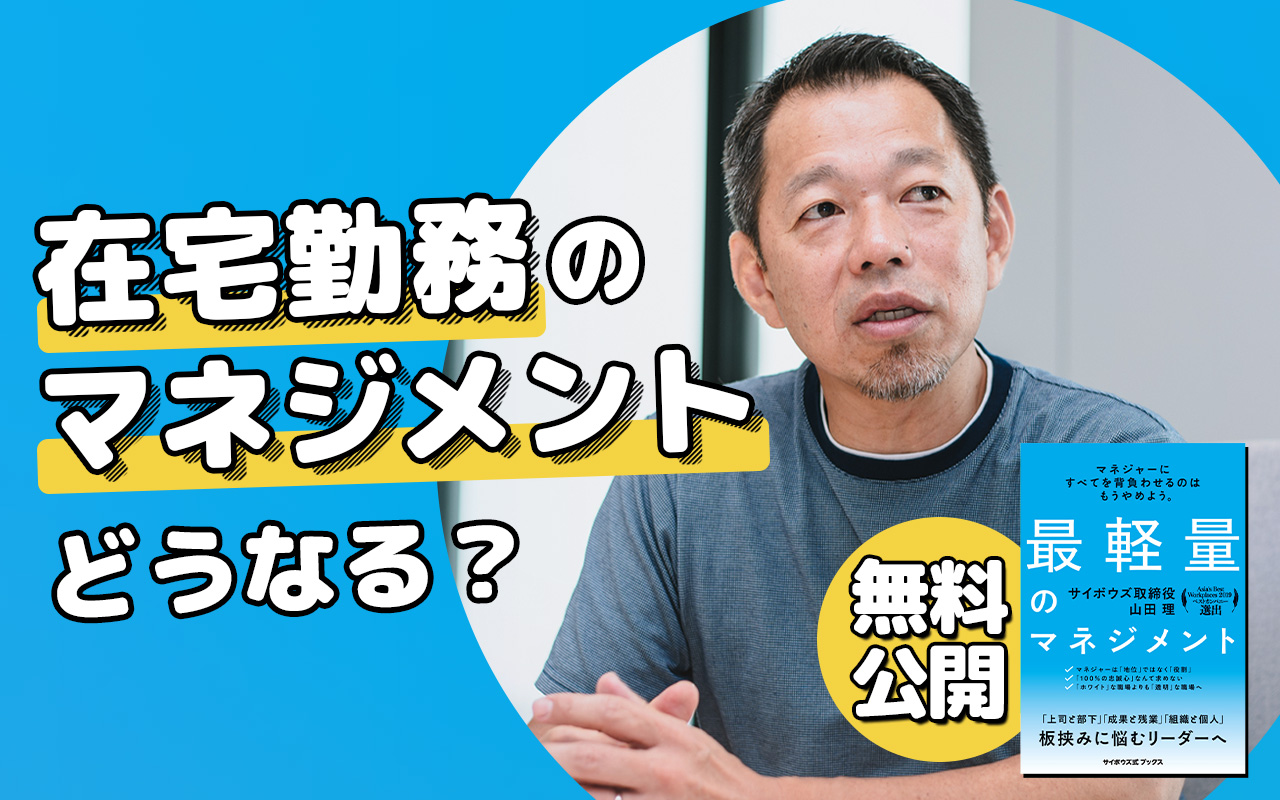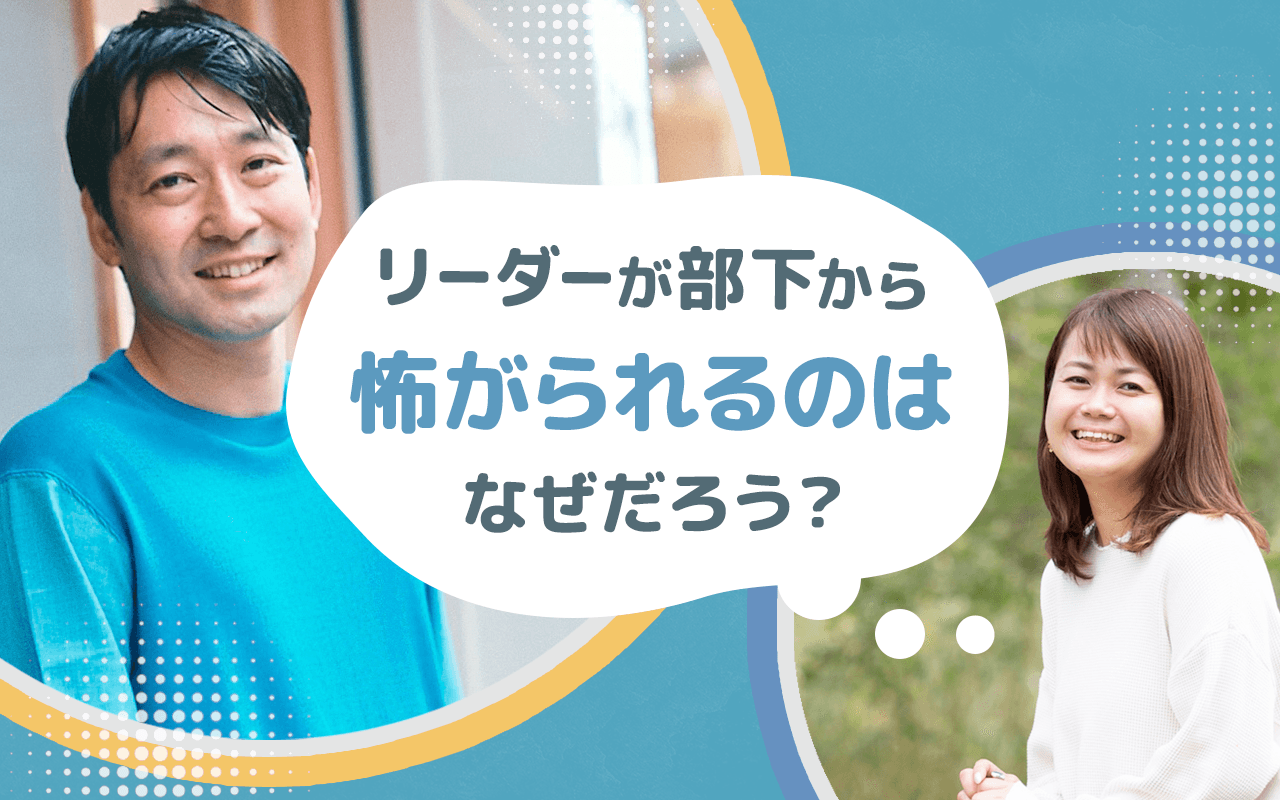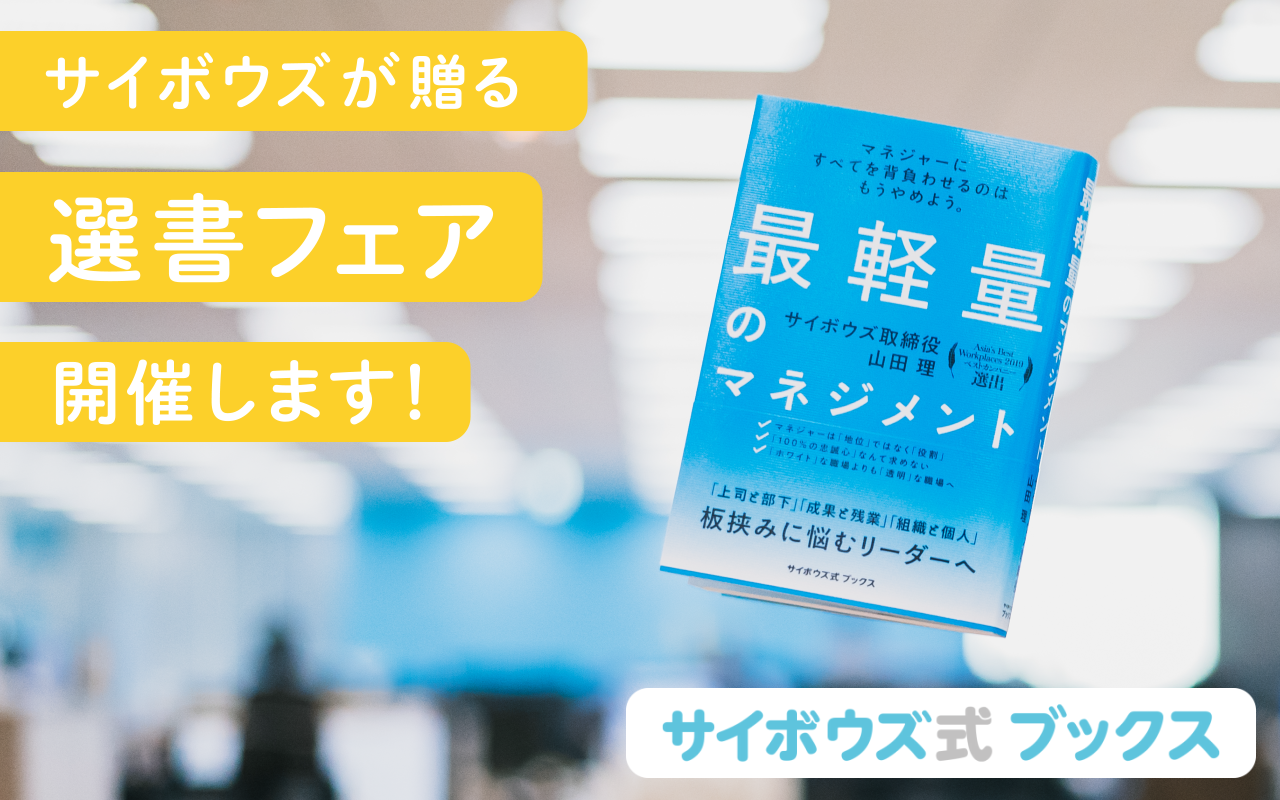これからのマネジャーについて、話そう。
人に値段をつけるって怖いんですよ。だって、正しい値段なんてあるわけないんですから──わざわざ 平田はる香×サイボウズ 山田理

長野県東御市御牧原にある、小さなパンと日用品の店「わざわざ」。最寄りの駅から車で15分、歩くと1時間くらいかかります。店名の由来は「わざわざ来てくださってありがとうございます」という感謝の意から。
経営者の平田はる香さんが2018年に公開したブログには、「山の上」という不便な場所にあるわざわざが、どのように成長してきたのか、数字のデータからさまざまな試みまで惜しみなく書かれており、大きな話題を呼びました。
店長である平田さんがひとりで始めたお店が、2018年度の決算は2億5千万円、スタッフは16名の組織へと成長。それにともない、「相思相愛採用」や「評価しない人事制度」などユニークな制度をつくり、チャレンジを続けています。
そんな新しい組織づくりに取り組む平田さんをサイボウズのオフィスにお招きし、マネジャーに関する本を8月に上梓予定のサイボウズ副社長 山田理との対談イベントを開催しました。テーマは「新しい組織作りやマネジメントを考える」です。
給料を一律にしたワケは「人事」をなくしたかったから




業績に応じてボーナスは出して、2017年度の実績でいえば、5カ月分は出しているので。


わざわざは製造・小売の会社なので、原価をかけて仕入れて、つくって売る、商売の基本のような形で経営しています。
何をしているのか形が残りにくい、何が正しいのかもわからない人事評価よりも、つくることや売ることに時間やお金を回したい。人事の仕事をなくして、もっと生産性を上げたいと思ったんです。

平田はる香(ひらた・はるか)。株式会社わざわざ代表取締役。1976年生まれ、東京生まれ静岡育ち。1996年川村都スタイリストスクール卒業。2002年に夫の転勤により長野県に移住。2009年にわざわざを一人で開業。前職はWEBデザイナーでありながらも、パン焼きにハマり、元々好きだった日用品の収集と掛け合わせた店、パンと日用品の店「わざわざ」を開業する。段々とスタッフが増えていったことで、店舗や事業を拡張し、2017年に株式会社わざわざ設立。二児の母。


それまでは人が入ったり辞めたりが多かったので、採用の課題については一旦クリアできたのかなと思っています。
人は人を正当に評価できない。正しい値段なんてあるわけない


評価する側に回った人ならわかると思いますが、怖いんですよ。人に値段をつける、ってことは。だって、正しい値段なんてあるわけないんですから。

山田 理(やまだ・おさむ)。サイボウズ 取締役副社長 兼 サイボウズUSA(Kintone Corporation)社長。1992年日本興業銀行入行。2000年にサイボウズへ転職し、責任者として財務、人事および法務部門を担当し、同社の人事制度・教育研修制度の構築を手がける。2014年からグローバルへの事業拡大を企図し、米国現地法人立ち上げのためサンフランシスコに赴任し、現在に至る。

自分自身の人生を振り返ったとき、正当な評価をされていなかったと感じることが多かったので。


忘れ物をしたり、遅刻をしたり、生活態度がよくなかったんです。そうすると、テストの成績が私よりも悪いのに、宿題をやっている子のほうがいい成績がついて。
「先生はどういう評価をしたんだろう?」という違和感がずっと残っているんです。



「わざわざで働きたい」と感じる魅力が、お金以外の部分にあるからこそ、成り立つ仕組みなんでしょう。

「年功序列」ってすごい。評価なんてできるわけがないんだから

僕はサイボウズに入る前は銀行で働いていて、「年功序列なんて必要ない」と思っていました。
だからこそサイボウズに入ったとき、年功序列とは真逆の成果主義を採用したんですよ。


半期に一度の評価で、最低の評価を2回とったら辞めてもらうように言っていた。それが、お互いのためだと思っていたんですよ。


そこで大きく反省して、働きやすい環境を整えることを第一に改善していくようになりました。


毎年歳を重ねたら、自動的に給料が上がっていく。そして、みんながそれが当然だと受け入れている。改めてこの制度をつくって実現している会社はすごいな、って感動しました。
マネジャーは「地位」ではなく「役割」に変化した




社員が手に入れた情報が課長に、課長から部長に、部長から取締役に……という流れで、大事な情報がすべて社長のもとに集まってくる。情報の価値と一緒に権限が集まり、そこにお金がついていっていた。


となると「俺がこの情報をもっているから権限がある」という考えが機能しなくなったんですね。情報格差が価値を生まなくなった。


開示できる情報はオープンにして、みんなが簡単にアクセスできる状態にしたほうが、結果的にアイデアが出やすくなるのではないか、と考えているんです。
「こういうことで悩んでいます」と情報を開示したら「だったら私はこういう解決策をもっています」と言ってもらえる。それが情報共有の世界。
情報をもっている人が限定されていたときは、一人ひとりが解決しないといけなかったので個人戦でした。でも、これからは団体戦になりますよね。
情報を開示すると、外部から新たな情報を得られる



そうしたら、「僕がこの情報を世界中の研究者に見せることで、この研究が加速するから」と教えてもらって。私、感動したんですね。


わざわざを始めてからも、売り上げの情報から石窯の設計図まで、すべて外部にオープンにしたんです。
そうすることで、結果的に自分も情報を得られますからね。

主体性は、選択肢がたくさんあってこそ成り立つし、そのためには情報が必要不可欠ですね。
マネジャーに必要なのは「謝ること」

平田さんは、何が大事だと思いますか。

いずれも共通して大事だと思っているのは、「とりあえず、バカでいること」です。




うまくいけばメンバーを褒めて、失敗したら「決定した僕に責任があります」と自分が謝る。それがマネジャーの大切な仕事。
本当に謝る覚悟ができているなら、しっかりと意思決定をするために情報収集をすると思うんです。そして、意思決定をして最終的にはメンバーに任せる。

以前、スタッフに「仕事の状況、いまどんな感じ?」と聞いたんです。そのスタッフはしっかりと状況を把握していて、いろいろと教えてくれた。それを聞いた上で仕事を任せたんです。


「あなたのほうが私よりもよく知っているようだったから、この場は任せたつもりだったよ」と伝えたら、わかってくれて、ほっとしましたね。
マネジャーがすべきは「放置」ではなく「放任」

でも、僕の中では「放置」ではなくて「放任」だと思っているんです。
放任は、任せた上で、うまくいっていないところはできる限りサポートすること。放置の場合は、見ることもないですから。

情報を確認しながら、できそうなことがあったら助ける。失敗をしそうな人がいたら、事前に助けてあげること。

ひとりでなんでもできればいいですが、できないことのほうが多いと思うので。
だから、マネジャーって「権限」というより、「場をオーガナイズする役割」のほうがしっくりくると思うんですよ。

人間関係のわだかまりをなくしたり、人材が足りてなかったら人を見つけてきたり、空間が狭かったらオフィスを借りてきたり。
働きやすい環境を整えることが、最善の役割ではないでしょうか。マネジメントの考え方としても同じで、「その場をまわりやすくサポートしていく」ということなんですよね。



コーチングの本を何冊も買って、心を動かす方法や戦略を考えてお手上げとなるよりは、まずマネジャーの仕事をほかの人に渡したり、高いスキルがなくてもできるように大衆化していくことが重要だと思います。
SNSシェア
執筆

撮影・イラスト

編集